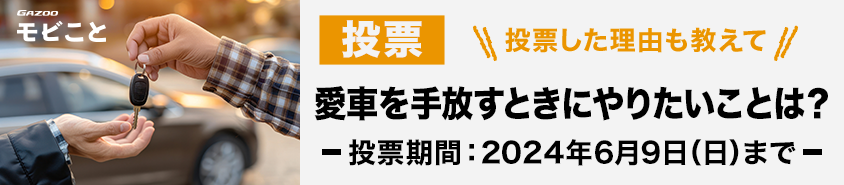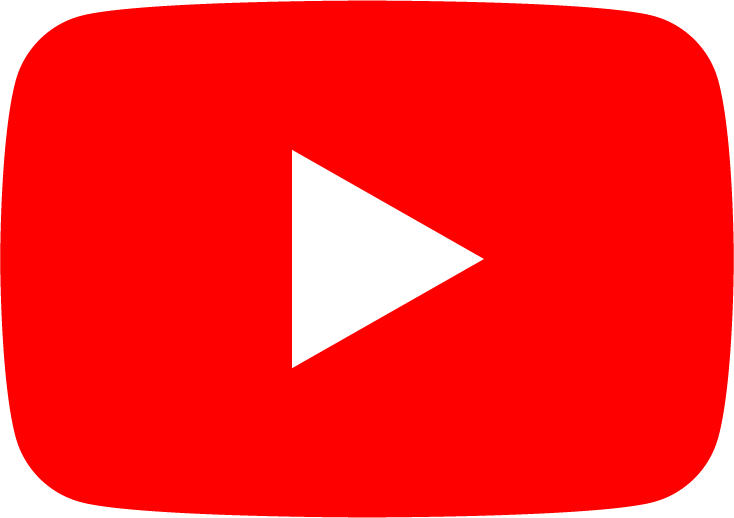幻のホンダ最強のファンカー! 初代「シティ」を振り返る・・・懐かしの名車をプレイバック
1981年にデビューし、独特のトールボーイスタイルで人気を集めた初代「ホンダ・シティ」。自動車業界全体に現代とは異なる自由さがあった時代だが、世間はホンダにそれ以上を求めていたし、ホンダもまた個性こそがアイデンティティーだと理解していた。その発露ともいえる愉快なハッチバックだった。
シティ カブリオレを買った
今から14年前、不躾(ぶしつけ)小沢コージは真っ赤なシティ カブリオレを買いました。ぶっちゃけ完全なる思い付きです。細かな経緯は忘れましたが、夜中に『カーセンサー』をパラパラと眺めつつ物件発見。「え? 動くシティ カブリオレがたった10万円(確か)!」「置いてある店、湘南じゃん」「買うっきゃない」とひらめいたことを覚えております。
もともと1980年代のホンダ車には憧れや思い入れがあり、その翌日、後先考えずに現物を見に行って即決です。当時ですでに30年落ち近かったですし、故障もするはず。しかも古いホンダ車はパーツが豊富ではないと聞いてましたが、なんとかなるでしょうと。
ただ買ったら最後、見てかわいいのはもちろん普通の街乗りだけでも楽しく、ついでに同世代のおっさんからの愛され性能ったらない。その後はバラ色の日々で、なぜ売ってしまったのか今でも悔やまれます。
とはいえ当時は乗らないクルマを置くスペースがなかったのと、家族をリアシートに乗せて走ってたときにふと「怖いな」と。追突されたらヤバいと数年後に手放しました。そもそも剛性の低いオープンボディーなので。今考えるともったいなかった気がします。
タイヤが4つのバイクのような存在
それはさておき1981年生まれの初代シティ(小沢の車は1984~1985年式ぐらいのカブリオレ)がなぜそんなに楽しいのか? 思い出が美しすぎるだけじゃないのか? いやいや違います。そこには明確な理由があるのです。
まずはあり得ないサイズと軽さ。初代シティは今の軽より短い3.3m強(カブリオレは3.4m強)の全長に、1.5m台の全幅と1.4m台の全高というユニークなディメンション。エンジンは1.2リッター直4 SOHCでたった67PSの最高出力&10.0kgf・mの最大トルク。しかしそのぶん車重はほぼ600kg台(カブリオレは800kg前後)と軽く、今のクルマにはない生々しさの塊でした。
アクセルやブレーキ、ステアリングのダイレクト感はもちろん、地面から伝わってくる振動や操作系の手応え、エンジンサウンドが妙に生々しい。逆に言うとボディー剛性が低いFFマシンがゆえにステアリングからのキックバックはすごく、コーナリング中は油断できません。オマケに初期型シティはパワステが付いてなかったので据え切りが重い重い。
ただ当時はそれすら楽しく、いろいろ取材に出かけました。まさにタイヤが4つ付いたバイクのようなもので、スーパーで売ってるラップ入りのトゲなしキュウリではなく、隣の畑から取ってきた土の匂いのするもぎたてにかぶりつくようなおいしさがあったのです。
最近「マツダ・ロードスター」の開発主査に「車重1t切りカーの素晴らしさ」を聞きました。軽さにはすべてのクルマの風味を研ぎ澄ます偉大なる効果があります。
オマケに当時のホンダ車には明らかに他メーカーにない個性最優先のつくりがなされていました。当時のシティや「シビック」を開発した名エンジニアの伊藤博之さんに聞いたことがあります。シビックは3代目で突然リアをスパッと切り取ったようなモダンデザインに生まれ変わりますが、なぜそんな大胆チェンジができたかというと、「2代目(シビック)はクルマとしてはできてたよ。だけど世の中の人がインパクトを感じてくれない。新しいシビックが出た! とは言ってくれないんだよね」と。
イイものさえつくればいい
シティに関してもそうです。「(あのころは)新しい息吹がないとね、ホンダの次の時代を築けないと思ってたから」と。
結果生まれたのが量産車にあるまじきリトラクタブルヘッドライト付きの2代目「インテグラ」や3代目「アコード」であり、当時のマスキー法をいち早くクリアしたCVCCエンジンであり、モダンな「ワンダーシビック」であり、かつてないトールボーイの初代シティだったのです。
今となっては1.4m後半の全高はなんてことありませんが、全長と全幅の短さを考えるとまさにリアル版「チョロQ」。オモチャのようなサイズで、確か当時の大人気漫画『Dr.スランプ』にも出ていたと思います。
ディテールを見ても今ほど厳しい衝突安全基準はなかったのでホンダの個性的デザイン全開! ピラーの細さはもちろんフロア構造も薄さが伝わってきて、剛性感は今ひとつ。当時のホンダは都市伝説的に「鉄板が薄い」と言われてましたが、正誤はともかく言われるだけの味わいがあり、当時はそれが許容されていたのです。
さらに当時のホンダはトヨタや日産より多少値づけが高くても、カッコ良くて楽しく個性的だったので値引きなしで売れたといいます。当時の国内最後発メーカー(後にミツオカが現れる)として、意図的に他にはない個性で勝負しており、それに見合う発想と許される時代背景があったのです。前出の伊藤さんは言いました。
「オヤジ(本田宗一郎)は“イイモノさえつくればいい”と。“お金がどうこうじゃなくてイイモノをつくれば売れるから”」と。
いろんな要因が重なり、1980年代のホンダは抜群に個性的でカッコ良かった。乗っても完成度は低かったが面白かった。シティだけでなく、ワンダーシビックにアコードに初代「CR-X」、どれも露骨に他にはつくり得ない大衆車だったのです。
にっぽんのビートルになると思っていた
なかでもシティはある意味今の「ワゴンR」や「N-BOX」を先取りしたようなトールボーイコンセプトに加え、ユニークすぎるバリエーションまで備えていました。省燃費というよりパンチを効かせたインタークーラー付きターボの「シティ ターボII“ブルドッグ”」に、「マンハッタンルーフ」と呼ばれたハイルーフ仕様。ちなみにブルドッグのボンネットには不思議なパワーバルジが付いており、これは当時の開発者に言わせると「力こぶ」だとか。
なにより小沢が持っていたシティ カブリオレです。当時の大衆コンパクトでは珍しいフルオープンで、ホンダでは1960年代の「S800」以来。ベースはターボIIと同じワイドボディーで、あのフェラーリで知られるイタリアのピニンファリーナが幌(ほろ)の設計を担当。製造担当は後にパジェロ製造となる岐阜の東洋工機。ボディーカラーも12色ととんでもなく豊富で、ある意味今の世知辛い世相だったらあり得ない設定。小沢は勝手に「ホンダ・シティはにっぽんの(フォルクスワーゲン)ビートルになる!」と思っていました。
もちろん乗ってみるとタダでさえ低いボディー剛性がより低く感じられ、ステアリングからのキックバックもまたえも言われぬ激しさ。遅さもハンパなく、さらに節度緩めの3段ホンダマチック(AT)が追い打ちをかけてくる。しかし高速ではそれが妙に楽しかったという……。
とはいえ今では許されない個性であり、事実5年後に登場した2代目ではあっさりとトールボーイコンセプトを半分撤回。全高1.3m台と平凡になり、ターボもカブリオレもつくられぬまま国内では消え去りました。
ある意味、ホンダの勢いと時代の鷹揚(おうよう)さがあったがゆえの希代の名作。寿命の短さがゆえ、逆にそれを懐かしく感じる部分もあるのかもしれませんね。
(文=小沢コージ)
初代ホンダ・シティ(1981年~1986年)解説
1.5リッター級にクラスアップした「シビック」のポジションを埋めるために開発されたコンパクトカー。全高1470mm前後という当時の乗用車としては異例のトールボーイスタイルが人気を集めた。
当初は最高出力67PSの1.2リッター4気筒SOHCエンジンのみだったが、1982年に100PSを発生する「ターボ」を、1983年には110PSを発生する「ターボII」(ブルドッグ)を追加。前後に大型フェンダーを持つワイドボディーの後者には、10秒間だけ過給圧が10%アップする「スクランブルブースト」機能も備わっていた。
1984年にはピニンファリーナが幌の設計を手がけたオープントップモデル「カブリオレ」が登場。少量生産モデルゆえにボディーカラーは全12色がラインナップされていた。
初代ホンダ・シティ 諸元
ターボII
乗車定員:5人
重量:735kg
全長:3420mm
全幅:1625mm
全高:1470mm
ホイールベース:2220mm
エンジン型式:ER
エンジン種類:直列4気筒
排気量:1231cc
最高出力:110PS/5500rpm
最大トルク:16.3kgf·m/3000rpm
サスペンション形式: (前)独立 マクファーソンストラット(後)ストラット
(GAZOO編集部)
懐かしの名車をプレイバック
-

-
俊敏なFFライトウェイトスポーツカー 2代目「ホンダCR-X」を振り返る…懐かしの名車をプレイバック
2024.04.03 特集
-

-
ホンダが生んだ奇跡のオープンスポーツカー「S2000」を振り返る…懐かしの名車をプレイバック
2024.04.02 特集
-

-
その静かさが高級車の概念を変えた! 初代「トヨタ・セルシオ」を振り返る…懐かしの名車をプレイバック
2024.04.01 特集
-

-
人気ナンバーワンの5代目! S13型「日産シルビア」を振り返る…懐かしの名車をプレイバック
2024.03.31 特集
-

-
ただよう欧州車の香り 初代「日産プリメーラ」を振り返る…懐かしの名車をプレイバック
2024.03.30 特集
-

-
そのカッコよさにみんなシビれた! 憧れた! 初代「日産フェアレディZ」を振り返る・・・懐かしの名車をプレイバック
2024.03.29 特集
連載コラム
最新ニュース
-

-
ブレーキキャリパー進化論、ピストン数と性能の関係を徹底解説~カスタムHOW TO~
2024.06.01
-

-
日本モータースポーツの歴史を語って映像で残すプロジェクト「レジェンドレーシングドライバーかく語りき」が5月31日より一般公開を開始
2024.06.01
-

-
スバル『WRX』に「tS」、STIチューンの足回り…米2025年型に設定
2024.06.01
-

-
ランチアがラリー復帰へ、『イプシロン』新型で…212馬力ターボ搭載
2024.06.01
-

-
『グランツーリスモ7』アップデートを配信開始! EG6シビックやGT500のNSXなど追加車種が盛りだくさん
2024.05.31
-

-
BYD、第5世代PHEV発表…エンジン併用で航続2100km
2024.05.31
-

-
「ワイルドなハスラー」登場! スズキ『ハスラー』仕様変更で装備充実、新モデル「タフワイルド」追加
2024.05.31
最新ニュース
-

-
ブレーキキャリパー進化論、ピストン数と性能の関係を徹底解説~カスタムHOW TO~
2024.06.01
-

-
日本モータースポーツの歴史を語って映像で残すプロジェクト「レジェンドレーシングドライバーかく語りき」が5月31日より一般公開を開始
2024.06.01
-

-
スバル『WRX』に「tS」、STIチューンの足回り…米2025年型に設定
2024.06.01
-

-
ランチアがラリー復帰へ、『イプシロン』新型で…212馬力ターボ搭載
2024.06.01
-

-
『グランツーリスモ7』アップデートを配信開始! EG6シビックやGT500のNSXなど追加車種が盛りだくさん
2024.05.31
-

-
BYD、第5世代PHEV発表…エンジン併用で航続2100km
2024.05.31