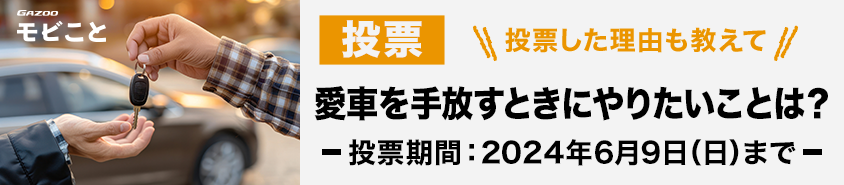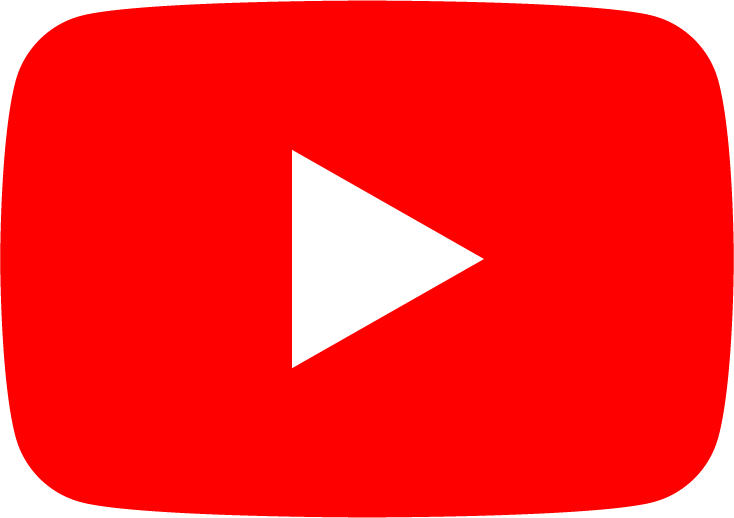カーボンニュートラルの実現へ、TOYOTA GAZOO Racingがスーパー耐久で車を走らせる意義とは?
「僕たちのミッションは、ガソリン車、ハイブリッド車と並べて、カーボンニュートラル車という選択肢をカタログに載せることです」。
こう語ったのは、トヨタ自動車のGR車両開発部で指揮を執る高橋智也部長だ。
2020年10月、日本政府は「2050年カーボンニュートラル宣言」を発表した。それは、2050年までに脱炭素社会を実現し、温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを目標に掲げるものだ。
この宣言の以前から、各自動車メーカーも独自の目標を打ち出し、ヨーロッパの自動車メーカーを中心にBEV(電気自動車)の開発が喫緊の課題となっていった。
そうした中、日本自動車工業会(JAMA)の会長も務めるトヨタ自動車の豊田章男社長は、BEVやFCEV(燃料電池車--水素を使って発電した電気で走る自動車--)の開発を進める傍ら、カーボンニュートラルに向けた選択肢を増やす方策を打ち出した。
その一つが水素を直接燃料とした内燃機関エンジンであり、また別の選択肢がカーボンニュートラル燃料というものだ。
これらの解説は別の記事に任せるが、その新しい機構や燃料の開発について、「スピード感を持ってアジャイルに開発していく」ためにモータースポーツ、しかも市販車ベースの車両が参戦できる最高峰のレースであるスーパー耐久に参戦するという手法が取られることとなった。
かの故 本田宗一郎氏は、「レースは走る実験室」という格言を残した。しかし昨今の自動車の製造は効率化の立場から分業が進み、誤解を恐れずに言えば、それぞれのセクションが与えられたミッションをきっちりとこなすことによって進められている。
そのことによる良い面はもちろんたくさんあるのだが、そのような方法で果たしてカーボンニュートラルについての開発の成果が現実のものとなるのか、筆者はどうしても引っ掛かるものがあった。
そこで、冒頭に紹介した高橋部長に、その開発がどのように進められ、またどのような想いで取り組んでいるのか、少々不躾な取材を申し込んでみたのだ。
まず、車両の開発を進めている「GR車両開発部」とはどのような組織なのかを伺った。
「トヨタ自動車の中だけで、水素エンジンカローラ、カーボンニュートラル燃料のGR86にはそれぞれ数十名が関わっています。エンジンやそのユニットについては、パワートレーンカンパニーが担当していますが、車体側はGR車両開発部が一括して開発を進めています」
「この車体開発のメンバーはすべてGR車両開発部に所属していて、ボディ設計、シャシー設計、電子技術、車両実験担当とか製造技術担当など、さまざまな部署から集まってもらっています。一つの部署の中にこれら様々な担当が集まっているのは、このGR車両開発部だけだと思います」
「我々にとって、スーパー耐久の活動は、レースに勝つためではなく、車を良くするためのものなんです。もちろんレースなので戦うことに意義はあるものの、実は勝ち負けにはこだわっていません。完走して、一つでも多くのデータを取って、それを次の車づくりにフィードバックしていくということが、スーパー耐久でのミッションです」
「つまり、市販車の開発のためにスーパー耐久に参戦しているんです。ですので、次の富士24時間レースでの目標も、完走、そして昨年よりも長く走り、より多くのデータを蓄積することです」
では、具体的にどのような目標を持って、水素エンジンとカーボンニュートラル燃料の開発を進めているのだろうか。
「水素エンジンについては、商品の出口としてはまだ見えていません。ただ、市販化に向けての課題をあぶりだす実証実験を進めるために、きちんと乗車定員を確保した形で水素のタンクを積んだ、水素エンジンの試験車を作り始めています。今年は、サーキットだけでなく、街中や渋滞での走行データもたくさん取っていきます」
「また、気体水素だけでなく、液体水素についても開発を進めています。これは苦労してますけどね……」
カーボンニュートラル燃料についてはどうだろうか。
「カーボンニュートラル燃料も、来年からいきなりすべてのスタンドにカーボンニュートラル燃料があるということにはならないので、実現までには足の長い話ではあります。でも今誰かが始めないとそうなっていかないですよね。未来に向けた挑戦なんです」
「また実現に向けては自動車メーカーが協力し合うことも大切で、各メーカーのエンジンベンチでのデータをエンジニア同士が共有しあったり、横のつながりを強化することについては軌道に乗ってきているのかなと思います」
「また技術開発のため、カーボンニュートラル燃料で走るGR86をスーパー耐久のST-Qクラスで走らせていますが、様々な課題が見えてきているので、もっともっと進化させていかなくてはなりません」
「カーボンニュートラル燃料で公道を普通に走るということであれば、今のGR86の技術でも十分だとは思います。でもGR86はスポーツ走行を楽しむための車でもあり、お客様が安心してサーキットを全開で走れるかという目で見ると、まだまだやるべきことがいっぱいあります」
レースごとの短い期間でのアップデート、車の極限の性能の追及、これまでにない技術の開発、そしてこれを市販車の開発に落とし込むこと、挙げればキリがなく、そんな途方もないミッションを与えられ、メンバーはどのように感じているのだろうか?
「実際大変です(笑)。でもみんな楽しんでやってくれているんですよね。しかも熱いんです! 僕も他の部署を経験してきましたが、このGR車両開発部はすごくモチベーションも高いですし、一体感がすごく強いんです」
「市販車の開発は基本的にセクションごとに分かれていて、各セクションがここまで深く交わることはあまりありません。でもGR車両開発部はいろいろな部署のスペシャリストが集まっていて、自分のセクションの担当業務をこなすことだけではなく、協力していい車を作ること、「共創」にパワーが向いています。みな気心も知れていますし、僕の仕事はそういう楽しく仕事ができる環境を作っていくことだと思っています」
「例えば、このGR車両開発部で経験を積んだメンバーを数年単位で、他の部署とローテーションで回して行くことによって、将来的には会社がより良い方向に変わって行くのではないかと考えています。これもGAZOO Racingカンパニーとしての大切なミッションだと思っています」
高橋部長はインタビュー中、こんなこと言っていいのかなと言いながら、「GR車両開発部が所属するGRカンパニーは小さなカンパニーですので、この開発が失敗してもトヨタが傾くことはないです」と話していた。
ただ、ここまでお読みの方はすでにお分かりのことだと思うが、このGR車両開発部のメンバーは失敗する気などさらさらないのだ。「失敗しない秘訣は、成功するまでやり続けること」という格言があるが、まさにこの挑戦にぴったりなのではないだろうか。
豊田章男社長が語る「失敗してもいい。バッターボックスに立ち続けることが大切」、その精神も見事に浸透していると言っていいだろう。
そして、また高橋部長の言葉をお借りするが、
「逆に、大きなトヨタができない、やらないようなことを、率先してやっていこうぜ」
メンバーはこの思いに一つになり、富士24時間でのより多く周回しての完走、そしてまだ見ぬお客様が選べる選択肢の一つとしてカーボンニュートラル車の実現を目指し、全力全開で走り続けるのだろう。
小さな種が大輪の花を咲かせる、そんな日まで。
(文:GAZOO編集部 山崎 写真:堤晋一)
こちらもおすすめ!S耐記事新着
-

-
青山学院大学の自動車部が、スーパー耐久参戦を目指す活動とマシンを発表!
2024.05.31 モータースポーツ
-

-
楽しく学んで美味しく味わう。S耐富士24時間で水素やカーボンニュートラルがより身近に
2024.05.26 モータースポーツ
-
-
富士24時間 液体水素GRカローラは新たな課題を発見、総合優勝は連覇の1号車 ROOKIE AMG GT3
2024.05.26 モータースポーツ
-
-
富士24時間を夜も楽しむ キャンプだけでない
2024.05.26 モータースポーツ
-

-
マツダがS耐で展開するステップアッププログラムがすごい! ロードスター・パーティレースのチャンピオンが集結
2024.05.26 モータースポーツ
-

-
「楽しくてしょうがない!」。近藤真彦“選手”が水素エンジンのGRカローラで16年振りにスーパー耐久に参戦!
2024.05.25 モータースポーツ
-
-
富士24時間 GRカローラの水素エンジンは更に深化
2024.05.25 モータースポーツ
-

-
立川祐路選手も参戦!タイのクルマ好きとコラボした日本の名門チームがスーパー耐久富士24時間でデビュー
2024.05.25 モータースポーツ
-
-
スーパー耐久24時間富士 開幕前日の入場ゲート 開場待ちのクルマから笑顔が溢れる
2024.05.24 モータースポーツ
連載コラム
最新ニュース
-

-
ブレーキキャリパー進化論、ピストン数と性能の関係を徹底解説~カスタムHOW TO~
2024.06.01
-

-
日本モータースポーツの歴史を語って映像で残すプロジェクト「レジェンドレーシングドライバーかく語りき」が5月31日より一般公開を開始
2024.06.01
-

-
スバル『WRX』に「tS」、STIチューンの足回り…米2025年型に設定
2024.06.01
-

-
ランチアがラリー復帰へ、『イプシロン』新型で…212馬力ターボ搭載
2024.06.01
-

-
『グランツーリスモ7』アップデートを配信開始! EG6シビックやGT500のNSXなど追加車種が盛りだくさん
2024.05.31
-

-
BYD、第5世代PHEV発表…エンジン併用で航続2100km
2024.05.31
-

-
「ワイルドなハスラー」登場! スズキ『ハスラー』仕様変更で装備充実、新モデル「タフワイルド」追加
2024.05.31
最新ニュース
-

-
ブレーキキャリパー進化論、ピストン数と性能の関係を徹底解説~カスタムHOW TO~
2024.06.01
-

-
日本モータースポーツの歴史を語って映像で残すプロジェクト「レジェンドレーシングドライバーかく語りき」が5月31日より一般公開を開始
2024.06.01
-

-
スバル『WRX』に「tS」、STIチューンの足回り…米2025年型に設定
2024.06.01
-

-
ランチアがラリー復帰へ、『イプシロン』新型で…212馬力ターボ搭載
2024.06.01
-

-
BYD、第5世代PHEV発表…エンジン併用で航続2100km
2024.05.31
-

-
『グランツーリスモ7』アップデートを配信開始! EG6シビックやGT500のNSXなど追加車種が盛りだくさん
2024.05.31