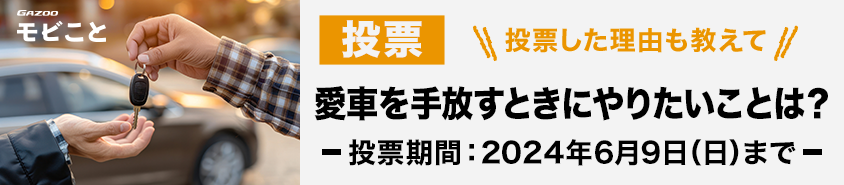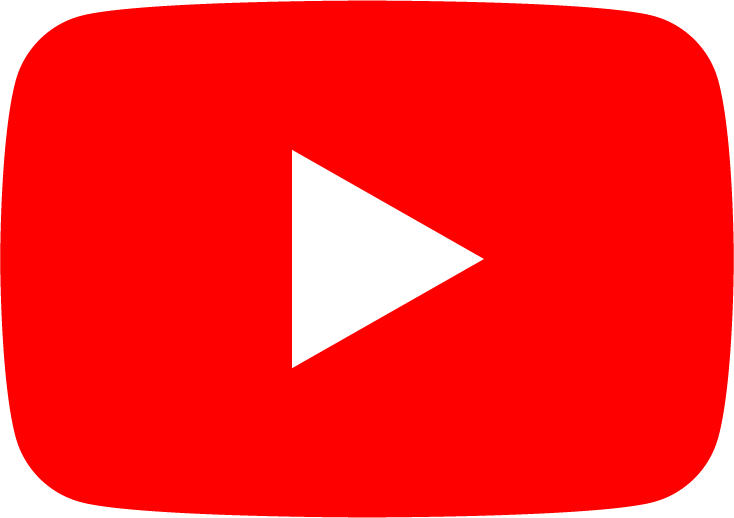WECドライバーが水素エンジンの“音”と“パワー”を堪能! MIRAIへは「充填時間の短さが武器」
-

水素エンジンのGRヤリスと小林可夢偉選手、中嶋一貴選手
2022年のスーパー耐久第5戦が行われたモビリティリゾートもてぎに、TOYOTA GAZOO RacingのFIA世界耐久選手権(WEC)のドライバーが来場し、ロードコースでORC ROOKIE GR Corolla H2 conceptやGRMNヤリスでのタイムアタックバトルで盛り上がったことを先日お届けした。
そのWECのドライバーたちは翌日も引き続きモビリティリゾートもてぎを訪れ、今度は水素エンジンを搭載する試験車両や燃料電池車のMIRAIなど、水素を燃料とする市販モデルを試乗した。
そして、その試乗の感想や、ゼロエミッションが進むヨーロッパでの水素普及の可能などについて語ってくれた。
会場に用意されたのは、燃料電池車両のMIRAI、水素エンジンを搭載するGRヤリスとカローラクロスだ。
このカローラクロスは、スーパー耐久で使用されている水素エンジンを移植し、水素タンクを後部座席下とラゲージルーム下に配置することで後部座席の乗員人数やラゲージスペースも確保している、公道実証実験に向けた試験車両だ。
水素エンジンもガソリンエンジンも、音・パワーともに同じフィーリング
-

WEC に参戦するTOYOTA GAZOO Racing8号車のドライバー
実際に試乗したドライバーたちは、「水素エンジンはガソリンエンジンと音もパワーも変わらない」と、その水素を燃料とする内燃機関エンジンのフィーリングと性能に驚いていた。
平川亮選手は、「走り始めから全く違和感がなく、全開で走った時もガソリンエンジンと伸びやパワー感が変わりませんでした。逆にアクセルを踏み込んだ時のレスポンスがいい時があったりしました」と、その乗り味を教えてくれた。
ブレンドン・ハートレー選手は、自身でも2台のGRヤリスを所有しているそうだが、ガソリンエンジンのGRヤリスと比較しても、どちらに乗っているのか分からなくなるほど、違いが少ないようだ。
そんなハートレー選手は、「内燃機関は人類が100年かけて進化させてきた技術ですので、それを捨ててしまうのはもったいないですし、そう意味でも水素で内燃機関が続いていくことは素晴らしいなと思いました。
MIRAIについては、BEVが充電するのに時間がかかるのに対して、(同じバッテリー駆動でも)燃料電池車であればその問題は解決できるのでいいコンセプトだと思います」とそのメリットについて語った。
水素エンジンがハイブリッドのように認められて欲しい
海外での普及の可能性について、セバスチャン・ブエミ選手は「ヨーロッパではまだ全然知られていないですし、また政治や政策で環境問題を解決する一番の方法がBEVであり最も確立している技術だとして、推し進められています。ただ、トヨタが水素エンジンの技術開発を進めていることは素晴らしいですし、他のメーカーも追従して欲しいと思います」と、その現状と想いを語っている。
またハートレー選手は、「私たちが参戦するWECでも、将来的には水素の導入が検討され始めています。水素の技術が、レースを通じて開発されていくということは、急速に発展させることができると思いますし、そのテクノロジーや魅力を発信し続けていくことで、ハイブリッドの時のように認められるようになっていくのではないかと思います」と続けた。
両選手とも水素ステーションの普及を課題として挙げているが、水素エンジンというテクノロジーには魅力を感じているようだ。
カーボンニュートラルの選択肢が増えていることが素晴らしい
-

WEC に参戦するTOYOTA GAZOO Racing7号車のドライバー
続いてインタビューに応じた7号車をドライブするホセ・マリア・ロペス選手は、水素エンジンのメリットについて、「ゼロエミッションであるということが大きな価値だと思います。運転を楽しみながらちょっと地球に優しいことができているということはうれしいですよね」と語る。
また、マイク・コンウェイ選手は、「水素エンジンはBEVに対して充填時間の短さがメリットなのかなと思います。あと、大気汚染の問題に対して、少し前はあまり選択肢がなかったのが、ここにきてHV、BEVもあるし、さらに水素エンジン、燃料電池などいろいろな選択肢が増えてきて、それをユーザーが選ぶことができるのが素晴らしいことかなと思います」ということをメリットに挙げている。
水素の特性に合わせたエンジンを開発していく
そして、水素エンジン車の仕掛け役と言ってもいい小林可夢偉選手は、現状でも十分なパフォーマンを発揮している水素エンジンに対して、普及のための次なる課題も語ってくれた。
「ガソリン特性のエンジン、ディーゼル特性のエンジンって違うじゃないですか? 今後やらなければいけないこととして水素エンジンの特性を作ることだと思います。単にガソリンエンジンの比較対象としての性能は分かってきましたが、乗りやすいクルマを作るという面で、特性を変えてあげたらもっと可能性は広がるんじゃないかなと思います。そういう開発の段階に入っていると思います。
ディーゼルは低回転、ガソリンエンジンは高回転でメリットがありますが、水素にも一番パワーを出しやすいトルクバンドがあると思いますが、僕は4000回転前後がおいしいレンジだと思っています。その美味しいレンジをできるだけ長くつかうエンジン特性を作ることによって、より水素の可能性を引き出せるんじゃないかなとイメージしています。
燃料に対してエンジンの特性を合わせてあげることが大切ですし、乗りやすくてレンジの広いエンジンが作れるのであれば、今後もっと可能性が広がっていくと思います」
今回、世界のトップドライバーがその魅力を語ってくれた水素エンジン。とはいえ、クルマとして走らせるための技術よりも、法律の改正や整備、そして水素を「つくる」「はこぶ」「ためる」「つかう」という環境整備などまだまだ課題は多い。
その課題は、決してトヨタ一社でクリアできるレベルではなく、まだまだその頂をはっきり見ることができないほど高い壁として立ちはだかっている。
ただ、モータースポーツを起点とすることで、仲間が集い、より素早く技術の開発が進み、そしてより広くその魅力を伝えていくことができることは間違いない。
現在では当たり前の技術となったハイブリッドのように、水素の活用が浸透し、この2020年代初頭のトヨタのチャレンジを懐かしく思う日が来ることは、そう遠い先のことではないのかもしれない。
(文、写真:GAZOO編集部 山崎)
こちらもおすすめ!S耐記事新着
-

-
青山学院大学の自動車部が、スーパー耐久参戦を目指す活動とマシンを発表!
2024.05.31 モータースポーツ
-

-
楽しく学んで美味しく味わう。S耐富士24時間で水素やカーボンニュートラルがより身近に
2024.05.26 モータースポーツ
-
-
富士24時間 液体水素GRカローラは新たな課題を発見、総合優勝は連覇の1号車 ROOKIE AMG GT3
2024.05.26 モータースポーツ
-
-
富士24時間を夜も楽しむ キャンプだけでない
2024.05.26 モータースポーツ
-

-
マツダがS耐で展開するステップアッププログラムがすごい! ロードスター・パーティレースのチャンピオンが集結
2024.05.26 モータースポーツ
-

-
「楽しくてしょうがない!」。近藤真彦“選手”が水素エンジンのGRカローラで16年振りにスーパー耐久に参戦!
2024.05.25 モータースポーツ
-
-
富士24時間 GRカローラの水素エンジンは更に深化
2024.05.25 モータースポーツ
-

-
立川祐路選手も参戦!タイのクルマ好きとコラボした日本の名門チームがスーパー耐久富士24時間でデビュー
2024.05.25 モータースポーツ
-
-
スーパー耐久24時間富士 開幕前日の入場ゲート 開場待ちのクルマから笑顔が溢れる
2024.05.24 モータースポーツ
連載コラム
最新ニュース
-

-
ブレーキキャリパー進化論、ピストン数と性能の関係を徹底解説~カスタムHOW TO~
2024.06.01
-

-
日本モータースポーツの歴史を語って映像で残すプロジェクト「レジェンドレーシングドライバーかく語りき」が5月31日より一般公開を開始
2024.06.01
-

-
スバル『WRX』に「tS」、STIチューンの足回り…米2025年型に設定
2024.06.01
-

-
ランチアがラリー復帰へ、『イプシロン』新型で…212馬力ターボ搭載
2024.06.01
-

-
BYD、第5世代PHEV発表…エンジン併用で航続2100km
2024.05.31
-

-
『グランツーリスモ7』アップデートを配信開始! EG6シビックやGT500のNSXなど追加車種が盛りだくさん
2024.05.31
-

-
「ワイルドなハスラー」登場! スズキ『ハスラー』仕様変更で装備充実、新モデル「タフワイルド」追加
2024.05.31
最新ニュース
-

-
ブレーキキャリパー進化論、ピストン数と性能の関係を徹底解説~カスタムHOW TO~
2024.06.01
-

-
日本モータースポーツの歴史を語って映像で残すプロジェクト「レジェンドレーシングドライバーかく語りき」が5月31日より一般公開を開始
2024.06.01
-

-
スバル『WRX』に「tS」、STIチューンの足回り…米2025年型に設定
2024.06.01
-

-
ランチアがラリー復帰へ、『イプシロン』新型で…212馬力ターボ搭載
2024.06.01
-

-
『グランツーリスモ7』アップデートを配信開始! EG6シビックやGT500のNSXなど追加車種が盛りだくさん
2024.05.31
-

-
BYD、第5世代PHEV発表…エンジン併用で航続2100km
2024.05.31