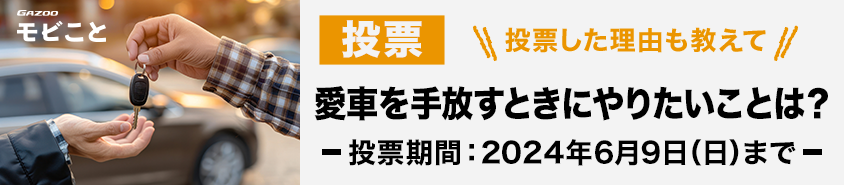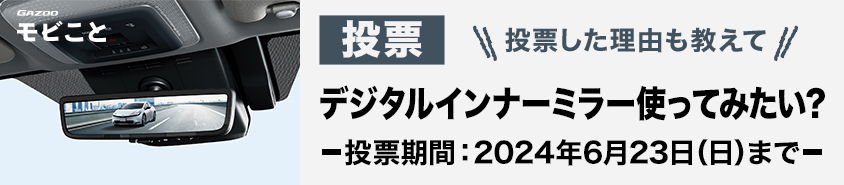【2022スーパー耐久第1戦鈴鹿】水素エンジンの量産化も視野に! 水素エンジンカローラのS耐2年目の挑戦と開発の現在地
3月20日、「ENEOS スーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook」の決勝レースが行われ、スーパー耐久で2年目を迎える水素エンジンを搭載したカローラスポーツも見事に完走をはたしている。
昨年、デビュー戦となった富士スピードウェイでの24時間レースでいきなり完走をはたした、水素エンジンを搭載する32号車ORC ROOKIE Corolla H2 concept。
初戦から11月の最終戦までの約半年で、出力は24%、トルクは33%向上し、エンジン性能をガソリンエンジン並みにまで向上させている。
水素の特性上、エンジン筒内の圧力が低下すると異常燃焼が起きやすくなることに対しても、エンジン筒内を可視化することでどのようなタイミングで発生するかを手の内化し、制御することができるようになってきているという。
こうして、モータースポーツの現場を生かし、早いサイクルでアジャイルに鍛え、課題を解決していく「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」は着実に成果を見せている。
S耐開幕戦鈴鹿での水素エンジンカローラの進化は?
この2022年の開幕戦に向けては、充填スピードを速くすることを目的に充填口と配管を変更し「大流量充填」とすることで、充填時間を前回の2分弱を1分半まで短縮している。
また異常燃焼の制御により、効率的に水素を使うことができるようになり、1回の充填での走行可能距離は20%向上、8周ごとに行っていた水素充填が10周に1回と回数を減らすことができている。
実際に、佐々木雅弘選手の予選のタイムは昨年9月の鈴鹿戦に比べ1秒ほど向上している。さらに周回数は昨年の90周から97周と、こちらも伸ばしてきていることからも、その進化のほどが伺える。
なお、昨年はFCY(フル・コース・イエロー:50km/h制限でコースを走行)、セーフティカーの導入はなかったが、2022年はFCYが3回、セーフティカーが1回導入されている。
水素エンジンの量産化に向け開発が始められている
今後も引き続きモータースポーツの現場での開発は進んでいくが、その先にある量産化に向けてもいろいろと検討が進んでいるようだ。
去年1年である程度のスピードで安全に走れるような開発は進められたが、-30度や50度などさまざまな環境での正常な燃焼や航続距離、燃焼による窒素酸化物(NOx)への対処はガソリンと同様でいいのかなど、より一般での使用環境を想定した開発も進めていくという。
また、水素タンクで後部座席がつぶされているなど、乗員、搭載性なども大きな課題となってくるだろう。
レースで使用される水素の供給については毎回新しい取り組みが行われるが、今回は福島県浪江町の太陽光由来水素に加え、新たに山梨県、東京電力ホールディング、東レが連携して製造する太陽光由来水素の供給を受けている。
また、水素の運搬にもこれまでの金属製タンクから樹脂ライナー製に変更することで、タンク圧力を20Mpsから45MPsに、運搬量も4倍にすることができるようになった。
-

水素エンジンの排気は水蒸気
具体的に、乗用にするのか、商用で活用していくのかなどの出口はまだ決まっていないというが、今シーズンが終わるころには方向性を見せてくれることとなりそうだ。
また、現在はMIRAIでも活用している気体の水素を燃料としているが、液体水素についても開発が進められているという。液体水素では、同じ量で1.7倍の容積が取れるため、さらなる可能性を秘めている。
しかし、水素を液体として貯蔵するためには-253度を維持できるタンクの開発や、充填インフラ、法律の問題もあるため、技術開発と法整備、両面で体制を整えていく必要があるようだ。
今回いろいろな話を聞いて、量産化への道のりにはまだまだ大きな壁が立ちふさがっていることが感じられた。
しかし、カーボンニュートラル社会の実現を目指し、水素を「つかう」「ためる・はこぶ」「つかう」仲間作りは、最初の8社からこの開幕戦で22社まで増え、「点」であった活動が「面」での広がりを見せている。
この流れは引き続き拡大していくだろうし、そこで結集された技術、そして情熱が、この大きな壁を乗り越える原動力となることは間違いないだろう。
(文、写真:ガズー編集部 山崎)
こちらもおすすめ!S耐記事新着
-

-
青山学院大学の自動車部が、スーパー耐久参戦を目指す活動とマシンを発表!
2024.05.31 モータースポーツ
-

-
楽しく学んで美味しく味わう。S耐富士24時間で水素やカーボンニュートラルがより身近に
2024.05.26 モータースポーツ
-
-
富士24時間 液体水素GRカローラは新たな課題を発見、総合優勝は連覇の1号車 ROOKIE AMG GT3
2024.05.26 モータースポーツ
-
-
富士24時間を夜も楽しむ キャンプだけでない
2024.05.26 モータースポーツ
-

-
マツダがS耐で展開するステップアッププログラムがすごい! ロードスター・パーティレースのチャンピオンが集結
2024.05.26 モータースポーツ
-

-
「楽しくてしょうがない!」。近藤真彦“選手”が水素エンジンのGRカローラで16年振りにスーパー耐久に参戦!
2024.05.25 モータースポーツ
-
-
富士24時間 GRカローラの水素エンジンは更に深化
2024.05.25 モータースポーツ
-

-
立川祐路選手も参戦!タイのクルマ好きとコラボした日本の名門チームがスーパー耐久富士24時間でデビュー
2024.05.25 モータースポーツ
-
-
スーパー耐久24時間富士 開幕前日の入場ゲート 開場待ちのクルマから笑顔が溢れる
2024.05.24 モータースポーツ
連載コラム
最新ニュース
-

-
車内でスマホを快適チャージ! 新機軸携帯充電アイテムを【特選カーアクセサリー名鑑】
2024.06.02
-

-
スバル『BRZ』現行モデルが生産終了、新型登場かマイナーチェンジか
2024.06.02
-

-
JAFが「いろいろなモビリティ」サイト公開---混在する交通社会
2024.06.02
-

-
ブレーキキャリパー進化論、ピストン数と性能の関係を徹底解説~カスタムHOW TO~
2024.06.01
-

-
日本モータースポーツの歴史を語って映像で残すプロジェクト「レジェンドレーシングドライバーかく語りき」が5月31日より一般公開を開始
2024.06.01
-

-
スバル『WRX』に「tS」、STIチューンの足回り…米2025年型に設定
2024.06.01
-

-
ランチアがラリー復帰へ、『イプシロン』新型で…212馬力ターボ搭載
2024.06.01
最新ニュース
-

-
車内でスマホを快適チャージ! 新機軸携帯充電アイテムを【特選カーアクセサリー名鑑】
2024.06.02
-

-
スバル『BRZ』現行モデルが生産終了、新型登場かマイナーチェンジか
2024.06.02
-

-
JAFが「いろいろなモビリティ」サイト公開---混在する交通社会
2024.06.02
-

-
ブレーキキャリパー進化論、ピストン数と性能の関係を徹底解説~カスタムHOW TO~
2024.06.01
-

-
日本モータースポーツの歴史を語って映像で残すプロジェクト「レジェンドレーシングドライバーかく語りき」が5月31日より一般公開を開始
2024.06.01
-

-
スバル『WRX』に「tS」、STIチューンの足回り…米2025年型に設定
2024.06.01