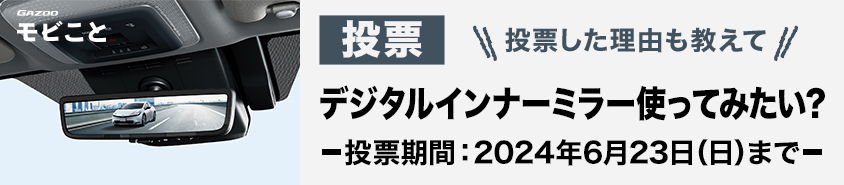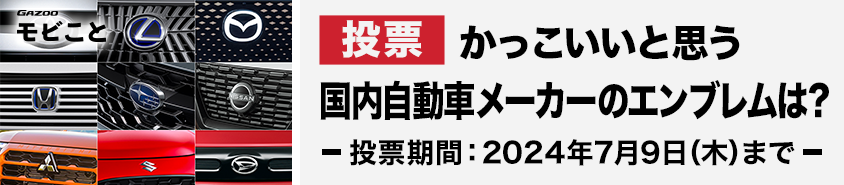スバル レースでSDGsに向けたパーツやアイサイトの開発を行う
レースというのは、厳格なルールの中で各チームが工夫を凝らし競うものである。しかし、スーパー耐久には、スーパー耐久機構が認めたメーカー開発車両、または各クラスに該当しない車両の参加ができる、厳格なルールが存在しないST-Qというクラスがある。2022年よりST-Qクラスに61号車Team SDA Engineering BRZ CNF Conceptで参戦しているスバルは、カーボンニュートラル燃料を利用した車両を持ち込み、車の正常進化にチャレンジしている。
スーパー耐久第5戦にて、スバルのメーカーチームTeam SDA Engineeringの本井雅人監督(スバル研究実験センター長)、航空宇宙カンパニー、千代田製作所がラウンドテーブルを行い、SDGsへの取り組みや、アイサイトをレースに導入する取り組みについて語った。
航空用パーツの再利用でSDGs
航空用のパーツは、品質を高い基準で維持する必要があるそうだ。そのため、航空機材としては利用できなくなっても、自動車用であれば素材として再利用できるものもある。
スバルでは、航空部品として利用され、品質保証期限を過ぎて破棄されるカーボンを、自動車用に再生する取り組みを行っている。2021年初旬より開始し、同年に製造プロセスを確立した。7月のスーパー耐久では、BRZのエンジンフードをオールカーボン化したが、再生カーボンを利用した。強度アップのため、再生カーボンではないカーボンを1枚利用しているが、残りは再生カーボンだ。効果は、2kgの重量低減、再生カーボンを生成するエネルギーを従来カーボンの約10%にできたそうだ。
しかし、このパーツはレース車両へのワンオフでの試作品であり、市販車などに展開するには幾つかの技術的な課題を解決していく必要があるそうだ。例えば、更なる強度アップや軽量化、そして表面の仕上げなどである。また、炭素繊維に樹脂を含ませる含侵性の向上も必要ということだ。
まだ量産は視野に入っていないということだが、スバル、スバル 航空宇宙カンパニー、千代田製作所の3社が協力して、研究開発を進めていくということだ。コスト低減については、スーパー耐久のレギュレーションであるエロアパーツ部品を40万円以下にすることを目標にしたいと語った。
市販車と同じアイサイトをレース車両に設置
アイサイトとは、車両に設置したステレオカメラを利用した、安全のための運転支援システムだ。今回、スーパー耐久参戦のBRZに搭載した映像を見せてもらえた。BRZより遥かに速いスピードの車、かなり遅い車が混走するが、ストレートでは他の車をしっかり認識できていた、一方コーナでは認識できないエリアも存在していた。
今回はデータ取得が目的であり、フラッグを認識できるようにする、FCYでの利用など、モータースポーツでどんな利用ができるかを今後検討していくそうだ。また、スバルの山内英輝選手がTwitterに、「S耐車両のBRZに、SCカー中やFCY中にアイサイト使えてたら、すごく良いのにな。ピットロードは自動運転システムで自分のピット前に止めれたらカッコいいのに。」とつぶやいている。
中島飛行機という会社をルーツにもち、自動車事業だけでなく日本の航空宇宙産業を担っているスバルらしい取り組みだと感じた。
(GAZOO編集部)
スーパー耐久(S耐) 新着記事一覧
-

-
「クルマ好きを笑顔に」。スーパー耐久で自動車メーカーがタッグを組む『共挑』の価値と可能性
2024.06.05 モータースポーツ
-

-
青山学院大学の自動車部が、スーパー耐久参戦を目指す活動とマシンを発表!
2024.05.31 モータースポーツ
-

-
楽しく学んで美味しく味わう。S耐富士24時間で水素やカーボンニュートラルがより身近に
2024.05.26 モータースポーツ
-
-
富士24時間 液体水素GRカローラは新たな課題を発見、総合優勝は連覇の1号車 ROOKIE AMG GT3
2024.05.26 モータースポーツ
-
-
富士24時間を夜も楽しむ キャンプだけでない
2024.05.26 モータースポーツ
-

-
マツダがS耐で展開するステップアッププログラムがすごい! ロードスター・パーティレースのチャンピオンが集結
2024.05.26 モータースポーツ
-

-
「楽しくてしょうがない!」。近藤真彦“選手”が水素エンジンのGRカローラで16年振りにスーパー耐久に参戦!
2024.05.25 モータースポーツ
-
-
富士24時間 GRカローラの水素エンジンは更に深化
2024.05.25 モータースポーツ
-

-
立川祐路選手も参戦!タイのクルマ好きとコラボした日本の名門チームがスーパー耐久富士24時間でデビュー
2024.05.25 モータースポーツ
連載コラム
最新ニュース
-

-
アウディのEVスポーツ『e-tron GT』、改良新型は表情変化…航続は609kmに拡大
2024.06.18
-

-
オイル添加剤で燃費向上? メリットとリスクを徹底検証~カスタムHOW TO~
2024.06.18
-

-
フィアット『パンダ』がファミリー拡大、『グランデパンダ』発表…新型コンパクトSUV
2024.06.18
-

-
トヨタ ランドクルーザー300 Tシャツ新発売
2024.06.17
-

-
レクサス『GX』新型、移動キッチンカーに…リアは観音開きに変更
2024.06.17
-

-
VW ゴルフ のセダン版、『ジェッタ』に改良新型…6月中に米国発表へ
2024.06.17
-

-
アバルトがガソリン車の日本向け生産終了---『F595』と『695』
2024.06.17