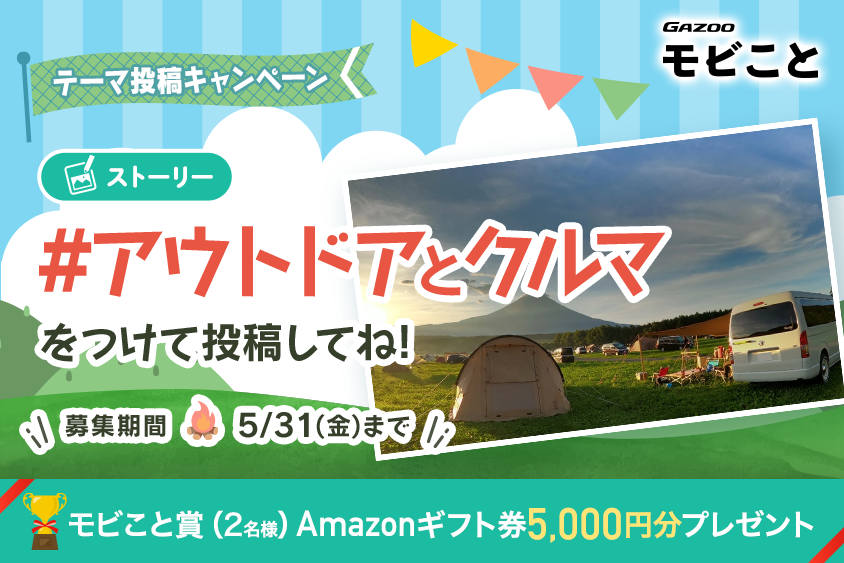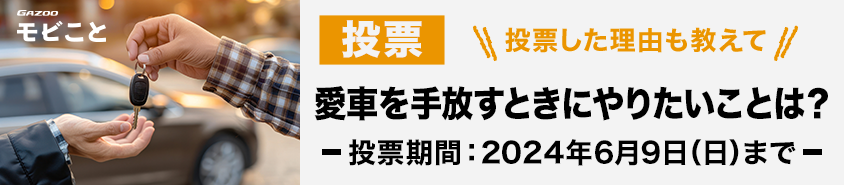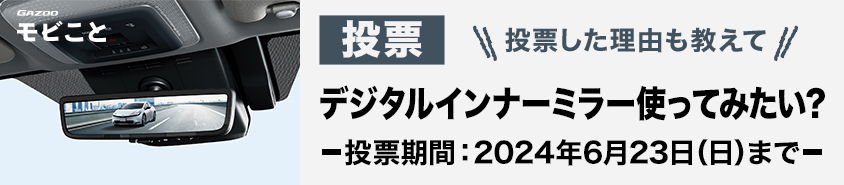NSX(NA1)をベースに、小学生の時から憧れたスーパーカーを自ら作り上げる
クルマは単なる移動手段としてだけでなく、夢や憧れの対象ともなりうる。その好例が1970年代に巻き起こったスーパーカーブームだろう。当時の小・中学生たちは、スーパーカーカード、スーパーカー消しゴムを集め、『いつかは自分もオーナーになりたい』と思っていた。そんなスーパーカーブーム真っ只中を過ごしたひとりが、この1993年式ホンダ・NSX(NA1)のオーナーである“たいちゃんやまちゃん"さんだ。
NSXとの出会い
ホンダ・NSX(NA1)といえば、ホンダのフラッグシップモデル。F1を戦った技術を投入して作り上げたミッドシップエンジン、リアドライブのクルマ。当時は世界でも類を見なかったアルミモノコックボディを採用し、エンジンを含め、手作業で組み上げられた『和製スーパーカー』だ。
とはいっても、このクルマのリアスタイルからはベースがNSXであることは想像できない。公認車検を取得し、世界で1台のスーパーカーに仕上がっている。
“たいちゃんやまちゃん”さんがNSXをベースにオリジナルの1台を作り上げようと考えたのは20年ほど前。40才の頃に「人生は1度きりだから、乗りたいクルマに乗ろう」と考え、スーパーカーブーム時に憧れたランボルギーニ・カウンタックを手に入れることを決意したのがはじまりだったという。
当時はまだ手が届きそうな価格帯だったため、地道に貯金を重ねていった。試乗するチャンスに恵まれ、いざカウンタックの運転席に座ってみると、190cm近くある長身では乗り降りもままならなかったのだ。
そしてちょうどその頃、仕事で腕の腱を痛めてしまい手術をすることになる。カウンタックを諦めた直後だった上に、MT車に乗ることも難しくなってしまったことから、しばらくは病室で落ち込んでいたという。
しかし「ATのNSXなら乗れるかも」と気持ちを切り替え、家族にも内緒で契約書にサイン。手術は無事に成功し、子供の頃の憧れとは違うものの“スーパーカー”を手に入れたことで、生活にも張り合いが生まれた。
そんなNSXも購入当初は市販のエアロパーツを組んでカスタマイズを楽しんでいたものの、次第にNSXオーナーの友人が増えていく中で『パーツにこだわったところで、同じパーツをつけているNSXがいれば、それは自分だけの一台とは言えない。それなら自分だけの1台を作り上げてしまおう!!』と決意。イメージは子供の頃から描き続けていた理想のスタイリングだ。
当時のスケッチを拝見すると、万年筆で描いた独特のタッチは、単なるクルマ好きの子供が描くイラストレベルではない。というのも、中学生時代には絵画コンクールで受賞経験もあるという美術センスの持ち主。アーティスティックなクルマを思い描く下地はこの時代から育まれていたというわけだ。
しかし、この思いを実現するために何軒もボディショップを回って相談したものの、引き受けてくれるお店はなかなか見つからず、1台丸ごとではなくセクションごとに分けてパーツ製作をお願いする作戦に変更。それでもまったく未知の作業というだけに『失敗しても料金は払うから』と鈑金屋さんに納得してもらい、なんとか製作をスタートさせることができたそうだ。
NSXを唯一のスーパーカーにカスタマイズ
しかし、作業が進むにつれてお願いしたお店同士が連絡を取るようになり、気がつけば製作プロジェクトのような形態に進化。そんな紆余曲折とまわりの協力の甲斐あって、パネル同士のチリも完璧に合い、イメージ通りのフォルムを作り上げることに成功したというわけだ。
ちなみにエアロパーツをワンオフ製作する場合、事故などに合うと同じものが作れないこともある。しかし、このNSXのために新規製作したボディパネルは、すべて市販エアロパーツと遜色のないクオリティで型から製作しているため、高精度のボディパネルを量産することも可能だという。この辺りもオーナーのこだわりポイントといえるだろう。
改めてエクステリアを拝見していくと、ノーマルの面影を残さないリアセクションは、流れるようなラインを作るためにオーバーハングを30ミリ延長。フレームを新規延長して強度を保つ工夫も施されている。
そして、それに合わせて作られた大型リアフードの開閉なども、ノーマルと同様の使い勝手とはいかない。
開閉機構として様々なシステムを検討した結果、家庭用介護ベッドの動きに注目。起き上がりなどの動作をそのまま取り入れることで、重量のあるフード開閉を電動で動かせると考えて即購入し、分解しながらフレームの取り付けを検討しつつ、モーターを流用することで最大90度までのチルトアップ機構を完成させているという。
ちなみに稼働させるには100V電源が必要になるため、シートバックにインバーターをセットして電源を取っているそうだ。
リアホイールは車体に合わせて採寸した20インチのオーダー品をセット。組み合わせるタイヤサイズは325/25R20と、まさにスーパーカーの貫禄を備えている。
なお、純正フューエルリッドは使用できなくなっており、リアフードを開けた部分に新設されるのだが、パイプの曲がり角がきついため給油は少量ずつ時間をかけて行わなければならないのは想定外の苦労ポイントだったとか。
「ガルウイングドアは実績のある秋田県のショップに依頼してフレームから設計してもらいました。型を作って軟鉄を流し込むところから製作しているので、上げたままでビクともしないガッチリとしたドアに仕上がっていますよ」
カウンタックを手に入れられなかったオーナーにとって、スーパーカーブームの頃にあこがれた『カウンタック・リバース(上半身を乗り出してバックするテクニック)』を安心してできるというのも、満足度を高めてくれるポイントなのだ。
いっぽうフロントセクションや内装を見ると、リア周りのような大掛かりなカスタマイズは施されていない。リアスタイル同様にフロントやルーフ、インテリアまでオリジナルカーのイメージは出来上がっているものの、妥協のない作り込みのために準備を進めている状況だという。
将来的には理想のデザインへと仕上げていきたいと考えているそうなので、どのように変化するのか興味深いところだ。
大事なのは良き理解者
思い返してみれば、幼少期のスーパーカーブームだけでなく、小・中学校の頃はイラストで理想のクルマを描いていたことも、このNSXにつながる歴史のひとつ。さらに、イラストによってイメージを膨らませつつ、NSXのイメージを固めるためにクレーモデルまで製作したというから驚きだ。
ちなみに本業は水沢市でカフェレストランを経営していて、この技術を生かしたクルマ型の立体ケーキ作りなども行なっているのだとか。
お店の名前は『つどいの食卓 カウンタック』。幼い頃の憧れをそのまま店名として使用し「イタリアのランボルギーニ社の許諾も受けている」とのことで、料理の味はもちろんのこと、NSXが看板代わりとなって全国からスーパーカーオーナーも訪れる観光名所となっている。
また、地元のカーショーに参加した際にはカウンタックの製作者のひとりであるアリーゴ・ガリッツィオ氏から表彰されたこともあるそうで、サーキットの狼の著者で知られる池沢さとし氏や、世界的な工業デザイナーのケン・オクヤマ氏など、著名人からも評価を受けているというからすごい!
家族に内緒でNSXを契約したときには奥さんが泣いてしまったという事実を娘さんからあとで聞かされたというが、現在では良き理解者として助手席で一緒にドライブも楽しんでいるという。これだけのプロジェクトを進めるためには、家族や周囲の理解や協力を得ることは必要不可欠なのだ。
また、奥さんのお兄さんが岩手県の自動車整備振興会会長ということもあり、カスタマイズの合法性に関して逐一アドバイスをもらっているとのこと。ここまで大幅なモデアファイながらもフル公認を取得しているというのも、このNSXの見どころのひとつといえるだろう。
家族に支えられつつ夢のクルマを作り続けている“たいちゃんやまちゃん”さん。デザインはもちろんのこと、細部までしっかりとプランを練りながら、仕事やフトコロ事情などにも考慮して進めているため、理想の1台が完成するのはまだしばらく先になりそう。もしかしたら子供や孫の代まで続くプロジェクトとなる可能性も!?
とはいえ、このNSXはすでに、オーナーの夢を乗せた『世界に1台の宝物』であることに違いない。
取材協力:盛岡競馬場(OROパーク)
(文:渡辺大輔 / 撮影:金子信敏)
[GAZOO編集部]
スーパーカーは最高!
連載コラム
最新ニュース
-

-
ランチア『イプシロン』新型、3グレードで欧州再進出…EVとハイブリッドから選択可能
2024.05.30
-

-
アキュラ『MDX』に「タイプS」、新フェイスに355馬力ターボ搭載…2025年型を米国発売
2024.05.30
-

-
節約&安全を両立! タイヤ・ローテーションと空気圧管理の重要性とは?~Weeklyメンテナンス~
2024.05.30
-

-
アウディ『Q6 e-tron』、後輪駆動を欧州で追加…航続はシリーズ最長の641km
2024.05.30
-

-
アイルトン・セナに敬意、マクラーレン『セナ』の8分の1スケールモデル開発中…日本円で320万円
2024.05.30
-

-
BMW M3 セダン、「コンペティション」は530馬力に強化
2024.05.30
-

-
アキュラの最上位SUV『MDX』、表情変化
2024.05.30
最新ニュース
-

-
ランチア『イプシロン』新型、3グレードで欧州再進出…EVとハイブリッドから選択可能
2024.05.30
-

-
アキュラ『MDX』に「タイプS」、新フェイスに355馬力ターボ搭載…2025年型を米国発売
2024.05.30
-

-
節約&安全を両立! タイヤ・ローテーションと空気圧管理の重要性とは?~Weeklyメンテナンス~
2024.05.30
-

-
アウディ『Q6 e-tron』、後輪駆動を欧州で追加…航続はシリーズ最長の641km
2024.05.30
-

-
アイルトン・セナに敬意、マクラーレン『セナ』の8分の1スケールモデル開発中…日本円で320万円
2024.05.30
-

-
アキュラの最上位SUV『MDX』、表情変化
2024.05.30