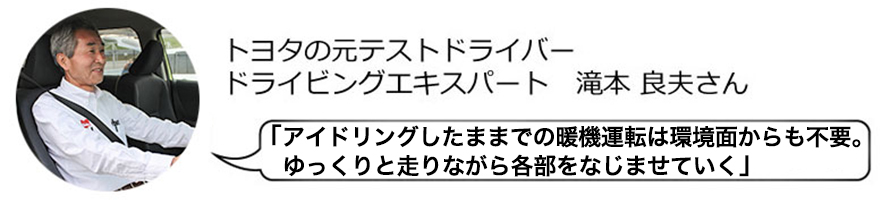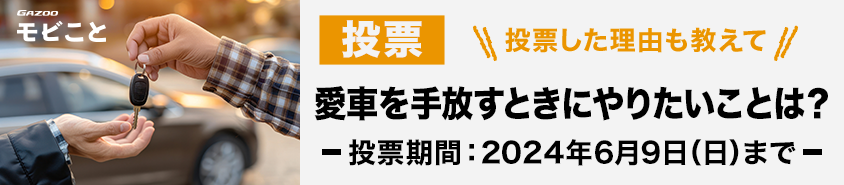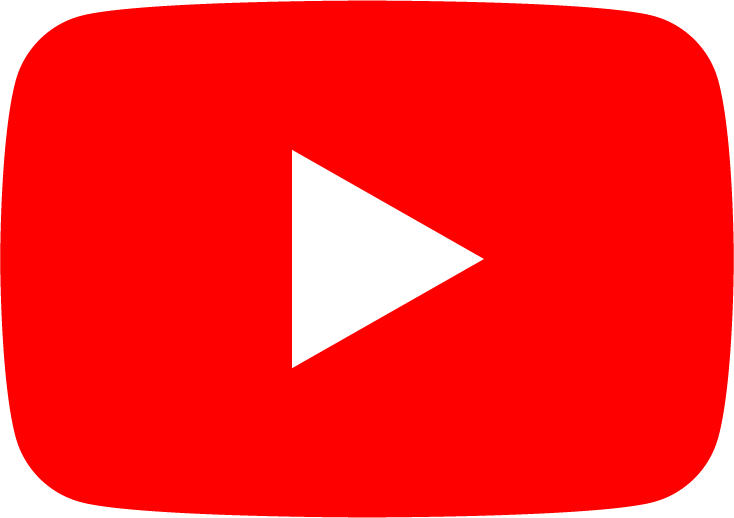クルマに乗る前の暖機、どうしている?(クルマの運転操作、みんなはどうしている?)
内燃機関が稼働する際、温度は重要なファクターです。低すぎると所定の性能を発揮できないばかりか、内部にダメージを与えてしまうこともあります。そのため必要となるのが「暖機」ですが、アイドリングのまま暖機を行うことは現在では奨励されておりません。
「水温計の針が動きだすまで待って発進する」
「エンジン始動後、すぐに発車する」
という方もいらっしゃるのでは。
みなさんは、どうしていますか?
昔なら当然のようにやっていたことでも、環境などの変化により現在では真逆の扱いになっている行為は多く存在します。
自動車の世界では「暖機運転」がそれに該当する行為かもしれません。かつては、水温計の針が動きだすまで5~10分くらいアイドリングのまま待つということが当たり前のように行われていたこともありました。エンジンがしっかり暖まるまで待って走り出す、それが寿命を延ばすことにもつながるので「愛車を大事にしている」アピールだった時代もありました。寒冷地では、しっかりとヒーターが効くまで待つことも日常でした。
しかし現在では、条例により長時間のアイドリングを禁じている自治体も増えてきているように、停止したままでの暖機は奨励されていないどころかオーナーズマニュアルにも「停車しての暖機は基本的に不要です」と明記している自動車メーカーもあります。
もちろん暖機にもメリットがあって、エンジンオイルが全体に行きわたり金属が熱膨張し最適なクリアランスになることにより内燃機関がもっとも効率よく稼働できる状態にしてから走り出すことはエンジンへのダメージも少ないですし燃費面でも好条件になります。
しかし、そこでいくら燃費が向上してもアイドリング時に消費した燃料を勘案するとトータルの燃費としては相殺になることだってあるでしょう。むしろ不要な排出ガスを出したぶん環境にとってはやさしくないことになります。
私は、みなさんがやっているのと同様に、走りながら各部をなじませる「暖機走行」を励行しています。燃料噴射量や水路などを高度にシミュレーションされている最近のエンジンは、走りながらの暖機でも大丈夫に作られています。やり方は、特別なことは何もしません。交通の流れを邪魔しない範囲で低めに回転数を保ちながらおとなしく運転するだけです。エンジン(水温)を暖めるのはもちろんですが、ミッションオイルやダンパーなど動かさなければ暖機にならないパーツについても、なじませることができます。待ち時間もなく目的地にも早く着けるので、その面でも効率的かと思っています。
ただし例外もあります。マイナス10℃を下回るような厳寒の地域での朝一番の始動時などは、オイルの循環が悪くなることがあります。また、長期間クルマに乗らなかったときなども、エンジン内のオイルが下がっており摺動する金属どうしが密着している状態にあります。このような場合はエンジンを始動してすぐに走り出すとエンジン内にダメージがおよぶ可能性があるので、わずかな時間だけでもアイドリングしたほうがいいともいわれています。
ライター:畑澤 清志
【監修・解説者】
ドライビングエキスパート(トヨタの元テストドライバー)
滝本 良夫(たきもと・よしお)
約40年にわたりトヨタの運転技術指導員として活躍しながら、車両実験部でハイエース、ダイナ、コースターなどの商用車系開発の実験および商品監査に携わる。2014年に定年退社。
[ガズー編集部]
連載コラム
最新ニュース
-

-
車内でスマホを快適チャージ! 新機軸携帯充電アイテムを【特選カーアクセサリー名鑑】
2024.06.02
-

-
スバル『BRZ』現行モデルが生産終了、新型登場かマイナーチェンジか
2024.06.02
-

-
JAFが「いろいろなモビリティ」サイト公開---混在する交通社会
2024.06.02
-

-
ブレーキキャリパー進化論、ピストン数と性能の関係を徹底解説~カスタムHOW TO~
2024.06.01
-

-
日本モータースポーツの歴史を語って映像で残すプロジェクト「レジェンドレーシングドライバーかく語りき」が5月31日より一般公開を開始
2024.06.01
-

-
スバル『WRX』に「tS」、STIチューンの足回り…米2025年型に設定
2024.06.01
-

-
ランチアがラリー復帰へ、『イプシロン』新型で…212馬力ターボ搭載
2024.06.01
最新ニュース
-

-
車内でスマホを快適チャージ! 新機軸携帯充電アイテムを【特選カーアクセサリー名鑑】
2024.06.02
-

-
スバル『BRZ』現行モデルが生産終了、新型登場かマイナーチェンジか
2024.06.02
-

-
JAFが「いろいろなモビリティ」サイト公開---混在する交通社会
2024.06.02
-

-
ブレーキキャリパー進化論、ピストン数と性能の関係を徹底解説~カスタムHOW TO~
2024.06.01
-

-
日本モータースポーツの歴史を語って映像で残すプロジェクト「レジェンドレーシングドライバーかく語りき」が5月31日より一般公開を開始
2024.06.01
-

-
スバル『WRX』に「tS」、STIチューンの足回り…米2025年型に設定
2024.06.01