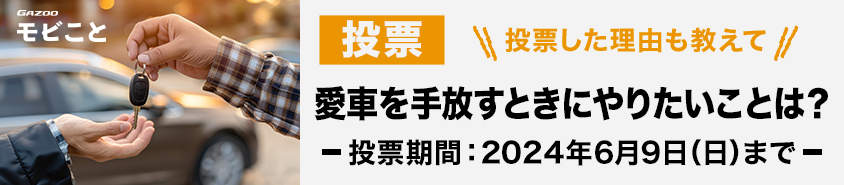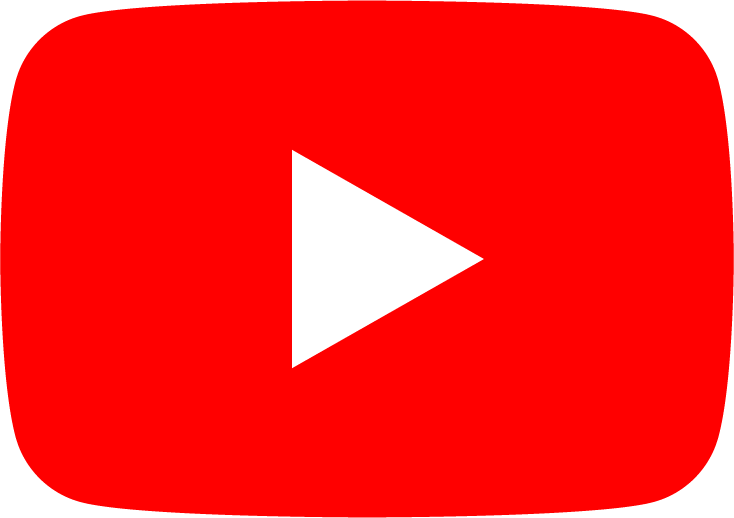知っているとクルマ通!? 「昔の装備」を9問のクイズで覚えよう!
新しい素材や技法の導入、コンピュータの性能向上、デバイスの小型化や機能の統合など、クルマは常に最新のテクノロジーが注がれ、設計・生産が行われています。
50年前に生産されたクルマと現在のクルマは、基本的な機能や操作こそ同じものの、内容は別物のように違うもの。クルマの装備品や機能を操作するインターフェイスも同様です。ほかの装備品との統合やコンピュータ制御となって姿を消す、あるいはがらりと姿を変えています。
今回は神奈川トヨタ自動車の協力のもと、昔のクルマにはあって当たり前、けれど現在、見かけなくなった装備品やインターフェイスをクイズ形式で紹介。初級から上級まで3問ずつ、計9問を用意したので、ぜひ挑戦してみてください!
まずは初級編!(3問)
●第1問:トヨペット・クラウン(初代)に備わる、これは何でしょうか?
1:ヒートシンク
2:整流板
3:サイドミラー
答えは・・・
3:サイドミラー
-

ボンネットの両端、ちょうど前輪の上あたりに装着されている
作業用車両など一部の車両をのぞけば、現在のクルマのサイドミラーは、ドアの上部にそなわる「ドアミラー」が主流です。しかし、1983年3月より以前は、法令によりサイドミラーはフェンダーに設置するよう定められていました。その設置位置から「フェンダーミラー」と呼ばれ、ドアミラーと区別されます。
フェンダーミラーはドアミラーよりも広い視界をカバーし、また確認時に視線の移動も少なくてすむため、今でもタクシーなどで活用されています。
-

画像はカローラレビン(初代)。1970年代には、画像のような「砲弾型」のフェンダーミラーが流行した
●第2問:カローラレビン(初代)のインストルメントパネル(以下、インパネ)に設置された、画像のマークは何でしょうか?
1:シガーライター
2:換気スイッチ
3:タバコ入れ
○答えは・・・
1:シガーライター
「シガーライター」はタバコへの着火を目的とした、電熱式の着火装置です。強く押し込むことで電熱線が加熱され、着火準備が整うと、最初の位置まで押し戻されます。シガーライターを抜いた受け口側は、「シガーソケット」と呼びます。
現在のクルマにもシガーソケットは「アクセサリーソケット」などの名称で装備されていますが、喫煙者が減ったこともあり、シガーライターはオプションとなるのが一般的になりました。
●第3問:トヨペット・コロナマークⅡ(2代目)にそなわる、このハンドルの名称は?
1:ウインドウレギュレーターハンドル
2:ドアノブ
3:ドアロック
○答えは・・・
1:ウインドウレギュレーターハンドル
サイドウインドウを開閉するハンドルのこと。日本でのパワーウィンドウの本格的な普及は1980年に入ってからで、それまで多くのクルマはこのウインドウレギュレーターハンドルをクルクルと回し、サイドウインドウの上げ下ろしを行っていました。
今、サイドウインドウの開閉操作を手動で行うのは、軽トラックの廉価グレードや少しでも軽さを求める一部のスポーツカーなどのみ。一般的な乗用車では、ほぼ見られなくなっています。
中級編(3問)
●第4問:トヨペット・クラウン(初代)にそなわる、この装備は何のためにあるでしょうか?
1:緊急時にウィンドウを破壊するため
2:開閉し、車内の換気をするため
3:取り外して車内の換気をするため
○答えは・・・
2:開閉し、車内の換気をするため
-

このように回転するように開閉する
形状から、その名が付けられた「三角窓」。サイドウインドウのようにドア内に収納されるのではなく、二辺の中央に設けられたヒンジで開け閉めを行います。開閉角度を調整することで、効率よく運転席や助手席に風を取り入れることができ、エアコンやクーラーのない(あるいは冷房の弱い)クルマで暑い夏の移動を行うのに、欠かせない装備でした。
●第5問:カローラレビン(初代)のダッシュボード下部に設置された、この装備品の名称は?
1:チョークノブ
2:スロットルノブ
3:クルーズコントロールスイッチ
○答えは・・・
1:チョークノブ
冷えている状態のエンジンを始動するとき、ガソリンと空気の供給量を調整し、エンジンをかかりやすくするためにあるのが、このチョークノブ。キャブレターという機械式の燃料噴射装置が使われていた時代の装備です。
四角にスラッシュの入ったマークは、キャブレターにもうけられた「チョーク弁」を図案化したものです。
-

初代クラウンの頃はチョークノブにチョーク弁のマークはなく、「CHOKE(チョーク)」の頭文字である「C」が記載されていた
現代のクルマは、燃料噴射を電子制御の「インジェクション(燃料噴射装置)」で行うため、チョークノブは不要となっています。
●第6問:トヨペット・コロナマークⅡ(2代目)のダッシュボード下部に設置された、2本のレバーの役割は?
1:ヘッドライトの光軸調整
2:サイドミラーの折りたたみ
3:サイドミラーのミラー角度を調整
○答えは・・・
3:サイドミラーのミラー角度を調整
今のクルマのドアミラーは、モーターでミラー角度の調整を行うことが多いですが、コロナマークⅡのフェンダーミラーはワイヤーで行うアナログ式。ダッシュボード右側にあるレバーから左右のフェンダーミラーまで、直接ワイヤーがつながっていて、レバー操作によりワイヤーを引っ張って角度調整を行いました。
余談ですが(電動式を含めて)運転席からミラーの角度を調整できる装備が普及する前は、ガソリンスタンドでスタッフによるミラーの角度調整サービスがありました。
さあいよいよ上級編です!(3問)
●第7問:トヨペット・クラウン(初代)に収納されている、曲がった鉄の棒は何のためのもの?
1:エンジンを始動するため
2:ジャッキアップを行うため
3:前輪の舵角を調整するため
○答えは・・・
1:エンジンを始動するため
-

フロントにある穴に差し込んで使う
画像の鉄の棒は「クランク棒(スターティング・ハンドル)」と呼びます。バッテリーやセルモーターの不調でエンジンが始動できないとき、クルマの外からクランク棒をエンジンのクランクシャフトにつなぎ、クランク棒を手で回してエンジンを始動していました。
-

トヨペット・クラウン(初代)の場合、ナンバーの上にクランク棒を挿入するための穴が設けられている
クランク棒による始動が必要とされたのは、バッテリーやセルモーターの性能や信頼性が低かった時代。クラウンも2代目の時点ですでに廃止されていましたから、見たことのない人がほとんどでしょう。ちなみに、1948年から1990年まで生産されたシトロエン「2CV」には、セルモーターがついたあとも生産終了までクランク棒による始動のための穴が設けられていました。
●第8問:トヨペット・クラウン(初代)に備わる、このオレンジのパーツの目的は何でしょうか?
1:警告灯
2:方向指示器
3:車幅灯
○答えは・・・
2:方向指示器
-

初代クラウンではBピラーに装着されていた
メーカーにより名前はさまざまですが、初代クラウンではこの方向指示器を「腕木式方向指示器(うでぎしきほうこうしじき)」と呼んでいました。左右のBピラーに内蔵され、ハンドル右側のレバー(今のウィンカーレバーと同じ位置)で操作します。
操作方法もウィンカーレバーと同様ですが、自動解除機能は備わっていません。交差点を曲がり終わったら手動でレバーを戻し、腕木式方向指示器を収納します。
-

使用されていないときの腕木式方向指示器は、きれいにBピラーに内蔵されている
展開時は電球により点灯しますが、今のウィンカーのように明滅する機能はありません。腕木式方向指示器の登場後、ほどなくして現代と同じタイプのウィンカーが登場。視認性にすぐれるウィンカーに、その役割を譲ります。
●第9問:トヨペット・クラウン(初代)の運転席フロアに備わるスイッチは何のためのもの?
1:サイドブレーキ
2:パーキングセレクタースイッチ
3:ヘッドライトのハイ/ロー切り替えスイッチ
○答えは・・・
3:ヘッドライトのハイ/ロー切り替えスイッチ
今のクルマのライトに関わるスイッチは、ハンドル右側のレバー(もしくはインパネのダイヤル)に集約されています。しかし、初代クラウンのハンドル右側には方向指示器のレバーしかありません。搭載するヘッドライトや車幅灯、フォグランプのスイッチはダッシュボードに装着され、ハイビームとロービームの切り替えは足下のスイッチで切り替えていたのです。
今はあって当たり前の装備も、20年後にはなくなっているかも
以上でクイズは終了です。皆さん、何問正解できましたか?
今は当たり前に使用している装備も10年後、20年後には消える、あるいは姿を変えているかもしれません。事実、ここ数年でモニターカメラが普及し、ミラーレス車が登場しました。クルマからミラーが消えるなんて、かつては誰も予想していなかったことでしょう。ひょっとしたら今後、サイドミラーやルームミラーがすべてのクルマから姿を消す……なんてこともあるかもしれません。
20年後に行われる「この装備品はなに?」クイズには、どのような装備品がピックアップされるのか、楽しみですね。
<関連リンク>
トヨタモビリティ神奈川 (神奈川トヨタ自動車株式会社)
(文・撮影:糸井賢一/協力・神奈川トヨタ自動車/編集:木谷宗義type-e+ノオト)
[GAZOO編集部]
あわせて読みたい!
コラムトップ
連載コラム
最新ニュース
-

-
車内でスマホを快適チャージ! 新機軸携帯充電アイテムを【特選カーアクセサリー名鑑】
2024.06.02
-

-
スバル『BRZ』現行モデルが生産終了、新型登場かマイナーチェンジか
2024.06.02
-

-
JAFが「いろいろなモビリティ」サイト公開---混在する交通社会
2024.06.02
-

-
ブレーキキャリパー進化論、ピストン数と性能の関係を徹底解説~カスタムHOW TO~
2024.06.01
-

-
日本モータースポーツの歴史を語って映像で残すプロジェクト「レジェンドレーシングドライバーかく語りき」が5月31日より一般公開を開始
2024.06.01
-

-
スバル『WRX』に「tS」、STIチューンの足回り…米2025年型に設定
2024.06.01
-

-
ランチアがラリー復帰へ、『イプシロン』新型で…212馬力ターボ搭載
2024.06.01
最新ニュース
-

-
車内でスマホを快適チャージ! 新機軸携帯充電アイテムを【特選カーアクセサリー名鑑】
2024.06.02
-

-
スバル『BRZ』現行モデルが生産終了、新型登場かマイナーチェンジか
2024.06.02
-

-
JAFが「いろいろなモビリティ」サイト公開---混在する交通社会
2024.06.02
-

-
ブレーキキャリパー進化論、ピストン数と性能の関係を徹底解説~カスタムHOW TO~
2024.06.01
-

-
日本モータースポーツの歴史を語って映像で残すプロジェクト「レジェンドレーシングドライバーかく語りき」が5月31日より一般公開を開始
2024.06.01
-

-
スバル『WRX』に「tS」、STIチューンの足回り…米2025年型に設定
2024.06.01