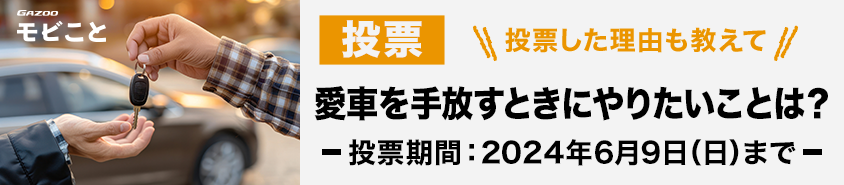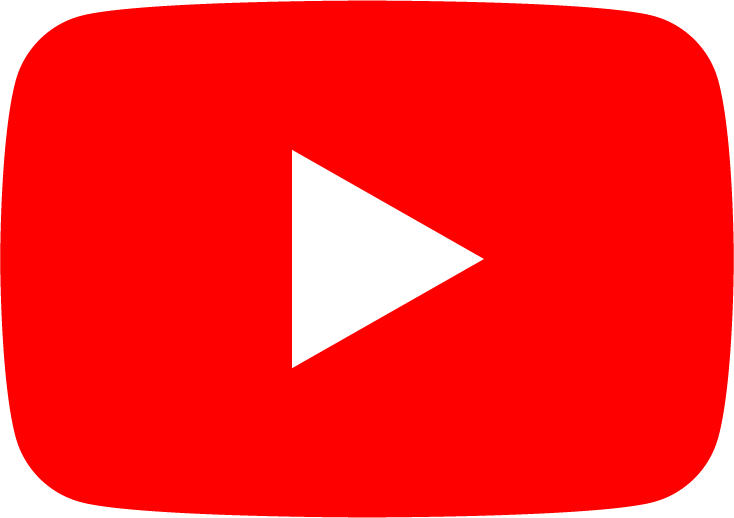マツダの歴代「RX-7」を解説・・・懐かしの名車をプレイバック
一世を風靡(ふうび)したあのクルマ、日本車の歴史を切り開いていったあのエポックメイキングなクルマを令和のいま振り返ってみれば、そこには懐かしさだけではない何か新しい発見があるかもしれない。今回は、マツダ自慢のロータリーエンジンを搭載したスポーツモデル「RX-7」の歴代モデルを取り上げる。
合わせて読む
初代 マツダ・サバンナRX-7 ロータリーで世界に挑んだ意欲作
2代目 マツダ・サバンナRX-7 人気を確立しバリエーション拡大で飛躍
3代目 アンフィニRX-7/マツダRX-7 好きすぎて手放せない
初代 RX-7(1978年~1985年)
初代「マツダ・サバンナRX-7」(SA22C)は、1978年(昭和53年)3月に誕生した。
当時の日本はイラン革命に端を発した第2次オイルショックや、ガソリンエンジン車に対して世界で最も厳しいといわれた昭和53年排ガス規制などによって、スポーツカーに逆風が吹いていた。
そんななかでリトラクタブルヘッドライトの2ドアクーペスタイルをまとって登場したサバンナRX-7は、クルマへの夢を支える一条の光ともいえた。世界で唯一、マツダが量産するロータリーエンジンの小型・軽量という特徴を生かし、低重心のフロントミドシップレイアウトによりスポーツカーとして十分に考慮された設計は、それまでの日本車とは一線を画すものだった。
デビュー当時に搭載された12A型2ローターエンジンはグロス値で最高出力130PSを発生し、前後重量配分は2人乗車時で50.7:49.3、パワーウェイレシオは7.58kg/PSと、スポーツカーにとって理想的な数値がカタログに並べられた。
1982年には最高出力165PSのターボモデルが追加設定され、6.18kg/PSのパワーウェイトレシオを誇った。
2代目 RX-7(1985年~1991年)
1985年10月に登場した2代目「マツダ・サバンナRX-7」(FC3S)は、初代の小型・軽量というイメージを一新する重厚なフォルムが目を引く。滑らかなボディーラインや幅広い偏平タイヤを収めるブリスターフェンダーが特徴で、空気抵抗係数=Cd値は0.32と発表されている。
エンジンは従来の12A型から13B型へ変更。排気量654cc×2の2ローターエンジンは、空冷インタークーラー付きツインスクロールターボチャージャーを組み合わせ、ネット表示で185PSの最高出力を誇った。フロントミドシップの思想を継承したシャシーの前後重量配分は50.5:49.5、「GT」グレードのパワーウェイトレシオは6.54kg/PSと発表された。
サスペンションはフロントがストラット式、リアは初代のリジッドからラテラルロッド付きの独立型セミトレーリングアーム式に変更され、リアサスペンションには「トーコントロールハブ」と呼ばれる4輪操舵システムが組み込まれた。
走りに特化した2座仕様の「アンフィニ」が台数限定モデルとして登場したほか、フルオープンモデルの「カブリオレ」が設定されたのも2代目RX-7のトピックである。
3代目 RX-7(1991年~2002年)
3代目「RX-7」は、マツダが当時行っていた販売ネットワークの5チャンネル化に伴い、アンフィニ店(旧マツダオート店)の専売モデルとして1991年10月に発表された。デビュー当時は販売チャンネルの名称を冠し「アンフィニRX-7」として販売されたが、販売チャンネルの整理・縮小に合わせ1996年10月以降は「マツダRX-7」に車名が変更された。
シャシーは新設計の専用品で、前後のダブルウイッシュボーン式サスペンションやドア、ボンネットなどがアルミ製になるなど、徹底した軽量化を実施。エンジンは13B型2ローターの進化版で、シーケンシャルツインターボが組み合わされる。
最高出力は従来型に比べ50PSアップの255PSを発生、4.9kg/PSというパワーウェイトレシオを達成した。1996年1月のマイナーチェンジでエンジンの最高出力は265PSに向上し、さらに1999年1月のビッグマイナーチェンジで最高出力は280PSに高められた。
2000年以降は進化・改良型の限定車をリリース。2002年8月に最終車両をラインオフし、24年間続いたRX-7の歴史に幕を閉じた。
(GAZOO編集部)
懐かしの名車をプレイバック
-

-
俊敏なFFライトウェイトスポーツカー 2代目「ホンダCR-X」を振り返る…懐かしの名車をプレイバック
2024.04.03 特集
-

-
ホンダが生んだ奇跡のオープンスポーツカー「S2000」を振り返る…懐かしの名車をプレイバック
2024.04.02 特集
-

-
その静かさが高級車の概念を変えた! 初代「トヨタ・セルシオ」を振り返る…懐かしの名車をプレイバック
2024.04.01 特集
-

-
人気ナンバーワンの5代目! S13型「日産シルビア」を振り返る…懐かしの名車をプレイバック
2024.03.31 特集
-

-
ただよう欧州車の香り 初代「日産プリメーラ」を振り返る…懐かしの名車をプレイバック
2024.03.30 特集
-

-
そのカッコよさにみんなシビれた! 憧れた! 初代「日産フェアレディZ」を振り返る・・・懐かしの名車をプレイバック
2024.03.29 特集
RX-7が愛車のカーライフ
-

-
20歳 初愛車でマツダ RX-7を購入した決断は、「回り道せず好きなクルマを買え」という助言
2024.05.29 愛車広場
-

-
父の英才教育でクルマ好きに、今はRX-7を操る
2024.03.03 愛車広場
-

-
ある朝、突然思い立って購入を決断した『青いRX-7』
2024.02.26 愛車広場
-

-
21歳でワイスピ劇中車仕様のオーナーに。RX-7はさまざまな出会いを運んでくれたスペシャルな相棒
2024.01.03 愛車広場
-

-
飽きっぽい性格の僕が熱中したマツダ RX-7への「愛車愛」そして「特別感」
2023.12.23 愛車広場
-

-
新車から35年乗り続けた “家族の一員” であるマツダ・サバンナRX-7は息子へと受け継がれる
2023.10.25 愛車広場
-

-
新車購入して32年19万km、人生を共にしてきたサバンナRX-7(FC3S)にあと10年は乗る
2023.09.20 愛車広場
-

-
マツダ・サバンナRX-7(FC3S)を4台乗り継いだ集大成の1台
2023.07.12 愛車広場
-

-
青春時代の憧れを現実に! マツダ RX-7でのカーライフは家族もうらやむ“リア充”生活に
2023.04.28 愛車広場
連載コラム
最新ニュース
-

-
ブレーキキャリパー進化論、ピストン数と性能の関係を徹底解説~カスタムHOW TO~
2024.06.01
-

-
日本モータースポーツの歴史を語って映像で残すプロジェクト「レジェンドレーシングドライバーかく語りき」が5月31日より一般公開を開始
2024.06.01
-

-
スバル『WRX』に「tS」、STIチューンの足回り…米2025年型に設定
2024.06.01
-

-
ランチアがラリー復帰へ、『イプシロン』新型で…212馬力ターボ搭載
2024.06.01
-

-
『グランツーリスモ7』アップデートを配信開始! EG6シビックやGT500のNSXなど追加車種が盛りだくさん
2024.05.31
-

-
BYD、第5世代PHEV発表…エンジン併用で航続2100km
2024.05.31
-

-
「ワイルドなハスラー」登場! スズキ『ハスラー』仕様変更で装備充実、新モデル「タフワイルド」追加
2024.05.31
最新ニュース
-

-
ブレーキキャリパー進化論、ピストン数と性能の関係を徹底解説~カスタムHOW TO~
2024.06.01
-

-
日本モータースポーツの歴史を語って映像で残すプロジェクト「レジェンドレーシングドライバーかく語りき」が5月31日より一般公開を開始
2024.06.01
-

-
スバル『WRX』に「tS」、STIチューンの足回り…米2025年型に設定
2024.06.01
-

-
ランチアがラリー復帰へ、『イプシロン』新型で…212馬力ターボ搭載
2024.06.01
-

-
『グランツーリスモ7』アップデートを配信開始! EG6シビックやGT500のNSXなど追加車種が盛りだくさん
2024.05.31
-

-
BYD、第5世代PHEV発表…エンジン併用で航続2100km
2024.05.31