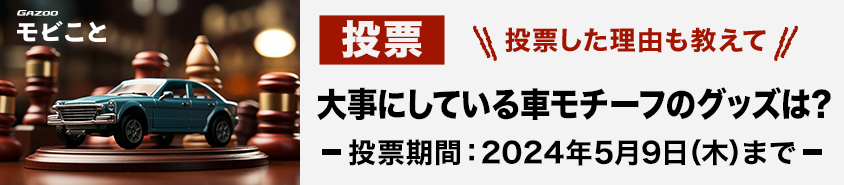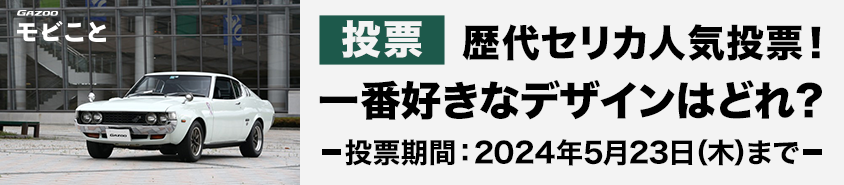日産GT-Rチーフ・プロダクト・スペシャリスト、田村宏志さんに聞く
「日産にいる私と同世代ではご多分に漏れず、小さい頃にハコスカGT-Rのレースを観戦しGT-Rを作るんだとの思いを胸に持ち続けたことが入社したきっかけです」
そう語ってくれたのは、ニスモビジネスオフィス兼・第一商品企画部チーフ・プロダクト・スペシャリストの田村宏志さん。
日産ファンにとっては、GT-R2014年モデルからチーフ・プロダクト・スペシャリストのバトンを前任者から引き継いだ人物として知られているはずだ。
日産の材料研究室を経て、オーテックジャパンで特注車両の担当へ
田村さんは、1984年に日産に入社。学生時代にハコスカと呼ばれたスカイラインGT-R(KPGC10)などで運転技術を磨き、クルマ作りを希望していた田村さんだったが、学生時代に化学を専攻していたため配属されたのはエンジンの材料を評価・研究する材料研究室だった。
ただ、クルマ作りに携わりたいという情熱は入社後も変わらない。そんな田村さんに転機が訪れたのは、入社から3年後のことだった。
「日産に社内公募という制度ができて、それを利用して当時できたばかりのオーテックジャパンに行くことにしました」
オーテックジャパンとは、おもに日産の特装車を製造する会社として1986年に設立。初代社長は「スカイラインの父」と呼ばれ初代から7代目(開発途中で伊藤修令さんが引き継ぐ)までの開発責任者だった“あの”櫻井眞一郎さんだ。
オーテックジャパンに移籍後、とくに一品架装、すなわち特注車両を手がけることになった田村さんにとって忘れられないモデルがある。それは伊ザガート社と共同開発で1990年に限定発売されたオーテック・ザガート・ステルビオだ。
「桜井(眞一郎)さんから『ザガートとコラボするぞ!』と言われ、車両計画図を書くことになったのですが相当苦労しましたね。ベースはレパード(2代目・F31型)やスカイライン(7代目・R31型)をミックスして車両を作りましたが、ブレーキはまた別のモデルから持ってきて、ショックやばねは作り直すなど、ひと言で言うと“ごちゃ混ぜ”。ホワイトボディを日産から部品として購入し組みたてる作業を担当したのですが…当時はペーペーだった私にとって技術屋として先輩方からしごいてもらった1台でした。当時はキツいなと思っていましたけど(苦笑)」
その後、お蔵入りになったもののRVブームを背景に「峠のかっとびワゴン」をコンセプトにしたアベニールの特別仕様や、某テーマパークのキャラクター専用車など本人いわく「色物系」を数多く担当した田村さん。
そんな中でクルマの作り手として、とくにこだわりを反映して仕上げたモデルがある。
こだわりの一台。速さだけではなく、余裕をもった「大人のスカイライン」
それは1992年に販売されたR32スカイライン・オーテックバージョンだ。
R32スカイライン・オーテックバージョンとは8代目スカイラインの4ドアに、NAのRB26型2.6リッター直6エンジンを搭載。ロングツーリングを軽々こなせる「GT」としての性格を強調している。R32型GT-Rを筆頭とする「速さ」を追求したスカイラインのラインナップにはない「大人のスカイライン」だった。
「当初、パワーよりトルクを重視し(R32型スカイラインGT-Rに搭載されていた)ツインターボのRB26型エンジンをシングルターボにして搭載し、4ドアなので2ペダルのほうがいいだろうとトランスミッションはATを組み合わせたいと考えていました。結局、シングルターボについては実現せず、ハイコンプレッションにしたNAのRB26型エンジンを搭載しましたが、GTカーとして速さだけでなくゆったりと走ることができたり、長距離を走ることもあるという要件を踏まえて作ったクルマでしたね」
スポーツカーといえど快適性を備えていることが当たり前だった現代とは違い、「スポーツカー=スパルタン」だった当時としては異例ともいえるモデルだったが、日産へ戻ったあとも同じコンセプトでスカイラインの限定車を発表している。
乗り心地と上質な内装を携えた、R34型スカイラインGT-R・Mスペック。そして、こだわりは、次のクルマへ
「大人の感性を刺激する」をテーマに仕上げられ2001年に登場したR34型スカイラインGT-R・Mスペックがそれだ。
路面の細かいストロークを吸収する効果があるリップルコントロールショックアブソーバーを装着したスカイラインGT-R・Mスペックは、乗り心地や路面との接地感が向上。また職人が手がけたコリノ本革シートをスカイラインシリーズとして初めて装備したモデルだ。
「GT-Rなので速さを追求する方向は変わりませんが、速さだけを求めていない大人たちもいるはずだと、そういう方をターゲットにしたモデルでした。R33型、R34型スカイラインの輸出仕様を手がけたときイギリスではこのクラスのスポーツセダンはシートがファブリックではありえないと本革を装着したのですが、その経験から大人向には本革シートだよねとシートメーカーに作ってもらったのです。ただ、本革シートは座ると冷たいですよね。そこでシートヒーターを装着したのですが、GT-Rは軽量化のため小さなバッテリーを積んでいました。当然、容量が足りずに全車寒冷地仕様のバッテリーを積んだので重くなっちゃいましたね(苦笑)」
当然、車重が増すとサーキットでのラップタイムは落ちるのは当然だ。しかし、サーキットや一般道での速さだけを追求した方向性とは違い、ロングドライブを楽々とこなすため乗り心地や上質な内装を重視したのは、この先、足が硬くてスパルタンなだけではスポーツカーが生きていけない時代になることを感じていたからだ。
その思想を如実に反映したクルマが2001年の「第35回・東京モーターショー」に出展されたGT-Rコンセプトだろう。
究極のドライビングプレジャーを具現化したモデルと説明されたGT-Rコンセプトだが、次期GT-Rを示唆するモデルであることは明らかだった。このクルマのコンセプトをまとめたのは田村さんだったのだ。
GT-Rコンセプトは東京モーターショーの会場だけではなく、国内外で大きな注目を集めたが、その理由のひとつがMTではなくパドルシフトでシフトを操作する2ペダルだったことだ。
GT-Rが目指すもの。テーマは「究極のドライビングプレジャー」
「スポーツカーはMTだと思われていた当時、インパネにシフトレバーがないのはGT-Rらしくなく軟弱なクルマだ、と大いに叩かれましたね(苦笑)」
GT-Rファンのみならず社内からもMTを採用しないことについて異論が相次いだというが、これからの時代、「究極のドライビングプレジャーを追求」をテーマに掲げるGT-RにはMTより2ペダルが必要だという信念を突き通した。
「クルマの能力が向上し続ける性能に対して人間が操作できる能力は変わりません。『究極のドライビングプレジャーの追求』、すなわちいつでもどこでも最高の喜びを与えるスーパースポーツであれば、これからの時代はドライバーが運転に集中してもらうために2ペダルですよと。社内の数多くいたGT-Rに思い入れのある先輩にはそう説きましたし、役員にはパドルシフトで操作することでラップタイムが1周あたり15秒くらい稼げることをデータで示しました。速さを求めるなら、2ペダルでパドルシフトしかないと」
パワーが上がり車速が上がれば、当然、操作が大変となる。スピードが増した分、また加速力でG(重力加速度)がかかる分だけコントロールしにくくなり、それを各種デバイスで補う。これは新世代GT-Rに必要であると考えた。 これは時代背景を考えて、会社ではなくユーザーの方に目を向けたクルマを作る、という田村さんの哲学そのものだ。
我々が作るのは、現代のスポーツカー。さまざまなニーズを表現するためにも、過去を理解し、現代にアジャストするべき
この哲学は2014年からチーフ・プロダクト・スペシャリストとして携わることになった現行GT-Rにも大いに反映されている。
「サーキットで速いこと、かつグランツーリスモ(GT)をきっちりやれるのがGT-R。ただレーシングカー寄りの性能ばかりやると日常使用で支障がでるし、GT寄りにするとクルマが重くなって遅くなる。速さにこだわる世界観を持つ人向け、また、それだけにこだわらない大人たち向けの両方を表現できないかなと思ったのがGT-Rの2014年モデルです」
2014年モデルは足まわりが硬かったそれ以前のモデルから乗り味を良くするため、ばね、ショック、ブッシュ、スタビライザー、タイヤ、全部変えた。また、スポット溶接ではなくボディの要所要所を構造接着剤で留めた“ボンディングボディ”を採用するなど、サーキットでの速さにこだわったGT-Rニスモを合わせてラインナップした。
「私にとってニュルブルクリンクで7分を切ることと、助手席に乗せた彼女や奥さんと極端に言えば時速300kmで走行しながらも車内で会話ができ、300kmの距離を1時間で着くことは同じ価値。もし『スポーツカー=スパルタン』という昔の時代が続いていたなら2013年までの硬い足まわり一本でいけたかもしれません。我々は現代のスポーツカーを作っているので、現代にアジャスト(合わせる)すべきです。ただ、いまのクルマがスポーツカーではないと昔のクルマを所有している人は理解できます」
そう語る田村さんの愛車は26年前に購入したR32型GT-R。
MTこそスポーツカーなのだと言われていた時代のクルマをけして否定しているのではないのだ。 ただ、田村さんの哲学を注入しているクルマはGT-Rだけではない。
「私のフィロソフィー(哲学)を反映させるクルマとして1000万円を超えるGT-Rだけではなく、ノートやマーチといったクルマでも表現したいのです。たとえばオリジナルのフロントバンパーやスポイラーを装着した外観がカワイイね、コンパクトでいいよねと150万円のマーチ・ニスモで十分という人と、ニスモが手がけるならエンジンチューンが必要だと言う人が選ぶ180万円のマーチ・ニスモSがあります。GT-RとGT-R・ニスモ以上に差があるかもしれないですけど、数多くのお客様が私たちが感じているドライビングプレジャーの世界観にいらっしゃっていただけるじゃないですか。私のフィロソフィーを200万円くらいで表現するにはちょうどいい。GT-RやZのチーフ・プロダクト・スペシャリストではありますが、私の仕事はニスモのラインアップをまとめることが主だと考えています」
2015年現在、次期GT-Rは、まだ私の頭の中。概要は、まだ先の話
最後に、私を含め多くの人が気になっている「次期GT-R」について質問をぶつけてみた。
「私がまとめに関わり、こないだまで開催していた第44回・東京モーターショーに出展した“ビジョン・グランツーリスモ” のリアテールランプを丸目にしたことで、あれは次期GT-Rだとか、ビジョンだという車名で(次期GT-Rと見られることから)逃げているとか言われていますが、あれは完全なコンセプトカー。次期モデルはまだ私の頭の中にあるので、出していないのが本当のところ。スクープ誌などでは日産の関係者から聞いたと記事が出ていますが、まだ社内の関係者、下手すると一番上の人にも話していないのに知りようがないですよね(笑)。いま話しているこの瞬間まで、私は次期モデルのコンセプトを作る責任者ですが、その概要を出すのはできるだけ遅くしたいと考えています」
(文:手束 毅 写真:小林和久/日産自動車)
自動車業界人インタビュー
[ガズー編集部]
連載コラム
最新ニュース
-

-
【ホンダ ヴェゼル 改良新型】CMFデザイナーが語る、新グレード「HuNT」にこめた「気軽さ」の表現とは
2024.05.02
-

-
季節の変わり目にエアコンが発する悪臭の正体とは? DIYで解決!~Weeklyメンテナンス~
2024.05.02
-

-
BMW 4シリーズ グランクーペ が新フェイスに、改良新型を発表…北京モーターショー2024
2024.05.01
-

-
トヨタがインドで新型SUV『アーバンクルーザー・タイザー』を発表…Aセグメント再参入
2024.05.01
-

-
メルセデスAMG『E53』新型、612馬力の電動セダンに…欧州受注開始
2024.04.30
-

-
この顔で中国EV市場に“爪痕”残すか? 日産『エピック・コンセプト』は26年までに市販へ…北京モーターショー2024
2024.04.30
-

-
トヨタ・クラウンのアウトドアカスタム「LANDSCAPE」がお披露目…移動時間すらも記憶に残るような車に
2024.04.30
最新ニュース
-

-
【ホンダ ヴェゼル 改良新型】CMFデザイナーが語る、新グレード「HuNT」にこめた「気軽さ」の表現とは
2024.05.02
-

-
季節の変わり目にエアコンが発する悪臭の正体とは? DIYで解決!~Weeklyメンテナンス~
2024.05.02
-

-
BMW 4シリーズ グランクーペ が新フェイスに、改良新型を発表…北京モーターショー2024
2024.05.01
-

-
トヨタがインドで新型SUV『アーバンクルーザー・タイザー』を発表…Aセグメント再参入
2024.05.01
-

-
この顔で中国EV市場に“爪痕”残すか? 日産『エピック・コンセプト』は26年までに市販へ…北京モーターショー2024
2024.04.30
-

-
メルセデスAMG『E53』新型、612馬力の電動セダンに…欧州受注開始
2024.04.30