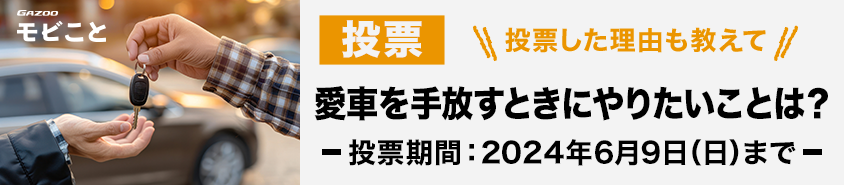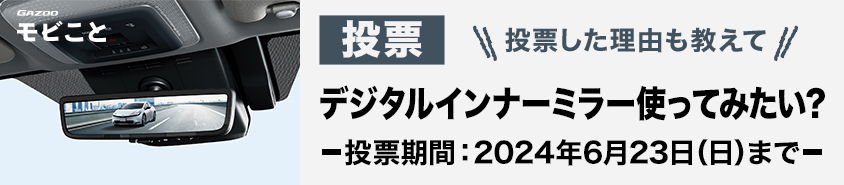デビュー当時の雰囲気が色濃く感じられる愛車。1995年式アンフィニ RX-7 タイプRS(FD3S型)
これまで何度も書いているが、この取材を続けていると最近強く感じることがある。年月が経過したからこそ湧き起こる感慨深さだ。クルマの年齢よりも若いオーナーが増えたり、純正にこだわるオーナーが少なくない。取材を通じたクルマを愛でる人たちとの出会いは何物にも代えがたい。
今回の主人公も、30代前半の男性オーナーだ。愛車とはほぼ同世代といっていいだろう。クルマ好きの父親の影響で、幼少期よりスポーツカーやレースゲームに親しんだ。そして高校生になると、トヨタの「メガウェブ」や、いまはなき「アムラックス」に通っていたという。運転免許取得後は日産 シルビア(S15型)を所有し、今から2年前の結婚直前に、憧れだったアンフィニ RX-7タイプRS(FD3S型、以下RX-7)に乗り換えて現在に至る。そんなオーナーに、まずはRX-7に憧れたきっかけを伺ってみた。
「小学校低学年のころ、父とドライブ中に白いスポーツカーとすれ違ったんです。それがあまりにも美しく、強烈な印象だったので、父に教えてもらってRX-7という存在を知りました。当時遊んでいたプレイステーションの『グランツーリスモ』でもRX-7を選んでいましたし、いつしか憧れのクルマになっていきました。今、現実に所有できていることで、ゲームでは味わえなかった魅力をたくさん知ることができています。とても幸せです」
そう話すオーナーのRX-7は、1995年式。オドメーターは14万キロを超えており、さらに生産から20年以上が経過しているとは信じられないほどのコンディションをキープしている。そして、RX-7といえば何らかのモディファイが施されている個体が多いなか、ほぼフルノーマルなのは稀有な存在ではないだろうか。当時の雰囲気を知る人が街中で目にしたらハッとするにちがいない。
オーナーの個体は「3型(前期型)」の「タイプRS」と呼ばれるグレード。当時の販売系列店「アンフィニ」を車名に冠していたため、マツダではなくアンフィニブランドのエンブレムが装着されている。オーナーは、この前期型のスタイルが大変気に入っているため、歴代オーナーがモディファイした箇所の“ノーマル戻し”を行った。納車当初に装着されていた社外品のマフラーは純正品に。後付けの追加メーター類も取り外した。言わずもがな、リアスポイラーやテールランプも前期型のままだ。そこまで徹底して純正にこだわる、オーナーの思いにせまってみた。
「私が前期型にこだわる理由は、RX-7のデザイナーが一番作りたかったモノが、前期型に集約されていると感じているからです。90年代前半にこのデザインが、ほぼそのまま世に出たこと自体すごいことだと思います。当時の国産車は、海外のスポーツカーを意識したデザインが多かったなか、こんなにもオリジナリティを感じるデザインは稀だと思うんです。『このデザインを世に送り出すべく、試行錯誤を繰り返して生産・量産にこぎつけたに違いない』と思わせるマツダの情熱を感じます。でも正直なところ、後期型パーツの流用に心が動くときもあるのですが、最終的には前期型にこだわりたいという思いがいつも勝りますね」
「とにかくデザインに惚れ込んだから」と語るオーナーの、前期型への愛は深い。
RX-7のボディサイズ(3型)は全長×全幅×全高:4280x1760x1230mm。シーケンシャルツインターボを搭載した2ローターの13B型エンジンは、3型で255馬力を叩き出す。この名車を所有できているという“幸せオーラ”が、オーナーからひしひしと伝わってくるわけだが、この個体との出逢いには、どんなエピソードがあるのだろうか。
「購入しようと決心してから、およそ半年間で10台ほど現車を確認しました。条件は前期型であること、そして程度の良い『ノーマルに近い個体であること』でした。ボディカラーが赤であることはたまたまです。ショップのなかには『ロータリーエンジンのクルマはこんなものです』と売りつけてくるケースもあると聞いたので、しっかりと吟味することを心がけました」
日々愛車に接するなかで、特に幸せだと感じる点はどこかを尋ねてみた。
「あらゆる部分に“スポーツカー”を強く感じられる点でしょうか。斜め後ろからのスタイルが好きで、眺めるたびにうっとりしています。実用性とデザイン性を兼ね備えたドアハンドルや、カップホルダーがあえて装備されていない点にもスポーツカーの美学を感じます。たとえ同乗の友人に不便がられても“これはジュースを飲みながらドライブするクルマじゃないんだよ”と言うと思い切り引かれますね(笑)」
唯一無二といわれるロータリーエンジンに感じている魅力は?
「以前乗っていた日産 シルビア(S15型)のSR20DET型は、回転数が上がると特有の振動があって、そこが好きな部分でもありましたが、この個体に搭載された13B型は、エンジンの振動がほとんどなく、吹けあがりの良さが抜群だと感じました」
さらに、乗りはじめて感じた変化を伺った。
「安全運転はもちろん、思いやりのある運転を、一層心がけるようになった気がします。“RX-7乗り=マナーが悪い”と思われて、クルマそのもののイメージダウンにもなってほしくないので……」
乗り手としての“ありかた”までも、深い思考をめぐらせているオーナー。趣味性が高いクルマゆえ、同じ車種のオーナー同士での交流はあるのだろうか。
「私の知っているRX-7のオーナーさんは、最年少は19歳から定年退職された方まで幅広いですね。オーナーズクラブのようなコミュニティも存在しています。さまざまなオーナーさんがいらっしゃいますが、全員に共通しているのは、このクルマが『FDが好き』という気持ちでしょうか。長年大切に乗り続けている方も多いです」
しかし、年式が年式なだけに、経年劣化によるトラブルは避けられないと思う。そこで、これまでのトラブルやメンテナンスで苦労している点などを伺ってみた。
「実は、直しても直しても修理が続いた時期があったんです。こういうクルマなので、ある程度は覚悟していたつもりだったものの、心が折れそうになったことがありました(笑)。今は“ひとまず試練の時期を乗り越えた”と安堵しています。これまで修理した箇所は、吸気温・ノッキング・スロットル・O2の各センサー、ソレノイドバルブの交換、ECUの交換、エンジンとミッションの間のシール交換、インマニの紙製ガスケットの交換です。圧縮比は定期的に確認してもらっています」
今後、この愛車とどう接していきたいかを伺ってみた。
「この先、環境の変化などで手放すときまで、一緒に走って良い想い出を重ねていきたいです。家族が増えたときは、父に託すと決めているんです。クルマ好きな父も乗りたがっていますし、再び中古車市場に流れてモディファイされることを考えると淋しくなってしまうので。父に託せば、もし手放しても、実家へ行けば会えるので安心できます」
例えオーナーの生活環境が変わろうとも、オーナーの家族によってこの個体はこれからも慈しまれていくのだ。そう思うと、心を打たれずにはいられなかった。
開発者へのリスペクトが随所に感じられた今回のインタビュー(オーナーは無意識だったそうだが)。今回は、開発陣へのメッセージで締め括ってもらった。
「当時の持てる力のすべてを注いで“イチバンのクルマを作りたい!”という情熱が、クルマを通して伝わってきます。乗っている側は、その情熱を受け取って感じていますよ」
「後世に残るということは、情熱を受け取るということ」。まさにその場面を目にできたようで、万感の思いだった。この先、オーナーが新しい命を授かったなら、子どもたちにもこのRX-7のスピリットが受け継がれるような気がしてならない。仕事の枠を超え、いちクルマ好きとして、オーナーの“愛車愛”を感じることができた幸せな時間だった。
(編集: vehiclenaviMAGAZINE編集部 / 撮影: 古宮こうき)
[ガズー編集部]
こだわりの「フルノーマル」の愛車たち
愛車紹介 新着記事
-

「いうことなし」な人生最後の愛車を娘婿が受け継ぐ。5速MTの1999年式トヨタ カローラ SEサルーン(AE110型)
-

「ジャパン・ブルー」に運命を感じて。27歳の藍染職人を魅了する1997年式 光岡 ガリュー(HK30型改)
-

30年以上の時を経て26歳のオーナーを魅了する、1992年式マツダ センティア エクスクルーシブ(HDES型)
-

29歳のオーナーが幼少期の「原体験」を大人になって再現。1994年式マツダ ユーノス500 20E(CAEP型)
-

29歳のオーナーが受け継いだのは、父が引き取った“発注ミス車”の1990年式ホンダ プレリュード Si 4WS(BA5型)
-

26歳のオーナー兼主治医曰く「大切な存在だけど大事には扱わない」1988年式日産 サニートラック ロング(L-GB122型)
-

新車から20年。「次の20年」を一緒に生きるためのレストアを決行!2004年式ホンダ S2000(AP1型)
-

幼なじみとの友情が導いた愛車、クルマの価値観を変えてくれた2014年式トヨタ ランドクルーザー 70(GRJ76K型)
愛車広場トップ
連載コラム
最新ニュース
-

-
ブレーキキャリパー進化論、ピストン数と性能の関係を徹底解説~カスタムHOW TO~
2024.06.01
-

-
日本モータースポーツの歴史を語って映像で残すプロジェクト「レジェンドレーシングドライバーかく語りき」が5月31日より一般公開を開始
2024.06.01
-

-
スバル『WRX』に「tS」、STIチューンの足回り…米2025年型に設定
2024.06.01
-

-
ランチアがラリー復帰へ、『イプシロン』新型で…212馬力ターボ搭載
2024.06.01
-

-
『グランツーリスモ7』アップデートを配信開始! EG6シビックやGT500のNSXなど追加車種が盛りだくさん
2024.05.31
-

-
BYD、第5世代PHEV発表…エンジン併用で航続2100km
2024.05.31
-

-
「ワイルドなハスラー」登場! スズキ『ハスラー』仕様変更で装備充実、新モデル「タフワイルド」追加
2024.05.31
最新ニュース
-

-
ブレーキキャリパー進化論、ピストン数と性能の関係を徹底解説~カスタムHOW TO~
2024.06.01
-

-
日本モータースポーツの歴史を語って映像で残すプロジェクト「レジェンドレーシングドライバーかく語りき」が5月31日より一般公開を開始
2024.06.01
-

-
スバル『WRX』に「tS」、STIチューンの足回り…米2025年型に設定
2024.06.01
-

-
ランチアがラリー復帰へ、『イプシロン』新型で…212馬力ターボ搭載
2024.06.01
-

-
BYD、第5世代PHEV発表…エンジン併用で航続2100km
2024.05.31
-

-
『グランツーリスモ7』アップデートを配信開始! EG6シビックやGT500のNSXなど追加車種が盛りだくさん
2024.05.31