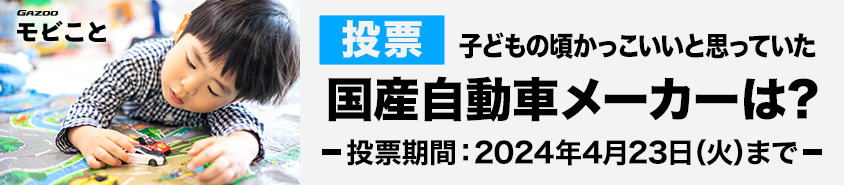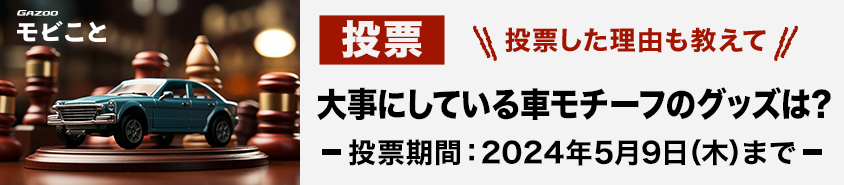ハイラックス 開発責任者に聞く - 共に創っていくクルマ -
ハイラックスの初代が登場したのは1968年。その後、世界各国で生産され、これまで180以上の国と地域で1600万台以上が販売されているピックアップトラックである。その壊れないタフさは、ランドクルーザーと並んで、世界中で高い支持を得ている。
2004年からはトヨタの世界戦略車IMV(Innovative International Multi-purpose Vehicle)プロジェクトの中核車として発売、その後も開発・生産が続けられ、2015年には8代目のハイラックスが販売されている。一方、国内では2004年に生産・販売が中止されていた。
しかし、今回、8代目のハイラックスが日本で販売される。13年ぶりの国内復活。その背景や狙いについて、ハイラックスのチーフエンジニアである前田昌彦氏に話を聞いた。
前田昌彦(まえだ・まさひこ)
1969年東京生まれ。東北大学工学部大学院卒。中学生の時からクルマに興味を持つようになり、高校時代にはチーフエンジニアに憧れる。就職にあたってはいろいろな選択肢の中から、「好きこそモノの上手なれ」「自分の得意なことをやるということが社会貢献につながる」という本田宗一郎氏の言葉が決定打となり、1994年トヨタ自動車入社。第一パワートレーン設計部配属。商用車の6気筒エンジンの開発などを担当。
将来、チーフエンジニアになるべく、「38歳で製品企画部に異動」と自己申告に書き続け、2001年、32歳のときに製品企画部に異動。初代IMVプロジェクトに参画。2004年初代IMVを発表後は、欧州での生産立ち上げを終えて、2005年から三代目プリウスの開発チームに異動。2009年からは再びIMVプロジェクトに戻り、2代目IMVの開発を担当。現行の8代目ハイラックスを2015年にタイで発表。2016年よりIMVプロジェクト(ハイラックス、フォーチュナー、イノーバ)のチーフエンジニアに就任。現在に至る。趣味はクルマとスキー。現在の愛車はランドクルーザーシグナス。
学生時代にピックアップトラックに乗っていました。
中学生の頃から『週刊少年ジャンプ』や『週刊少年マガジン』じゃなくて、『カートップ』や『ベストカー』『CAR and DRIVER 』を毎号買って読み漁る。そんな“クルマバカ”な少年だった私が、学生時代に一目惚れというか、衝動的に、購入したのがクライスラーのダッジ・ダコタです。全長5メートルのピックアップトラックのオープンカー。
その前に乗っていたコンパクトで俊敏なプジョー205 GTIとは、真逆の趣きのクルマです。周囲からは「この狭い日本でそんなクルマを買ってどうするの?バカじゃないの?」と呆れられました。
たしかに、大きすぎて取り回しは面倒。駐車場に入れるのもひと苦労です。シングルキャブなので後部座席がないため、荷物は荷台に積むことになりますが、雨が降ったら大変で、すぐに手当をしないといけない。ゴミ袋に荷物を入れて、走っていました(笑)。そして、1ナンバーの商用車なので毎年車検。税金こそ、少しお安くなりますが、高速道路やカーフェリーの料金もちょっと高くなります。

- 前田チーフエンジニアの学生時代の愛車「ダッジ・ダコタ」(1990年製)。ピックアップトラックのオープンカーと山の情景との佇まいが、たまらなく好きだったという。
でも、このクルマにはそんな不自由さや不便さを吹き飛ばしてしまうような愉しさ、他のクルマではけっして味わえない官能的な魅力がありました。なんといっても、大きくてゴツくてカッコいいボディ。街中を走るとみんながこっちを見ている(ように感じる)存在感。アイポジションの高いオープンカーの爽快感。プジョー205で味わえる運転する愉しさとはまた違った、ピックアップトラックが持つ「佇まい」が気に入っていました。速く走るなんて、もはやどうでもいい。そんな気持ちにさせてくれるクルマでした。運転席の高さがかなり違うので、同じ道を走っても、プジョー205とは違う景色が流れ、このクルマならではの気持ち良さがありました。
このクルマに出会って、私のクルマに対する価値観にも大きく影響し、楽しみ方の幅が広がりました。
13年ぶりの国内販売再開の舞台裏。
さて、そんなクルマバカだった私がいま、トヨタの世界戦略車IMVのチーフエンジニアとして、世界のいろいろな道を走り、多くの人たちから愛されてやまない“タフで壊れないクルマ”、ハイラックスのヘリテージ(遺産)を引き継いで、その開発を担当しています。
ご存知の通り、2004年にハイラックスの国内生産・販売は終了しました。理由は使い勝手や実用性の点から日本の市場にはピックアップトラックは根付かないという判断からです。ではなぜ、今回、販売を再開することになったのか?
きっかけは2013年だったと思いますが、ある販売店から私たちに寄せられた、「国内に保有されているハイラックス約9000台が、買い替え時期を迎えて、買い替えていただくクルマがありません。なんとかしてください」という要望でした。
メーカーとして、これはみすごすことはできません。私たちはすぐに動き出しました。しかし、私たちの前には日本の排ガス規制という大きな壁が立ち塞がっていました。日本の排ガス規制はとても厳しい基準なので、海外で走っているディーゼル車をそのまま持ってくることはできません。もちろん、ガソリン車なら可能でしたが、いま保有されているお客様のほとんどが北海道で農業や林業などの仕事で使われているワークユースのお客様でした。みなさんご自宅には農機具用などの軽油のタンクがある。ちょっと給油にガソリンスタンドまでといっても、北海道だとかなり遠方まで出掛けないといけません。だから、やっぱり自宅で給油したい。また、ディーゼルの方がトルクが出るし、燃料コストも安くてすみます。ですから、ディーゼルにはこだわっていました。
そこで、プラドと一緒に新型のディーゼルエンジンと排気システムを開発しました。開発に時間がかかり、お客様を大変お待たせすることになってしまいましたが、なんとかディーゼル車を日本に持ってくることができました。
今回の販売再開にあたり、まずはハイラックスを保有されているお客様にきちんと新しいハイラックスをお届けする。メーカーとしてはそれが第一義ではありますが、たとえば、ピュア・オフローダーと呼ばれるオフロードが大好きなお客様。バリバリのオフロードタイヤを履き、車高を上げ、シュノーケルをつけて走破するといった使い方にも、世界で評価され続けているハイラックスの高いオフロード性能は十分ご満足いただけるはずです。また、荷台にジェットスキーとかキャンプ道具などを積み込んで海へ山へとレジャーに出掛けていく方にも重宝されるでしょうし、さらには、単純に街乗り(アーバン・ピック)として、街中をガンガン音楽をかけて走ったらカッコいいよねと思う人もいらっしゃることでしょう。
今回発表された トヨタ ハイラックス Z(ネビュラブルーメタリック)
世界でタフを極めたハイラックスの開発
8代目ハイラックスの開発は、「単に壊れないだけが、タフじゃない。もう一度、実用性の面から、タフを再定義しよう」というテーマを掲げ、世界中の道や仕事場へ実際に行って、ハイラックがどんな使われ方をしているのかを徹底的に研究して、様々な使い方に耐えうる機能的価値の向上を図りました。
たとえば、ニュージーランドの畑に行った際は、「昔は4WDのローギアに入れておけば、アクセルを踏まなくても一定の早さでクルマが動いたので、クルマを走らせながら収穫ができた。いまはそれができない。改善して欲しい」という要望をお聞きしました。これは燃費重視のギア比の設定に改良した結果そうなってしまっていたわけですが、これについては試行錯誤の末に、5速から6速にギアを増やして、燃費とデフのギア比の最適化を図ることで解決しました。
また、オーストラリアの森林管理局のハイラックスに乗せてもらったときは、車内に6個くらいトランシーバーがありました。いろいろな人と交信するためにどうしてもその数が必要だが収納場所に困っていると聞き、私たちが「ありったけ収納」と呼ぶ、乗用車に引けを取らない収納の工夫をしました。さらに、車内でトランシーバーを使うには静寂性も重要と再認識しました。つまり、音の静かなディーゼル・エンジンが求められていると。こうしたことは現地に行ってみなければ分からない気付きばかりでした。
そういう実用的な快適性、利便性。これらも広い意味での「タフさ」だと考えています。
-
-

- タイの小口配送トラック(個人運送業)
-
-
-

- オーストラリアの農場
-
世界各地の仕事現場へ足を運び、ピックアップトラックの使われ方を聞きまわった。
正直なところ、今回のハイラックスは日本の排ガス規制に適合させたことを除いて、日本専用に開発したものではありません。でも裏返せば、世界仕様、世界標準のピックアップトラックをそのまま逆輸入しています。この機会に、世界中を回ってタフを極めたハイラックスとはどんなものかを、ぜひ体験していただきたいです。
日本の新しいお客様にもぜひ知ってほしい。ハイラックスは、本物が分かる人のクルマ。

- オフロード走行性能テストの様子(8代目ハイラックス プロトタイプ)
歴代、ハイラックスの開発では「道が人を鍛えて、人がクルマを造る」という理念のもと、開発者は実際にクルマが使用されている現場に足を運び、その使い方を現地現物で確認し、使い勝手を改善しています。また、“壊し切り”という開発手法で、壊れるまでテストを続け、耐久性の向上にも努めています。ハイラックスは、長い年月をかけ、こうして鍛え・磨き上げられた「壊れない」ヘリテージを受け継いできた歴史があります。

- オフロード走行性能テストの様子(8代目ハイラックス プロトタイプ)
2004年に国内で生産・販売がストップして13年が経ちました。この間に、クルマも使い勝手や利便性、環境性能などの点で大きく進化しています。なによりもクルマに対する価値観が大きく変化しています。もしかしたら、最近のクルマに飽きてしまい、もっと違う、自分の感性にピンと響くようなクルマをお探しのお客様がいらっしゃるかもしれない。
そんな方にこそ、ハイラックスを提案してみたい。かつて私がピックアップトラックとの出会いでクルマに対する価値観が変わったように、それはその人生やライフスタイルを変えてしまうような衝撃的な出会いになるかもしれない。それくらい、ハイラックスは刺激的で個性的な、他に類を見ないクルマだと自負しています。
-

- オーストラリアの実環境で、走破性を確認する様子。(8代目ハイラックス プロトタイプ)
「日本の市場にはピックアップは根付かない」と思っているのは実はメーカーだけの思い込みで、お客様は単に知らないだけ、気づいていないだけなのかもしれない。それをメーカーの都合だけで販売中止にしているのは時代に合っていないのではないか。今一度、日本の市場にピックアップトラックを提案していこう。それは私たちにとって新しい挑戦でもあります。
そして、そんな挑戦を後押ししてくれた出来事がありました。ちょうど3年前のランドクルーザー70の大ヒットです。期間限定の国内販売再開でしたが、あんなに売れるとは誰も予想できませんでした。見事なまでに予想が裏切られました。
およそ日常生活の使い勝手を考えると利便性が高いとはいえず、燃費も悪いし、しかもマニュアル。さらにはハイラックスと同じく、1ナンバーの商用車で1年車検、高速料金もちょっと高い、そんなクルマがなぜあんなに売れたのか?販売店の人に聞いても明確な答えは分かっていません。
少なくともいえることは、「ランクル70が持っている本物感」「限定販売」「自分だけの」「歴史が証明する裏付け」がキーワードだったこと自分は感じています。
それは、ハイラックスにも同様に当てはまります。壊れない本物のヘリテージと、世界中でタフを極めたハイラックスを、日本で試す時がやってきた!そう強く思いました。
中でも、私たちが特に注目しているのはアクティブシニアと呼ばれる団塊の世代のお客様です。バブルも経験し、本物を見抜く目を持っている。そして、「自分らしく生きたい」さらには、「いつまでも元気にはつらつと生きたい」とお考えのみなさんに、ハイラックスを提案してみたいと思っています。実際、ランクル70を購入された方にもアクティブシニアのお客様がたくさんいらっしゃいました。
そして今回、MTではなくATを採用。4WDへの切り替えは、従来の固いレバー式じゃなく、スイッチにするなど、女性や幅広い年齢層の方に、お乗りいただきやすくしました。
また、世界中で販売されているハイラックスだからこそ、カスタムパーツも豊富に揃っています。それらを取り寄せて、自分だけのハイラックにカスタマイズできることも魅力のひとつです。
お客様とともに作っていく「共創」
「過去からの延長線上に未来はない」。そんな大きな変化がいま市場で起こっていると感じています。さらには、モノの消費からコトの消費へ、「それを使って何をするか?」、さらにはそれを所有している意味的な価値へと、お客様の価値観が大きく変わっています。
コト消費の時代には、従来のメーカーのモノ消費のマーケティングは通用しません。メーカーは過去の先入観を一旦捨てて、謙虚になって、市場やお客様と対話することが重要だと思います。そのために、私たちは販売店の力も借りながら、お客様と対話していきたいのです。いわば、お客様、販売店とメーカーが一緒になって、コトづくりをしていく、そんな「共創」という考え方です。
「日本にはピックアップは根付かない」といわれて来たハイラックスがお客様にどう評価されるのか?どんな方が興味を持ち、購入され、また、どんな使い方をされるのか?
私たちが想像もしなかったような「コト消費」があるかもしれません。もしくは、期待と裏腹に、全く売れなかったということもあり得るかもしれません。
いずれにしても、このクルマが発売後、どんなことがおこるのか? いまはとてもワクワク、ドキドキしています。
取材・文・写真:宮崎秀敏(株式会社ネクスト・ワン)
[ガズー編集部]
関連リンク
連載コラム
最新ニュース
-

-
車中泊を快適に! ランドクルーザー250 用ベッドキット登場
2024.04.19
-

-
トヨタ カムリ 新型、全車ハイブリッドに
2024.04.19
-

-
シトロエンの新デザイン採用、『C3エアクロス』新型を欧州発表
2024.04.19
-

-
トヨタ ランドクルーザー250 をモデリスタがカスタム…都会派もアウトドア派も
2024.04.19
-

-
マツダ、新型3列シートSUV『CX-80』をついに世界初公開 日本導入時期は
2024.04.19
-

-
アウディ Q8、e-tron史上最長の一充電航続距離619kmを実現…オプションパッケージ発売
2024.04.18
-

-
アルファロメオ『ジュニア』がミラノ・デザインウィーク2024に登場
2024.04.18