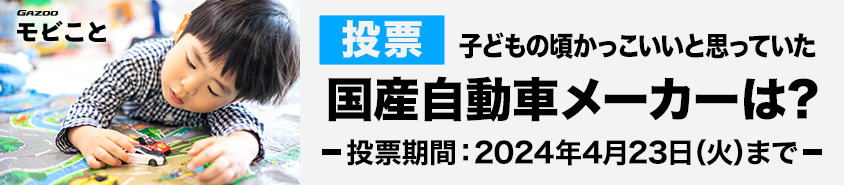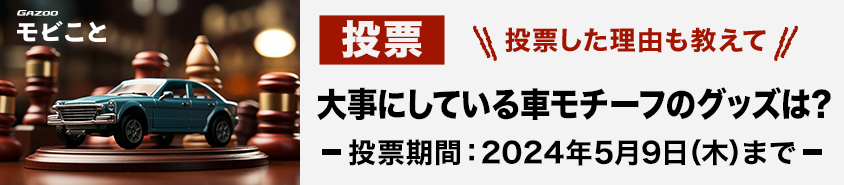日本グランプリの思い出(前編) ―津々見友彦―
レースを過熱させたモータリゼーションの機運
日本で最初のサーキットといえば、1936年に開業し、本田宗一郎さんもカーチス号で走ったという一周1.2㎞のダートのオーバルトラック「多摩川スピードウヱー」だろう。四輪のレースはこの頃には行われていたのだ。
しかし、本当に近代的なモータースポーツがスタートしたのは、宗一郎さんが1962年に鈴鹿サーキットを造ってからだ。それまで、主としてモータースポーツは二輪車の世界だった。北軽井沢の公道コースやダートの浅間高原自動車テストコースでは「全日本オートバイ耐久ロードレース」「クラブマンレース」などが開催され、バイク雑誌が二輪の英雄たちの活躍を伝えていた。
一方、四輪のレースとしては1963年に鈴鹿サーキットで日本初となる本格的なロードレースが開催される。「第1回 日本グランプリ」だ。まだクルマは一家に一台ではなく、これから普及が始まるという時代だった。
1955年には通産省が国民車構想を発表し、1958年にはこのコンセプトに沿った「スバル360」が登場。1961年にはトヨタから「パブリカ」が38万9000円(現在の価値で約200万円)で販売され、憧れのマイカーがグッと身近になった。また、1964年開催の東京オリンピックに向けて首都高速道路が部分開通。名神高速道路も栗東まで延び始めていた。
何より、国民全員がアメリカの近代的なライフスタイルに憧れていた。その中心にあるのがクルマであり、自家用車を持つのが最大の憧れだった。それだけに各自動車メーカーには、初めての日本グランプリレースに参加しようという、むんむんとするような熱気があった。
私は偶然、1962年に東京モーターショーで式場壮吉氏、徳大寺有恒氏、角田昌巳氏らと知り合い、それまで二輪のレースしか知らなかったのが、四輪のモータースポーツを知り、将来はレーシングドライバーになると心に決めたばかりだった。クルマに詳しいわけではなかったが、ポルシェが高性能だと知っていたのでこのクルマを基準に探し、結局DKWに(金額的に)落ち着いた経緯がある。つまり国産車は選択肢に入ってなかった。
すべてが手探りだった第1回 日本グランプリ
第1回 日本グランプリには、ヨーロッパから来た本格的なレーシングマシンや、国内外のスポーツカー、そしてツーリングカーなどが出場。海外から招聘(しょうへい)したレーシングマシンで競われる2500cc以上のスポーツカークラスをはじめ、1301~2500ccのスポーツカーのクラス、軽自動車のクラス、私が走った701~1000ccクラスなど、11ものクラスによる多彩なレースが行われた。
タイヤは急きょ、ダンロップがバイアスタイヤ「ダンセーフ」の幅を広げたレーシングタイヤを提供した。今でいうラジアルくらいの幅広のもの。一応、体裁は整っていた。
マシンのチューニングはさまざまだった。無改造に近いレースカーで参戦するプライベーターや、ワークスでもプリンスは自工会(日本自動車工業会)の申し合わせを正直に守り、ほとんどノーマルの「スカイライン スポーツ」で参加した。一方、低い車高の「クラウン」やパブリカを投入したトヨタなどは、レースカーに大幅なチューニングを施していた。このように各社の姿勢には大きな差があった。何しろモータースポーツは初めてで、未知の領域だったからだ。
1301~2500ccのスポーツカーレースでは、ノーマルとはいえトライアンフの「TR4」が最有力候補だった。しかし、低い車高に軽量化したボディー、アメリカ仕様のツインキャプでレースチューンされた「フェアレディ」が、田原源一郎氏のドライビングで最初からリードし圧勝。スポーツカーは輸入車が勝つと信じていた多くの人たちに衝撃を与えた。前々から海外ラリーに参加し、またアメリカでもレースの経験のある日産ならではのノウハウが生かされたのだ。
気の毒だったのは、ばか正直なプリンス・スカイライン スポーツだ。ミケロッティデザインの華麗なオープンスポーツは自信満々だったが、コーナーでは大きくロールし、あえぐような走りでフェアレディのはるか後塵(こうじん)を拝する7位と10位に低迷した。もっともこの屈辱が、翌年に観衆をアッと驚かせるあの「プリンス・スカイライン2000GT」を生み出す執念につながったのだが……。
マシンといえば、国産車の場合はコラムシフトの3段マニュアルのクルマもあり、またほとんどがドラムブレーキだった。コーナーでは大きくロールし、ブレーキの利きは悪く、すぐにフェード。ブレーキ液も沸騰してふわふわになるなど、基本性能が低かった。何しろ、国産車は高速連続走行の実績が乏しかったのだ。
ドライバーも、一部の二輪出身の選手はサーキットの走りのセオリーを心得ていたものの、私も含め、ほとんどが手探り状態だった。
それでも5月3日、4日の2日間での観客数はなんと23万人。グランドスタンドは超満員で、もちろん各コーナーサイドの赤土のスタンドも満席。憧れのクルマが華やかに走る初めての自動車レースにワクワクしながら見入っていた。
このように、国産マシンとドライバーたちは、まだつたないながらも、強烈な熱気の中でモータースポーツの世界に突き進み始めたのだ。
【編集協力・素材提供】
(株)webCG http://www.webcg.net/
[ガズ―編集部]
連載コラム
最新ニュース
-

-
車中泊を快適に! ランドクルーザー250 用ベッドキット登場
2024.04.19
-

-
トヨタ カムリ 新型、全車ハイブリッドに
2024.04.19
-

-
シトロエンの新デザイン採用、『C3エアクロス』新型を欧州発表
2024.04.19
-

-
トヨタ ランドクルーザー250 をモデリスタがカスタム…都会派もアウトドア派も
2024.04.19
-

-
マツダ、新型3列シートSUV『CX-80』をついに世界初公開 日本導入時期は
2024.04.19
-

-
アウディ Q8、e-tron史上最長の一充電航続距離619kmを実現…オプションパッケージ発売
2024.04.18
-

-
アルファロメオ『ジュニア』がミラノ・デザインウィーク2024に登場
2024.04.18