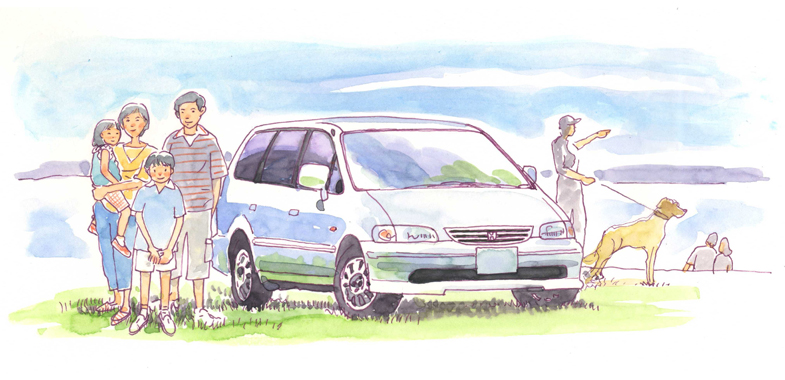ミニバン文化の発展(1994年)
よくわかる 自動車歴史館 第17話
5代目オデッセイの変貌
2013年、ホンダ・オデッセイはフルモデルチェンジを受けて5代目となった。1994年の初登場以来維持してきた4枚ヒンジドアを廃止し、左右のリアドアはスライド式になった。タワーパーキングに入る低い全高にも見切りをつけ、外観は他社の売れ筋ミニバンと変わらなくなった。消費者がミニバンに求める要素は、20年足らずの間に一変していたのだ。
ミニバンとは、小さいサイズのバンを意味する。バンは、貨物車から主に乗客を乗せるMPV(マルチ・パーパス・ヴィークル)までを含む広い概念だ。アメリカでフルサイズのバンといえば、全長5メートル以上、全幅と全高は2メートルに達する巨大な箱型のクルマである。だから、ミニバンといっても日本の感覚では相当に大きい。代表的な車種であるダッジ・キャラバンやシボレー・アストロは、日本の道では持て余すサイズだ。
70年代までの日本では、後ろに荷室のついたクルマをライトバンと呼ぶのが普通だった。あくまで商用車であり、レジャーを楽しむためのワゴンという概念はほとんど知られていなかった。1982年に発売された日産プレーリーは日本型ミニバンの始祖と考えられているが、当時のキャッチコピーは“びっくり BOXY SEDAN”だった。耳慣れないミニバンなどという言葉を使っても消費者に伝わらないことは明らかだったので、苦心してひねり出した表現だったのだろう。
苦肉の策で生まれた低車高
トヨタ・タウンエース、三菱デリカワゴンなど、キャブオーバー型のワンボックスカーは以前から存在していた。ただ、それらのモデルは商用車がベースであり、乗り心地や高級感の面ではセダンとは大きな差があった。1990年、トヨタがエスティマを発売し、マツダは北米向けに生産していたMPVを国内でも販売開始する。3列シートの広いスペースを生かしたファミリーカーが、ようやく評価を高めてきた。
その頃のホンダは、売れ筋となりつつあったSUVやミニバンをラインナップに持っていなかった。以前から生産していたセダンやクーペは、次第に売れ行きを落としていた時期である。救世主のように現れたのが、オデッセイだった。大きな期待を背負って登場したわけではない。発売当初の月間販売目標台数は4000台にすぎなかった。しかし、すぐに生産計画を見直してラインを増強する必要に迫られることになる。
ベースとなったのは、アコードのプラットフォームである。新たに一から設計を始める余裕は、時間的にも資金的にもなかった。生産ラインもアコードと同じものを使うので、サイズに制約が生じる。低く構えたフォルムやヒンジドアは、苦肉の策で生じたものだったのだ。背が高くてドアがスライドするという“ミニバンらしさ”を欠いたことで、商品力が低いとみなされたのは仕方がない。しかし、そのことがむしろヒットの要因になったのである。
ミニバンが登場して間もない頃で、乗用車感覚を求めるユーザーはまだまだ多かった。長年セダンに乗ってきたドライバーにとって、高い重心でコーナリング時にふらつくのは大きな不安となった。オデッセイは、運転席に座っている限りミニバンであることを意識しないですんだのである。低床なので乗降しやすく、天井が低くても十分なスペースを確保できた。コラムシフトを採用したことで、前席から後席へのウォークスルーも可能になっていた。ミニバンの利点を享受しながら、従来の運転感覚をそのまま保持していられる。過渡期のモデルとしては、理想的な仕上がりだったのだ。
ホンダはオデッセイを先頭に押し立てて、“クリエイティブ・ムーバー戦略”を展開する。CR-V、ステップワゴン、S-MXをたてつづけに市場に投入し、脱セダンのラインナップを充実させていった。
バリエーションを広げた日本のミニバン
「オデッセイは、会社の方針として開発されていたわけではない。レジェンドのV6エンジンを使ったアメリカンミニバンの研究チームはあったが、資金不足もあって解散してしまう。しかし、チームの一員だった浅木泰昭氏は、その後も勝手にミニバンの開発を続けた。V6担当なのに直4エンジンを使ったわけで、組織上はありえない、おきて破りの行動である。もちろん上司は叱責(しっせき)したが、無理やり中止させなかったところがホンダらしい。
「クビにはならなかったんですよね。黙認というか、つぶし切らないという風土はありますね。まあ、冷や飯は食いましたけど、覚悟の上ですから」
浅木氏はそう語っている。もともとF1のエンジニアだった浅木氏は、レギュレーションの中で最大の成果を求めることを常に要求されていた。オデッセイがさまざまな制約を背負っていたことも、あるいは発奮材料になったのかもしれない。
“ホンダはスポーツカーを諦め、ミニバンメーカーになってしまった”
そんなふうに言われた時期もあった。しかし、ミニバンという新たな世界を切り開くのは、ホンダにとってスポーツカーと同様のエキサイティングな挑戦だったのだ。
オデッセイのヒット以降、日本のミニバンはバリエーションを広げ、独特の進化をたどっていく。2000年にホンダは5ナンバー枠に収まるストリームを発売し、コンパクトサイズの7人乗りミニバンという新たなジャンルを作り出した。トヨタのタウンエース・ノアはFFの新シャシーを得てノア/ヴォクシーに生まれ変わり、良質な乗り心地と運動性能を手に入れた。日産エルグランド、トヨタ・アルファードといった大きくて豪華な上級ミニバンも人気を博す。
軽自動車の世界でもスズキ・ワゴンRやダイハツ・ムーヴなどのハイトワゴンが主流となり、ミニ・ミニバンともいうべきジャンルを作り出した。日本のファミリーカーの主流はミニバンとなり、セダンの運転感覚を基準にする必要は失われた。広さと便利さに慣れたユーザーは、もう元には戻れない。
この20年の間に自動車の技術は飛躍的な発展を遂げ、背の高いミニバンでも驚くほどスポーティーな運動性能をもつようになった。もう、過渡期のミニバンは役割を終えたのかもしれない。それでも、日本のミニバン文化の発展と隆盛の発火点となったのは、間違いなくオデッセイだったのだ。
1994年の出来事
topics 1
光岡がゼロワンを発表
富山県の自動車ディーラーだった光岡が自動車開発部門を発足させたのは1979年のことだった。原付き免許で運転できるBUBUシャトルを皮切りに、他社製のクルマをベースにしたクラシックカーのレプリカモデルなどを生産・販売していた。
1994年に発売したのが、ロータスセブンを模したゼロワンである。形はクラシックだがユーノス・ロードスターのエンジンを搭載して信頼性を確保し、内装も乗用車ライクな快適仕様だった。このモデルが1996年に運輸省から型式認定を受け、光岡は晴れて自動車メーカーとして認められることになった。
2001年には初めて東京モーターショーに参加し、スーパーカー然としたフォルムのオロチを出品した。最初はホンダNSXをベースにしていたが、市販するときには自社製のシャシーを採用している。ほかにマーチベースのビュート、ティアナベースのガリューなどを販売している。
topics 2
“音速の貴公子”セナ事故死
ホンダの活躍で、1980年代に日本ではF1が大人気となった。中でも一番のスターとなったのが、ブラジル人ドライバーのアイルトン・セナである。哀愁を帯びた表情で女性からも人気となり、“音速の貴公子”の名で呼ばれるようになった。命名したのは、絶叫中継をしていた古舘伊知郎である。
顔立ちとは裏腹にドライビングスタイルは攻撃的で、プロストやマンセルなどのライバルたちと激しい戦いを繰り広げた。ホンダがF1から撤退し、セナは1994年シーズンからウィリアムズ・ルノーに移籍する。
調子が上がらないまま迎えた第3戦のサンマリノグランプリで悲劇が起きた。ポールポジションからスタートした7周目、時速312kmでタンブレロコーナーを直進し、コンクリートウォールに激突した。ヘリコプターで病院に運ばれたが、約4時間後に死亡が確認された。事故原因は、今もはっきりとはわかっていない。
topics 3
「自社さ」連立村山政権発足
1993年に8党連立の細川護煕政権が成立し、自由民主党は1955年以来維持してきた政権を手放すことになった。しかし寄り合い所帯の内閣は結束を保つことができず、自滅する形で退陣に追い込まれる。1年足らずの短命政権だった。
跡を継いだ羽田孜内閣は、さらに短い64日間しか続かなかった。政権を取り戻したい自民党は55年体制下で対立関係にあった日本社会党と組み、首班に社会党委員長の村山富市を担ぐという奇策に出た。社会党と新党さきがけの政策合意に自民党が乗る形だった。
第一党の自民党が第二党の社会党をサポートするという変則的な政権運営で、次第に不協和音が高まっていった。1996年に村山首相が退陣して橋本龍太郎内閣が発足し、自民党政権が復活した。
【編集協力・素材提供】
(株)webCG http://www.webcg.net/
[ガズー編集部]