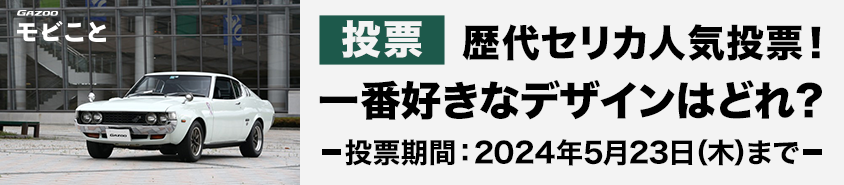鈴鹿サーキット小史(前編)
「あれ」があったから、「今」がある。半世紀以上も前の1962年の秋にこけら落としとして二輪の全日本選手権が開催されたのに続き、1963年の5月に行われた第1回日本グランプリは、僕たちクルマ好きにとって“黒船の来航”だった。ペチャッと低いロータス23や、英国流バックヤードスペシャルの見本みたいなマーコスGT、華やかなフェラーリ250SWB、ごう音をまき散らすアストンマーティンDB4 ザガート、ヘアピンで派手なオーバーステアを演ずるポルシェ・カレラ2などを本当に見られるなんて、それまでは夢のまた夢でしかなかった。国内メーカーもこぞって参戦し、早くも翌年(第2回GP)には本格的なワークスチームが勢ぞろいした。中でもスカGの存在が際立っていた。4気筒スカイラインの鼻先を延ばしてグロリアの6気筒を詰め込んだ怪物は、今に至るGT-R狂騒曲の発端となる。そしてホンダも、ここで大きな転換点を駆け抜けた。通産省の業界再編策を先読みし、二輪メーカーから四輪へと、大胆に踏み込んだ時期だったのだ。こんな鈴鹿を舞台として、日本の近代モータースポーツは産声を上げた。
-

- 1964年に開催された第2回日本グランプリにて、ポルシェ904を追いかけるプリンス・スカイラインGT。
あのころ、ホンダ(本田技研工業)の創業者・本田宗一郎社長は、あらゆる既成概念と全力で戦っていた。すでに1950年代からマン島TTなど国際的な二輪レースで活躍していたが、「急速に成長した技術を世界に認めさせるには、レースで勝つしかない。そのためには国内にもサーキットを作らねば」が持論だった。そこで候補地に選ばれたのが、新たに建設した鈴鹿製作所に近い緩やかな丘陵地帯だった。尊い稲作のための水田をつぶさないようにと考えたからだが、鈴鹿サーキットが屈曲と勾配に富んでいるのは、この地形による。
社内案が二転三転した後、オランダのザントフールト運営などで経験豊富なジョン・フーゲンホルツが招聘(しょうへい)され、最終的に山肌をくねくね縫う、東西に細長いレイアウトになった。一周の途中に立体交差を設けた8の字形は、当初の社内案から受け継がれた。「これだと、左右のタイヤが同じように減るからね」とフーゲンホルツも同意したのだが、F1が走れるコースで立体交差があるのは、鈴鹿とフィオラーノ(フェラーリの社内テストコース)だけという特徴的なサーキットになった。
-

- 1962年、完成間近の鈴鹿サーキット。
このように誕生の経緯がヨーロッパ的だったことと、幕開けのレースで輝いたスターがヨーロッパ車だったことから、鈴鹿ではヨーロッパ流のイベントが主流になり、それがやがて1987年のF1日本GP開催へとつながることになる。その過程ではさまざまな改修も施されたが、テクニックの限りを尽くして攻めることを要求する難攻不落の性格は守り通され、来日したF1ドライバーの多くが「世界で最も走りがいのあるサーキット」と褒めそやしている。もちろんホンダF1の多くも鈴鹿でのテストで育てられ、やがて世界を制した。僕たちアマチュアも、年に一度は鈴鹿を走らないと、なんとなく聖地詣でをサボったような気がしたものだ。
-

- 1987年に鈴鹿で初めて開催されたF1日本グランプリの様子。フェラーリをドライブするゲルハルト・ベルガーが、鈴鹿で初のF1ウィナーとなった。
(文=熊倉重春)
【編集協力・素材提供】
(株)webCG http://www.webcg.net/
[ガズ―編集部]
連載コラム
最新ニュース
-

-
円安、コスト上昇の影響はミニカーの世界にも 注目は「レジン」…第62回 静岡ホビーショー
2024.05.10
-
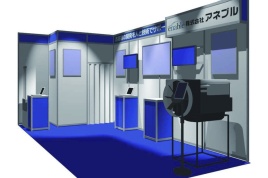
-
アネブルが水素エンジンモデルを「人とくるまのテクノロジー展 2024」に展示へ
2024.05.10
-

-
ディフェンダー に2025年型、マイルドハイブリッドディーゼルを350馬力に強化
2024.05.10
-

-
【ホンダ フリード 新型】「ちょうどいい」使い勝手と見た目をさらにアゲる、純正アクセサリー公開
2024.05.10
-

-
【ホンダ フリード 新型】「フリードらしいデザイン」とは? 新型で実現したデザイナーたちの挑戦
2024.05.10
-

-
レクサスのミニバン『LM』に6座仕様、価格は1500万円
2024.05.10
-

-
【ホンダ フリード 新型】「“ちょうどいい”と言葉でいうのは簡単」それでも目指した唯一無二の価値とは
2024.05.09
最新ニュース
-

-
円安、コスト上昇の影響はミニカーの世界にも 注目は「レジン」…第62回 静岡ホビーショー
2024.05.10
-
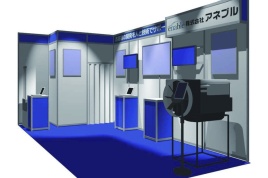
-
アネブルが水素エンジンモデルを「人とくるまのテクノロジー展 2024」に展示へ
2024.05.10
-

-
ディフェンダー に2025年型、マイルドハイブリッドディーゼルを350馬力に強化
2024.05.10
-

-
【ホンダ フリード 新型】「ちょうどいい」使い勝手と見た目をさらにアゲる、純正アクセサリー公開
2024.05.10
-

-
【ホンダ フリード 新型】「フリードらしいデザイン」とは? 新型で実現したデザイナーたちの挑戦
2024.05.10
-

-
レクサスのミニバン『LM』に6座仕様、価格は1500万円
2024.05.10