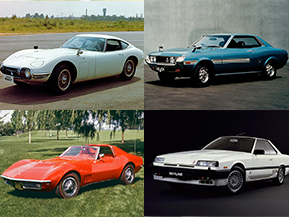【連載全9話】第1話 トヨタ・クラウン・・・スーパーチャージャー付きの日本車特集
“過給エンジン”といえば、今の主流はターボエンジン。そして、クルマの内燃機関からさらなるパワーを引き出すアイテムとしてもうひとつ挙げられるのが、スーパーチャージャーです。今回は、その搭載車として知られる日本車を紹介します。
トヨタ・クラウン
内燃機関でより高い燃焼エネルギーを得るため、燃焼室に大気圧以上の圧力で空気を送り込む過給器。自動車用としては、大別してエンジンの出力で駆動する機械式過給器(スーパーチャージャー)と排気圧を利用する排気タービン式過給器(ターボチャージャー)がある。先に登場したのはスーパーチャージャーで、1920年代に実用化され、戦前はレーシングカーや高性能車、高級車に多く採用されていた。
戦後は自然吸気エンジンの性能向上などによって、スーパーチャージャーはいったん姿を消し、その間に自動車用過給器は1960年代に登場したターボチャージャーに取って代わられた感があった。しかし、ある程度エンジン回転数が上がらないと過給せず、利き始めるまでにタイムラグがあるターボに対して、低回転域からすばやく反応するスーパーチャージャーの特性が見直され、1980年代から再び導入する車種が現れた。
日本車に初採用されたのは1985年。車種は1983年に「いつかはクラウン」という傑作コピーを掲げて登場した7代目トヨタ・クラウンである。当時の税制では“排気量2リッター以上”に高額な税金がかけられていたため、クラウンにはそれまで、基本設計を1960年代にさかのぼる2リッター直6 SOHCのM型をベースとするターボエンジン搭載車が設定されていた。これに代わるパワーユニットとして、新世代の高性能エンジンである2リッター直6 DOHC 24バルブの1G-GEU型にスーパーチャージャーを装着したのである。
ルーツ式と呼ばれる、自動車用としては一般的な機構のスーパーチャージャーを備えた1G-GZEU型の最高出力と最大トルクは、ベースユニットの140PS/6400rpm、16.5kgf・m/4600rpmから160PS/6000rpm、21.0kgf・m/4000rpmへと向上。また出力、トルクともに発生回転数が自然吸気版より下がって中低速型となった。
戦前のクルマのような常時過給ではなく、電磁クラッチにより加速時や高負荷時のみにスーパーチャージャーが作動して効率を高め、また駆動方式もギアからベルトに代えて騒音の問題も解決した1G-GZEU型。自動車専門誌の試乗インプレッションでは、幅広い回転域でタイムラグなしに作動してトルクを補い、自然吸気版に比べはるかに活発にクラウンを走らせ、燃費も従来のターボユニットよりは良好と、おおむね高評価が与えられた。
このスーパーチャージドユニットは1987年にフルモデルチェンジした8代目クラウンにも継続され、また改良型が1988年に登場したX80系マークII、チェイサー、クレスタの3兄弟にも搭載された。
[GAZOO編集部]
【連載全9話】スーパーチャージャー付きの日本車特集
-

-
【連載全9話】第9話 日産・ノート・・・スーパーチャージャー付きの日本車特集
2025.05.07 特集
-

-
【連載全9話】第8話 トヨタ・エスティマ・・・スーパーチャージャー付きの日本車特集
2025.04.30 特集
-

-
【連載全9話】第7話 ユーノス800・・・スーパーチャージャー付きの日本車特集
2025.04.23 特集
-

-
【連載全9話】第6話 スバル・ヴィヴィオ・・・スーパーチャージャー付きの日本車特集
2025.04.16 特集
-

-
【連載全9話】第5話 日産マーチ スーパーターボ・・・スーパーチャージャー付きの日本車特集
2025.04.09 特集
-

-
【連載全9話】第4話 トヨタ・カローラ レビンGT-Z/スプリンター トレノGT-Z・・・スーパーチャージャー付きの日本車特集
2025.04.02 特集
-

-
【連載全9話】第3話 三菱デボネアV・・・スーパーチャージャー付きの日本車特集
2025.03.26 特集
-

-
【連載全9話】第2話 トヨタMR2・・・スーパーチャージャー付きの日本車特集
2025.03.19 特集
-

-
【連載全9話】第1話 トヨタ・クラウン・・・スーパーチャージャー付きの日本車特集
2025.03.12 特集