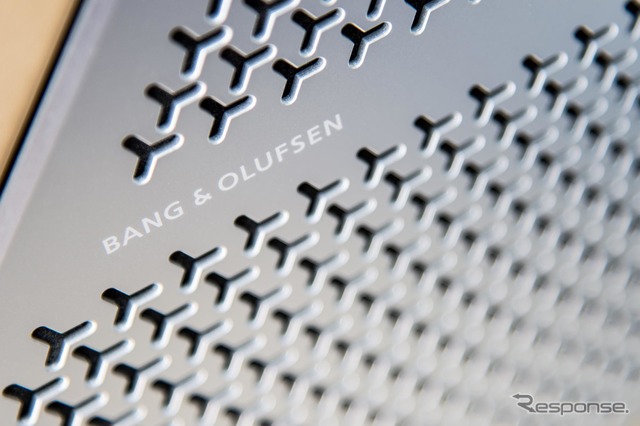【ランボルギーニ ウルス 海外試乗】本物のパフォーマンスを有している、その事実に価値がある…西川淳
『ウルス』という名前は、英語でいうところの「オーロックス」で、家畜牛の先祖にあたる野生牛を指している。そのオーロックスの血脈に、歴代ランボルギーニがその名を拝借してきた闘牛たち、例えば『ウラカン』や『アヴェンタドール』も連なっているのだ。その寓意は、“ウルスはスーパースポーツの母”、というのは深読みし過ぎだろうか?
ウルスを生産することで、2倍の会社規模になったランボルギーニ。当然、その利益はまだ見ぬ未来のスーパースポーツへと還元されるだろう。そう、ポルシェがそうであったように。
ランボルギーニ初のSUV、などというと『LM002』があったじゃないか、とマニアには叱られそうだ。とはいえ、LM002は生産台数もごくわずか(およそ170台)で、カウンタック用の12気筒エンジンを積んだ超マニアックモデル。日本にもけっこうな数が輸入されたはずだが、昨今の相場急上昇(数年で3倍以上の3000万円超級に)で海外流出した個体も多い。一度でも乗ったことのある人なら、“SUV”などと気軽に呼んでいいクルマではないと知っているはず。ここでは、過去にもランボルギーニを名乗った背の高いモデルがあった、という程度に留めておこう。
◆初のSUVで、初の市販ターボカー
ランボルギーニにとってウルスは、初の市販ターボカーだ。4リットルV8ツインターボ+8AT+トルセン式フルタイム4WDというパワートレーンは、VWアウディグループとの共同開発品である。要するに、『トゥアレグ』や『Q7』の上に位置する高性能SUV群、ポルシェ『カイエン』やベントレー『ベンテイガ』と同じグループ。最高出力は、その高性能SUVグループのなかでも最高値の650psで、0-100km/h加速が3.6秒、最高速度は305km/h、というから、数字を見るかぎりカイエンターボやベンテイガを上回る、正に背が高いスーパーカー、だ。
4WDシステムのトルク配分は、お馴染みの前40:後60で、走行環境に応じてフロントへ最大70%、リアへ最大87%のトルクを振り分ける。巨大なSUVを意のままに操るべく、リアステアシステムやアクティヴトルクベクタリングも備えた。
最も注目すべき装備は、センターコンソール上に取って付けてきたように目立って配置されている、操縦桿のようなタンブーロだ。ドライブモード(パワートレーン、ステアリング、サスペンションのセッティングバランス)を各種選ぶことができ、強力なパワートレーンと最新の車体制御システムを路面環境や走行場所に応じて最適にセッティングできる。
ちなみに余談だが、当初の提案では、これほど大きな操縦桿デザインではなく、オーソドックスにボタンかモニター上で選択する方式だったが、エンジニアリング部門トップのマウリツィオ・レッジャーニ以下、エンジニアたちの切実な希望で、確実な操作フィールの得られるレバー方式になったのだという。ちなみに、モニター上での操作もできるようにはなっている。
ドライバー側のレバーを使って、ストラーダ(ノーマル)・スポーツ・コルサ(サーキット)といったお馴染みの3モードに、テッラ(グラベル)・ネーヴェ(スノー)・サッビア(デザート)という新たな3つのモードを加えた計6モードのなかから、走行環境に応じて好みのセッティングを選ぶ。レバーを下げると、ストラーダから順にスポーツ、コルサと一方通行に変わっていく。長押しでデフォルトのストラーダに戻るが、レバーで、たとえばいきなりテッラを選ぶことはできない。レバー操作が面倒な向き用にモニター上のタッチスイッチもあり、それを使えば一発で好みのモードを選ぶことも可能だ。システム的には、カイエンやベンテイガと同じロジックだろう。ちなみに、助手席側のレバーは、インディヴィジュアル=お好みセッティング用となる。
◆新しい世界観を示した走り
ウルス国際試乗会はローマ近郊のヴァッレルンガ・サーキットで開催された。サーキット試乗(22インチ+カーボンパッケージ)はもちろんのこと、オンロード試乗(23インチ)とオフロード試乗(21インチ+オフロードパッケージ)も行なった。
まずは、一周4.1kmのサーキットへ。SUVとはいえ、モダン・ランボルギーニの要点はスタイルとダイナミック性能にある。デザインの判断は皆さんにお任せるとして、気になるのはやはりその走りだ。
勢いよくコースへと飛び出た瞬間、クルマの軽さを実感した。ハンドルを左右に振った際の、ノーズの動きがとてもピュアで、車体の大きさをまったくと言っていいほど感じさせない。動きも敏しょうだ。右アシの裏には常に力強さがみなぎっていて、踏むたびに腰のあたりが軽くなる感覚がある。
プロドライバーの先導で、徐々にスピードアップ。視線が高く、見晴らしが効くから、コーナーへの進入口も広く遠くまで見渡すことができる。つまり、狙ったとおりのラインをトレースしやすい。
パドルシフトで変速するマニュアルモードで踏みこんでしまうと、回転計の針はあっという間にレッドゾーンへ突入し、何度も燃料カットが効いてしまった。そのたびに先行車両との距離が広がる。日産『GT-R』のときのように、早め早めにシフトアップした方が、タイムロスは少ない。
しばらくスポーツモードで走ってみたが、ウラカンなどに比べて意のままに動かせていないという感覚があった。試しにコルサモードに換えてみれば、断然、楽しめた。この手の巨体で攻めるにはニュートラルステア傾向に制御してもらうほうが適しているのだろう。タイトベントでは面白いように内を向き、高速コーナーでは超安定志向でノーズを固定するのだけれど、その間、姿勢はとにかくフラットを保ち、巨体をむやみに感じさせることなく、安心して攻めこんでいけた。
もっとも、ブレーキはさすがに辛い。巨大なコンポジットブレーキを標準で装備するものの、後半にテクニカルパートの多いサーキットを2、3周もがむしゃらに攻め込めこめば、ロードカー用ブレーキではもたない。むしろ、2トンオーバーのクルマであったことを思えば、それでも優秀だったというべきだ。
SUVにしては、サーキットをよくこなし、とてつもなく速かった。優秀な制御のおかげで、サーキットでのドライブフィールはかなり洗練された部類だ。そのためか、スリルに満ちたドライブとは言えなかったのも事実だ。冷静に、汗ひとつかかずに、攻め込めた。その良し悪しは、判断の分かれるところ。否、ウルスは、刺激的なスーパースポーツではない。SUVなのだから、それで当たり前という、ランボにとっては新しい世界観を示したということかもしれない。
◆スーパーカーの真髄とは
サーキットを終えて、ランチの前に一般道テストへ向かう。ヴァッレルンガ・サーキットの近くにある大きな湖を周回するコース。広めのカントリーロードと街中の狭い道が交互に現れる。乗用テストにはもってこい。
そこでのウルスは、最高の“乗用車”となった。乗り心地は、ちょっと昔の欧州車のように、ややソリッドさが優るもので、23インチのスペシャルタイヤでも不快な突き上げなどはなく、ここでも常にフラットライドを保つ。足元でタイヤが常によく動いているが、ボディが不快に揺れたりはしない。ボディが強いのだ。
意のままに、かつ、クリーンに動く鼻先の動きもお見事。クルマの先端までドライバーの意思が伝わっているかのようで、これもまたクルマの大きさを不用意に感じさせない要因だ。知らぬ間に、ランボルギーニをドライブしているということさえ忘れてしまい、鼻歌まじりで転がしている自分に気づいて、失笑してしまった。日常遣いには、不満がない。
ではいったい、ランボらしさはどこにあるのだろうか。ちょっと前が空いた頃合いを見計い、フルスロットルを試す。
その加速のすさまじさこそが、ランボルギーニだ。加速の最中は、車体がふわっと浮いているような感覚で、まるで重量の一部を喪失してしまったかのよう。これはスリリング。サーキットのような広がった空間ではさほど大きく聞こえてこなかったサウンドも、一般道ではなかなかにけたたましい。
ランチののち、特設のオフロードコースでもウルスを試す。タンブーロは、テッラ(=グラベル)モード。砂利と砂でとても滑り易い路面が、ミニサーキットのようになっていた。ベンテイガを砂漠や氷上で試したときもそうだったが、トラクション制御のすさまじさには驚くほかない。強大なトルクを、自信をもって存分に使っていける。左右輪のあいだでデカップリング可能なアクティブアンチロールバーの恩恵で、凸凹が続いても、またもやフラットライドを保とうとするから、視線は常に安定し、道が荒れていても運転しやすいのだ。
とはいえ、調子に乗って踏みすぎると、とたんに物理的な重さが制御を超えてしまう。丁寧な右アシの所作を心がけ、4輪スライドコントロールを楽しみながら連続するコーナーを脱出する楽しさに比べたら、サーキットでのウルスなんて、ただ速いだけのクルマだと思ったほど。
ウルスを買ってオフロードを楽しむなんて人は、中東の石油王くらいのもので、少ないことだろう。けれども、それは、アヴェンタドールやウラカンを買って、積極的にサーキットに行く人がさほど多くないことと同じだ。本物のパフォーマンスを有しているという事実に価値がある。だからこそ、ゆっくりと街中を転がしていても、格好いい。それがスーパーカーの真髄。普段遣いの乗用車としても使えるウルスだからこそ、オンでもオフでも、第一級の性能を備える必要があったというわけだ。
西川淳|自動車ライター/編集者
産業から経済、歴史、文化、工学まで俯瞰して自動車を眺めることを理想とする。高額車、スポーツカー、輸入車、クラシックカーといった趣味の領域が得意。中古車事情にも通じる。永遠のスーパーカー少年。自動車における趣味と実用の建設的な分離と両立が最近のテーマ。精密機械工学部出身。
(レスポンス 西川淳)
ウルスを生産することで、2倍の会社規模になったランボルギーニ。当然、その利益はまだ見ぬ未来のスーパースポーツへと還元されるだろう。そう、ポルシェがそうであったように。
ランボルギーニ初のSUV、などというと『LM002』があったじゃないか、とマニアには叱られそうだ。とはいえ、LM002は生産台数もごくわずか(およそ170台)で、カウンタック用の12気筒エンジンを積んだ超マニアックモデル。日本にもけっこうな数が輸入されたはずだが、昨今の相場急上昇(数年で3倍以上の3000万円超級に)で海外流出した個体も多い。一度でも乗ったことのある人なら、“SUV”などと気軽に呼んでいいクルマではないと知っているはず。ここでは、過去にもランボルギーニを名乗った背の高いモデルがあった、という程度に留めておこう。
◆初のSUVで、初の市販ターボカー
ランボルギーニにとってウルスは、初の市販ターボカーだ。4リットルV8ツインターボ+8AT+トルセン式フルタイム4WDというパワートレーンは、VWアウディグループとの共同開発品である。要するに、『トゥアレグ』や『Q7』の上に位置する高性能SUV群、ポルシェ『カイエン』やベントレー『ベンテイガ』と同じグループ。最高出力は、その高性能SUVグループのなかでも最高値の650psで、0-100km/h加速が3.6秒、最高速度は305km/h、というから、数字を見るかぎりカイエンターボやベンテイガを上回る、正に背が高いスーパーカー、だ。
4WDシステムのトルク配分は、お馴染みの前40:後60で、走行環境に応じてフロントへ最大70%、リアへ最大87%のトルクを振り分ける。巨大なSUVを意のままに操るべく、リアステアシステムやアクティヴトルクベクタリングも備えた。
最も注目すべき装備は、センターコンソール上に取って付けてきたように目立って配置されている、操縦桿のようなタンブーロだ。ドライブモード(パワートレーン、ステアリング、サスペンションのセッティングバランス)を各種選ぶことができ、強力なパワートレーンと最新の車体制御システムを路面環境や走行場所に応じて最適にセッティングできる。
ちなみに余談だが、当初の提案では、これほど大きな操縦桿デザインではなく、オーソドックスにボタンかモニター上で選択する方式だったが、エンジニアリング部門トップのマウリツィオ・レッジャーニ以下、エンジニアたちの切実な希望で、確実な操作フィールの得られるレバー方式になったのだという。ちなみに、モニター上での操作もできるようにはなっている。
ドライバー側のレバーを使って、ストラーダ(ノーマル)・スポーツ・コルサ(サーキット)といったお馴染みの3モードに、テッラ(グラベル)・ネーヴェ(スノー)・サッビア(デザート)という新たな3つのモードを加えた計6モードのなかから、走行環境に応じて好みのセッティングを選ぶ。レバーを下げると、ストラーダから順にスポーツ、コルサと一方通行に変わっていく。長押しでデフォルトのストラーダに戻るが、レバーで、たとえばいきなりテッラを選ぶことはできない。レバー操作が面倒な向き用にモニター上のタッチスイッチもあり、それを使えば一発で好みのモードを選ぶことも可能だ。システム的には、カイエンやベンテイガと同じロジックだろう。ちなみに、助手席側のレバーは、インディヴィジュアル=お好みセッティング用となる。
◆新しい世界観を示した走り
ウルス国際試乗会はローマ近郊のヴァッレルンガ・サーキットで開催された。サーキット試乗(22インチ+カーボンパッケージ)はもちろんのこと、オンロード試乗(23インチ)とオフロード試乗(21インチ+オフロードパッケージ)も行なった。
まずは、一周4.1kmのサーキットへ。SUVとはいえ、モダン・ランボルギーニの要点はスタイルとダイナミック性能にある。デザインの判断は皆さんにお任せるとして、気になるのはやはりその走りだ。
勢いよくコースへと飛び出た瞬間、クルマの軽さを実感した。ハンドルを左右に振った際の、ノーズの動きがとてもピュアで、車体の大きさをまったくと言っていいほど感じさせない。動きも敏しょうだ。右アシの裏には常に力強さがみなぎっていて、踏むたびに腰のあたりが軽くなる感覚がある。
プロドライバーの先導で、徐々にスピードアップ。視線が高く、見晴らしが効くから、コーナーへの進入口も広く遠くまで見渡すことができる。つまり、狙ったとおりのラインをトレースしやすい。
パドルシフトで変速するマニュアルモードで踏みこんでしまうと、回転計の針はあっという間にレッドゾーンへ突入し、何度も燃料カットが効いてしまった。そのたびに先行車両との距離が広がる。日産『GT-R』のときのように、早め早めにシフトアップした方が、タイムロスは少ない。
しばらくスポーツモードで走ってみたが、ウラカンなどに比べて意のままに動かせていないという感覚があった。試しにコルサモードに換えてみれば、断然、楽しめた。この手の巨体で攻めるにはニュートラルステア傾向に制御してもらうほうが適しているのだろう。タイトベントでは面白いように内を向き、高速コーナーでは超安定志向でノーズを固定するのだけれど、その間、姿勢はとにかくフラットを保ち、巨体をむやみに感じさせることなく、安心して攻めこんでいけた。
もっとも、ブレーキはさすがに辛い。巨大なコンポジットブレーキを標準で装備するものの、後半にテクニカルパートの多いサーキットを2、3周もがむしゃらに攻め込めこめば、ロードカー用ブレーキではもたない。むしろ、2トンオーバーのクルマであったことを思えば、それでも優秀だったというべきだ。
SUVにしては、サーキットをよくこなし、とてつもなく速かった。優秀な制御のおかげで、サーキットでのドライブフィールはかなり洗練された部類だ。そのためか、スリルに満ちたドライブとは言えなかったのも事実だ。冷静に、汗ひとつかかずに、攻め込めた。その良し悪しは、判断の分かれるところ。否、ウルスは、刺激的なスーパースポーツではない。SUVなのだから、それで当たり前という、ランボにとっては新しい世界観を示したということかもしれない。
◆スーパーカーの真髄とは
サーキットを終えて、ランチの前に一般道テストへ向かう。ヴァッレルンガ・サーキットの近くにある大きな湖を周回するコース。広めのカントリーロードと街中の狭い道が交互に現れる。乗用テストにはもってこい。
そこでのウルスは、最高の“乗用車”となった。乗り心地は、ちょっと昔の欧州車のように、ややソリッドさが優るもので、23インチのスペシャルタイヤでも不快な突き上げなどはなく、ここでも常にフラットライドを保つ。足元でタイヤが常によく動いているが、ボディが不快に揺れたりはしない。ボディが強いのだ。
意のままに、かつ、クリーンに動く鼻先の動きもお見事。クルマの先端までドライバーの意思が伝わっているかのようで、これもまたクルマの大きさを不用意に感じさせない要因だ。知らぬ間に、ランボルギーニをドライブしているということさえ忘れてしまい、鼻歌まじりで転がしている自分に気づいて、失笑してしまった。日常遣いには、不満がない。
ではいったい、ランボらしさはどこにあるのだろうか。ちょっと前が空いた頃合いを見計い、フルスロットルを試す。
その加速のすさまじさこそが、ランボルギーニだ。加速の最中は、車体がふわっと浮いているような感覚で、まるで重量の一部を喪失してしまったかのよう。これはスリリング。サーキットのような広がった空間ではさほど大きく聞こえてこなかったサウンドも、一般道ではなかなかにけたたましい。
ランチののち、特設のオフロードコースでもウルスを試す。タンブーロは、テッラ(=グラベル)モード。砂利と砂でとても滑り易い路面が、ミニサーキットのようになっていた。ベンテイガを砂漠や氷上で試したときもそうだったが、トラクション制御のすさまじさには驚くほかない。強大なトルクを、自信をもって存分に使っていける。左右輪のあいだでデカップリング可能なアクティブアンチロールバーの恩恵で、凸凹が続いても、またもやフラットライドを保とうとするから、視線は常に安定し、道が荒れていても運転しやすいのだ。
とはいえ、調子に乗って踏みすぎると、とたんに物理的な重さが制御を超えてしまう。丁寧な右アシの所作を心がけ、4輪スライドコントロールを楽しみながら連続するコーナーを脱出する楽しさに比べたら、サーキットでのウルスなんて、ただ速いだけのクルマだと思ったほど。
ウルスを買ってオフロードを楽しむなんて人は、中東の石油王くらいのもので、少ないことだろう。けれども、それは、アヴェンタドールやウラカンを買って、積極的にサーキットに行く人がさほど多くないことと同じだ。本物のパフォーマンスを有しているという事実に価値がある。だからこそ、ゆっくりと街中を転がしていても、格好いい。それがスーパーカーの真髄。普段遣いの乗用車としても使えるウルスだからこそ、オンでもオフでも、第一級の性能を備える必要があったというわけだ。
西川淳|自動車ライター/編集者
産業から経済、歴史、文化、工学まで俯瞰して自動車を眺めることを理想とする。高額車、スポーツカー、輸入車、クラシックカーといった趣味の領域が得意。中古車事情にも通じる。永遠のスーパーカー少年。自動車における趣味と実用の建設的な分離と両立が最近のテーマ。精密機械工学部出身。
(レスポンス 西川淳)
最新ニュース
-

-
ジープ『V6ラングラー』に8速AT復活…米国での人気に応える
2024.12.19
-

-
スバル『フォレスター』新型、米IIHSの最高安全評価「TOP SAFETY PICK+」獲得
2024.12.19
-

-
「ネーミング通りの雰囲気」トヨタの新型電動SUV『アーバンクルーザー』発表に、日本のファンも注目
2024.12.19
-

-
時代は変わった! 24時間営業や純水洗車も、進化するコイン洗車場の全貌~Weeklyメンテナンス~
2024.12.19
-

-
日産、ビームスとコラボした特別な6車種発表…シートカバーに裏返しデニムを再現
2024.12.19
-

-
日本最大級のモータースポーツイベント、2025年3月に横浜で開催へ
2024.12.19
-

-
ポルシェ『マカン』新型、「ユーロNCAP」で最高評価の5つ星を獲得
2024.12.18
最新ニュース
-

-
ジープ『V6ラングラー』に8速AT復活…米国での人気に応える
2024.12.19
-

-
スバル『フォレスター』新型、米IIHSの最高安全評価「TOP SAFETY PICK+」獲得
2024.12.19
-

-
「ネーミング通りの雰囲気」トヨタの新型電動SUV『アーバンクルーザー』発表に、日本のファンも注目
2024.12.19
-

-
時代は変わった! 24時間営業や純水洗車も、進化するコイン洗車場の全貌~Weeklyメンテナンス~
2024.12.19
-

-
日産、ビームスとコラボした特別な6車種発表…シートカバーに裏返しデニムを再現
2024.12.19
-

-
日本最大級のモータースポーツイベント、2025年3月に横浜で開催へ
2024.12.19
MORIZO on the Road