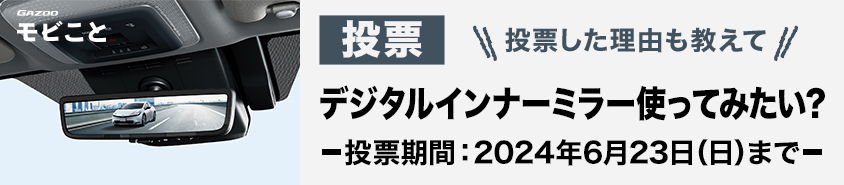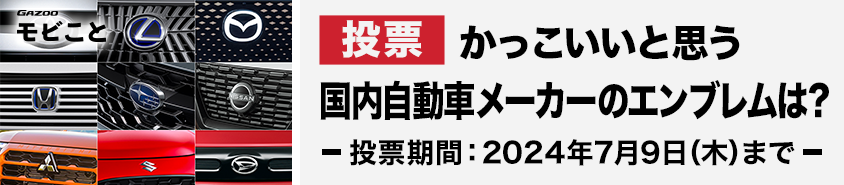ラリーで勝つために生まれ、サスペンションに“技術革新”をもたらし続けるTEIN・・・カスタマイズパーツ誕生秘話③
最も過酷な自動車競技と言われる『ラリー』から生まれ、WRC(世界ラリー選手権)など最高峰のモータースポーツフィールドで活躍を続けてきたサスペンションメーカー『TEIN(テイン)』。
そんな戦場を開発の場として性能を磨き上げられたサスペンションは、スポーツタイプのクルマはもちろんのこと、セダンやミニバン、SUVや4WD問わず、多くの国産車と主要外国車を網羅するラインアップを誇る。
『ドライビングプレジャーを創造する総合サスペンションメーカー』として、乗っていて楽しく、長く乗り続けていても疲れない、愛車が意のままに動くようなサスペンション作りを信条とするテインの誕生から現在までのお話を、創設者のひとりである藤本吉郎氏にインタービュー。サスペンションカスタムをとりまく時代や環境の変化とともに振り返っていく。
TEINのはじまりは『俺達の走りに耐えてくれるショックアブソーバーがない』
-

1995年のサファリラリーで優勝を飾ったドライバーの藤本吉郎氏。写真はその実車をレストアしたセリカ(ST185)
テインの代表取締役社長である市野諮氏と専務取締役の藤本吉郎氏は、1980年代初頭、いすゞワークスチームとしてジェミニ(PF60)でラリーに参戦していた。
「当時は『神奈川を制するものは日本を制する』と言われるほどレベルが高い地区で、TE71やKP61を相手に戦っていたんですが、険しいダートコースを1日中走ると、必ずと言っていいほどサスペンションが壊れてしまうんです。しかし、当時のサスペンションメーカーは純正品を作るのがメインで、競技用にあれこれと細かく意見を聞いて作ってくれるという雰囲気ではなく『それならば自分たちで作ろう!』と考えたのがはじまりでした」
そう話してくれたのは、当時のドライバーであり、現在は専務取締役を務める藤本吉郎氏。
WRCをはじめ、スーパー耐久、ダートトライアル、ドリフトなどさまざまなカテゴリで戦い、その経験を製品へとフィードバックしている
1985年、起業するにあたって社名は自分たちの思いを込めて『TECHNICAL・INNOVATION(テクニカル・イノベーション/技術革新)』の頭文字を合わせ『TEIN』と命名。
「当時、競技車両を後ろから見たときに『黄色はBILSTEIN』『赤はKONI』というようにサスペンションが目立っていたので、ウチは他と被らない色でクリーンなイメージのある『緑色』にしよう!と決めました」とのこと。
現場で鍛え上げられたショックアブソーバーの評判は『群を抜くポテンシャルと耐久性を併せ持つ』と、瞬く間にモータースポーツ界に浸透。そのステージはラリーだけでなく、N1耐久レース(現在のスーパー耐久)でも装着率80%という驚異のシェアを獲得。時を同じくして1987年には2人の念願だった海外の『香港~北京ラリー』に参戦。1989年にはラリーの最高峰である『WRC』にも出場を果たしたのだ。
テイン創業当時の社屋と、レース用としてOEM生産していたショックアブソーバー
「10坪ほどの小さな社屋からスタートした会社でしたが、自分たちで減衰力テスターを作り上げて数値をデータ化したり、最先端の競技車に使われていた減衰力調整機構や別タンク式サスペンションを日本にいち早く持ち込んだりと、今でも社是に掲げている『やればできる』をモットーに取り組んできました。ニードル調整式の減衰力調整機構を日本で市販車用ショックアブソーバーに採用したのは、おそらくウチが最初だったんじゃないかな」と藤本氏。
こうした実戦での経験をフルに生かし、1990年には『TEIN』ブランドとして初のオリジナル製品『TYPE H DAMPER』を発表。その後もさまざまなラインアップを生み出していくことになる。
『サスペンションの交換』が流行した経緯は?
-

車高調整式サスペンションキットには、得意とする走行シチュエーション別に、多くの機種がラインアップされる。 写真は本格スポーツユーザーをターゲットとしたR35用の『SUPER RACING』
元来、サスペンションの改造や社外品への交換は『道路運送車両法』によって規制されており、構造等変更検査などの手続きを行えば一般公道を走ることはできたものの、そのハードルは高く“競技車両のアイテム”というイメージが強かった。
しかし1995年、日米自動車・同部品協議を経て規制緩和が行なわれたことにより、愛車カスタムのハードルはグッと下がった。サスペンションの交換や改造についても、スプリングの遊びがないことや最低地上高9cm以上といった条件に合致していれば車検を取得することができるとあって、全国のクルマ好きたちの間で広まっていったのだ。
こうしてサスペンションの交換が気軽にできるようになると「少し車高を落としてコーナリング時の安定感を高めたい」というようなファミリー層から「ローダウンさせて見た目をカッコよくしたい」といった若者、そしてもちろん「サーキットでのスポーツ走行を楽しみたい」といったスポーツ志向のユーザーまで、そのマーケットは拡大の一途を辿り『サスペンション交換』はクルマ好きにとってスタンダードなカスタムメニューとなっていった。
-

サスペンションの交換は、スポーツ派だけでなくドレスアップを望むユーザーからの支持も得た
「創業当時から『安全な製品を合法的に安心して使っていただきたい』というコンセプトのもと、規制緩和以前は構造変更に必要な書類を添付して販売していました。1995年以降は最低地上高を簡単に確認するための『90mmゲージ』も作りました。取り扱い説明書もできるだけわかりやすいようにイラストを添付するなど、常にユーザー目線で製品作りを行うように心がけています」と藤本氏。
全長調整式車高調が流行しはじめた際にも、サビによる固着を防ぐ防錆剤『ラストプルーフ』を販売したり、SST(塩水噴霧試験)による耐久テストを実施したりと、さまざまな策を講じてユーザーに寄り添った製品開発を実施してきたのだ。
そして同時に、生産ラインの改良や材料の大量に仕入れによってコストを抑えるなど、ハイクオリティはそのままにリーズナブルな価格で製品を提供していく努力も続けてきたという。
『M.S.V.』機構の搭載によって、ダンパーの減衰力性能が飛躍的に向上した。
サスペンションの良し悪しの中核となるのが、ショックアブソーバーの性能である。走行中に車高が上下(ダンパーが伸び/縮み)する際、ダンパーの内部に封入されているオイルが狭い流路を通ることで抵抗となり、上下運動のスピードを抑制、コントロールする。これが『減衰力』と言われるものだ。
しかし、利便性を求めて減衰力の調整幅を大きく取ってしまうと、ステアリングフィールや路面への追従性、トラクションといった面がスポイルしてしまう。そこで、微低速領域での減衰力の落ち込みを防ぐために「M.S.V.(マイクロスピードバルブ)」機構を開発。オイルの動きを緻密にコントロールすることで、よりリニアなドライビングを可能とした。この機構が市販モデルに搭載され、リリースされたのは2006年のことである。
-

現行型の『EDFC5』はジャーク理論などが採用され、AIも投入。リニアに可変する減衰力で快適なドライブを可能とした。
また、その減衰力を段階的に変更することで乗り心地の良さとスポーティな運動性能を両立する『減衰力調整機構』が普及していく中で、テインが2001年に開発したのが『EDFC』と名付けられたアイテム。
車内に設置したコントローラーによって4本のダンパーの減衰力をスイッチひとつで調整することを可能にし、クルマから一旦降りて各ダンパーをクリックして減衰力を変えるという手間をも無くしてしまったのだ。
さらにそれをベースに数度のモデルチェンジを経て、2023年に登場した『EDFC5』ではAI技術も取り入れられ、よりエルゴノミクス的なシステムへと革新を遂げている。
「1995年の規制緩和でサスペンションカスタムが流行しはじめた頃は『とにかく硬いアシがいい』という声が多かったですが、じょじょに『クルマの動きを抑えてくれて乗り心地もいいアシ』が求められるようになっていきました。そういった声にテインは『EDFC』や『M.S.V.』などの開発によって応えてきました」と藤本氏は振り返る。
ニーズの変化とともに成長し続けるサスペンションの未来
-

製品の精度と耐久性は、実車装着テストだけでなく測定器上でも厳密にテスト&チェックが繰り返される
分散していた生産拠点を、2003年に現在の社屋に統合。生産機械や測定器なども1箇所に集約したとで、開発設計から生産、組み立てまでを妥協なく自社で行う環境を実現。国際規格ISO9001の認証を全事業所で取得するなど、品質管理も万全の体制を誇っているテイン。
アメリカやヨーロッパにも拠点を構える他、現在は中国に生産工場を設け『地産地消』を目指して生産と販売に力を入れているという。
ちなみに中国では電気自動車の足まわりカスタムの需要が高く、その傾向はタイをはじめとするASEAN地域にも広がりを見せているそうだ。
神奈川県横浜市戸塚区にある本社(写真左)と、中国の江蘇省宿遷市にある生産工場(写真右)
もちろん、日本国内においても、クルマの静粛性向上に合わせてアッパーマウントに強化ゴムを採用したり、純正アッパーマウント流用や車高調整機能省略によって価格を抑えたラインアップを追加したりと、時代やニーズに合わせたアップデートを続けているという。
創業時に2人でスタートしたテインは、2023年に社員数400名弱まで成長したという。
「テインは2025年に創立40周年を迎えます。これだけ長くおなじ分野で製品を作り続けていても、まだまだやりたいことはたくさんあるので、これからもサスペンションにこだわり続けて“進化”と“深化”を続けていきたいです」と藤本氏は締めくくってくれた。
-

街中でもワインディングの走行でも意のままに動いてくれるサスペンション
取材協力:テイン
[GAZOO編集部]
カスタマイズパーツ誕生秘話
-

-
仲間を大切にする小倉クラッチが乗りやすさにこだわった強化クラッチブランド『ORC』・・・カスタマイズパーツ誕生秘話
2024.06.14 コラム・エッセイ
-

-
ボディ剛性パーツを身近にしたCUSCOが、多様なパーツを手掛ける理由とは?・・・カスタマイズパーツ誕生秘話
2024.05.28 コラム・エッセイ
-

-
ラリーで勝つために生まれ、サスペンションに“技術革新”をもたらし続けるTEIN・・・カスタマイズパーツ誕生秘話③
2024.05.20 コラム・エッセイ
-

-
長野から世界へ。『ブレーキ強化』を競技車から市販車へと普及させたENDLESS・・・カスタマイズパーツ誕生秘話②
2024.04.29 コラム・エッセイ
-

-
FUJITSUBOがいち早く創りあげた『車検対応マフラー』へのこだわりと匠の技・・・カスタマイズパーツ誕生秘話①
2024.04.18 コラム・エッセイ
連載コラム
最新ニュース
-

-
知っておきたい! ブレーキパッドのメリット・デメリットとカスタマイズ術~カスタムHOW TO~
2024.06.15
-

-
日産『デイズ』と『ルークス』、一部仕様を変更し新色も追加
2024.06.15
-

-
日本発の高性能EV『アウル』、最高速438.7km/hを記録…世界最速の電動ハイパーカーに
2024.06.15
-

-
アルピーヌ初のEV、コンパクトハッチ『A290』発表…220馬力モーター搭載
2024.06.15
-

-
メルセデスベンツ、『EQB』をマイナーチェンジし発売…価格は811万円から
2024.06.14
-

-
ホンダが新型軽商用EV『N-VAN e:』発売…実質的な価格は200万円以下、一充電走行距離245km
2024.06.14
-

-
日産『ノートオーラ』がマイナーチェンジ、90周年記念車と“大人のオーラ”「AUTECH」も新設定
2024.06.14