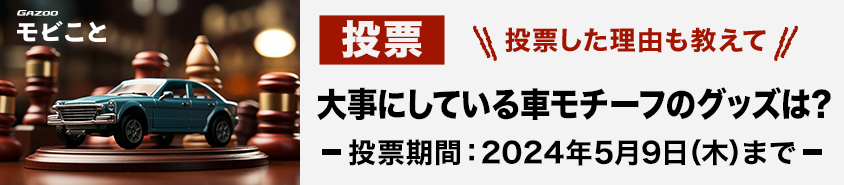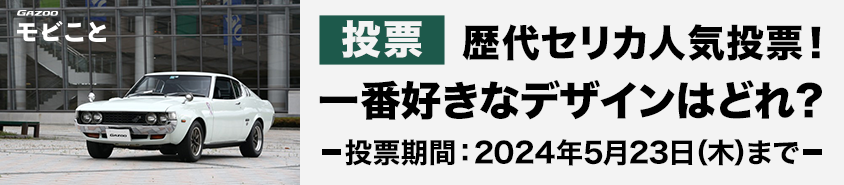日本の自動車史に残るクルマが愛車であることの歓びと誇り。日産・スカイラインGT-R(BNR32型)
スカイラインGT-R。
このクルマが、レースとは切っても切り離せないほど強い結びつきがあることは言うまでもない。1969年〜72年に掛けて「国内レースにおいて通算50勝」という記録を打ち立てたことは、もはや伝説から神話へとなりつつある。
世代によって思い浮かべるモデルは異なるだろうが、クルマを愛する者であれば、「スカイラインGT-R」というキーワードに対して特別な感情を抱く人も多いはずだ。今回、紹介するオーナーも、そんなスカイラインGT-Rに魅せられ、ともに人生を歩んできたと言い切っても過言ではないほど強い思い入れがあるようだ。
「このクルマは、1993年式日産・スカイラインGT-R Vスペック(以下、スカイラインGT-R)です。私が手に入れた時点で7年落ちだったんですが、わずか1.6万キロしか走っていなかったんです。この個体を手に入れてから18年が経ちましたが、オドメーターは現在18万キロを超えたあたりです。NISMO製フルスケールメーターに交換されたことが記録簿にも明記されており、これが実走行です」。
オーナーが所有する「R32 GT-R」が誕生したのは1989年。早いもので、もう30年近くも前なのだ。いわゆる「ハコスカ」・「ケンメリ」と呼ばれるスカイラインGT-Rが途絶えてから16年。ファンが長らく待ち望んだ復活だった。
GT-Rの名を冠した特別なスカイラインである以上、「レースで勝ち続けること」は、このクルマが生まれながらにして背負った宿命だ。このクルマの開発陣は、見事、ファンの期待に応えるクルマを造り上げた。スカイラインGT-Rは、全日本ツーリングカー選手権(グループA)において、1990年から1993年に掛けて参戦したレース26戦で全勝という偉業を成し遂げ、圧倒的な強さを誇った。こうして、スカイラインGT-R伝説に新たな歴史の1ページが加えられたのだ。
スカイラインGT-Rのボディサイズは、全長×全幅×全高:4545x1755x1340mm。「RB26DETT」と呼ばれる、排気量2568cc、直列6気筒DOHCツインターボエンジンの最大出力は280馬力を誇る。さらに、グループAカテゴリーのレギュレーションをクリアしつつ、耐久性とパワーを兼ね備えるべく開発されたレース用エンジンの最大出力は、600馬力に耐えうる性能を持ち合わせていたという。オーナーの個体は、ブレンボ製ブレーキと、前後にBBS製ホイールおよび225/50R17インチサイズのタイヤを装着した「Vスペック」だ。今でこそ珍しくなくなったが、Vスペックが発売された当時は、このサイズのタイヤが純正装着されたことに驚いたものだ(後に、245/45R17インチのタイヤを装着した「VスペックII」へと進化している)。
オーナーが、スカイラインGT-Rというクルマに強く惹かれた理由を尋ねてみた。
「幼い頃、親族の家にスカイライン2000GTがあったんです。それがスカイラインというクルマを知ったきっかけだったように思います。その後、従兄から譲り受けた雑誌に、「ハコスカGT-R」が紹介されている記事を見つけたんです。いろいろと調べていくうちに、少年時代の私でもスカイラインGT-Rが凄いクルマだということが分かってきたんですね。ちょうどその頃、日本はスーパーカーブーム真っ只中。私も、他の子どもたちと同様にランボルギーニ ミウラやカウンタックに魅せられました。しかし、いつしか興味がスカイラインGT-Rに移っていったんです。当時はまだ小学生でしたが、『大人になったらスカイラインGT-Rを買おう』と心に決めていました」。
幼少期に抱いた夢を実現できる人は本当にごくわずかだ。夢を断念することもあるだろうし、興味の対象が変わることも少なくない。しかし、オーナーは違った。
「現在、私は52歳になります。私が社会人になった1989年、つまり20代前半の頃に、BNR32型のスカイラインGT-Rがデビューしたんです。当時、スクープイラストを見たときは半信半疑でしたが、本当に復活を果たして実車を見たとき、一瞬で魅せられたんです。『これは欲しい!』と思いましたね。しかし、社会人1年生に、当時の車輌本体価格445万円は手の届かない存在でした…。そこで、プリンス自動車工業を経て、今はなき日産村山工場に勤めていた私の父が家族用に購入した日産・パルサー(N12型)に乗らせてもらいつつ、必死にお金を貯めたんです」。
その後、貯金に励んだことで、念願のスカイラインGT-Rを購入できたのであろうか?
「いえいえ。もちろんすぐ買えるようなクルマではありませんでした。そこで4ドアのスカイラインGTS-t type-M(R32型)を手に入れたんですが、スカイラインGT-Rが横に並ぶと気になって仕方ないんですね。そのときは既にR33型へとモデルチェンジしていた時期でしたし、4ドアのGT-Rとして販売されたオーテックバージョン(BCNR33型)に乗り換えたんです。足まわりなども交換して自分なりに楽しんでいたんですが、どうにもしっくりこなくて…。改めて、自分はBNR32型スカイラインGT-Rが欲しいんだということを再認識して、程度の良い個体を探すことにしたんです」。
こうして、オーナーがBNR32型スカイラインGT-R購入の意志を固めたときには、既に生産終了となっていた。そんなオーナーに、思わずぐっとくるような情報がもたらされることとなる。
「あるGT-R専門店から『7年落ちのVスペックだけど、ワンオーナー車で距離は1万キロ台、あるショップでエンジンをオーバーホールしてある個体が入庫するかもしれないよ』と連絡をもらったんです。それが現在の愛車です」。
オーナーが手に入れた時点では、どのようなモディファイが施されていたのだろうか?
「前オーナーの方の好みで、NISMO製オイルクーラーおよびフルスケールメーター、マインズ製のコンピューター・フロントパイプ。マフラーに交換されてあったんです。さらにエンジンは、当時N1カテゴリーのレースに参戦していたスカイラインGT-Rのメンテナンスを担当していた『サイマー』というチューニングショップによってオーバーホールされた仕様でした。これらのメニューを購入後に行うとそれなりの費用が掛かります。それに、私が購入した当時は、ノーマルとVスペックの中古車相場がほぼ同じだったんです。私好みの仕様だったこともあり、結果として良い個体に巡り会えたことは幸運でしたね」。
こうして、ついに念願だったBNR32型スカイラインGT-Rを手に入れオーナーとなったことで感じたことはあったのだろうか?
「実は、所有するまでBNR32型スカイラインGT-Rを運転したことがなかったんです。それだけに『ついに一番好きなクルマを手に入れたんだ!』と、喜びを嚙みしめましたよ。私自身、このクルマのスタイルが気に入っているので、購入後に手を加えたのは、フロントバンパーのNISMO製ダクトとブレーキパッドくらいです」。
手に入れてから18年という月日が流れているが、他のクルマに乗り換えようと思ったことはないのだろうか?
「本当に1度もありません(笑)。この型のGT-Rのウィークポイントと呼ばれているようなトラブルを何度も経験しましたが、それでも手放そうと思ったことは1度もなかったですね」。
心底このスカイラインGT-Rに惚れ込んでいるようだが、「NISMOヘリテージパーツ」としてBNR32型スカイラインGT-Rの部品が再生産されたこと、そして現行GT-Rについての思いを伺ってみた。
「部品が再生産されたことは、オーナーとして素直に嬉しいです。あとは、シートベルトまわりの部品も再生産して欲しいですね。この部分が壊れると、保安基準を満たしていないことになり、車検が通らないんです。それから、現行GT-Rについてですが…。個人的にはやはり『スカイラインGT-R』の名を残して欲しかったというのが本音です。輸出仕様は日産GT-Rとして販売し、日本国内はスカイラインGT-Rのままでも良かったのではないかと思います」。
最後に、このスカイラインGT-Rと今後どのように接していきたいと思っているのかを尋ねてみた。
「今までどおり乗り続けます。本当に代わりのクルマが見つからないんですよ。以前、開発陣の方ともお会いする機会がありましたが、改めてこのクルマを世に送り出してくれたことに感謝の気持ちを伝えたいです。そして…、私自身、このクルマのオーナーに相応しい人でありたいです。身体を鍛えることはもちろん、きちんと身なりを整え、格好良く乗りたいですね」。
オーナーは決して多くを語らなかったが、仕事の合間に自然災害のあった被災地などに赴き、ボランティアの一員として参加しているという。また、日本国内の自動車関連イベントのサポートメンバーとして精力的に活動する一面も併せ持っている。その移動の足となっているのが、このスカイラインGT-Rなのだ。このスカイラインGT-Rと過ごした18万キロという距離、そして18年という歳月の何割かが、見知らぬ誰かの幸せのために捧げたものなのかもしれない。
このスカイラインGT-Rは、間違いなく日本の自動車史に残る1台であろう。このクルマと過ごす時間を、惜しげもなく見知らぬ誰かのために費やすことができるオーナーは、このクルマのオーナーに相応しい「ジェントルマンドライバー」だ。それほど誠実なオーナーに溺愛されているこのスカイラインGT-Rは、この上なく幸せな個体といえるだろう。
【撮影地:潮見周辺(東京都江東区)、西新宿周辺(東京都新宿区)、新国立競技場周辺(東京都新宿区/渋谷区)】
(編集: vehiclenaviMAGAZINE編集部 / 撮影: 古宮こうき)
[ガズー編集部]
連載コラム
最新ニュース
-

-
トヨタが新型BEVの『bZ3C』と『bZ3X』を世界初公開
2024.04.25
-

-
メルセデスベンツ GLCクーペ、PHEVモデルを追加…EV走行距離118km
2024.04.25
-

-
中国IT大手のテンセントとトヨタ自動車が戦略提携
2024.04.25
-

-
ホンダが新型EVの『e:NP2』を発売
2024.04.25
-

-
ゲーム内で先行体験! AFEELAプロトタイプがグランツーリスモ7に登場
2024.04.25
-

-
マツダ、電動セダン『EZ-6』世界初公開、24年発売へ SUVコンセプトも…北京モーターショー2024
2024.04.25
-

-
ヒョンデの高性能EV『アイオニック5N』が日本上陸! 特別仕様車の予約開始
2024.04.25