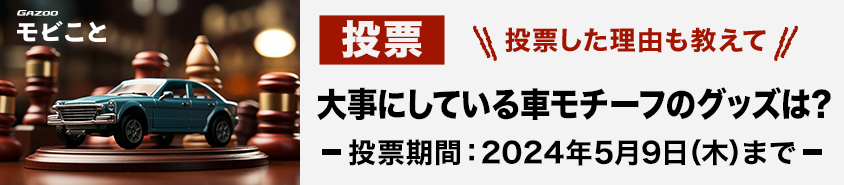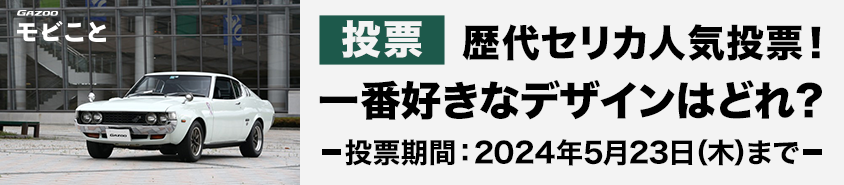自費出版するほどクルマ愛が深い27歳オーナーの愛車は、フルノーマルのトヨタ ソアラ(Z30型)
今回紹介するトヨタ・ソアラ(Z30型、以下ソアラ)の男性オーナーは、現在27歳。愛車は手に入れてから1年3ヶ月が経過している。
「この個体は1999年式の後期型です。『3.0GT Gパッケージ』といって、後期型の中でも最後のマイナーチェンジ時のモデルだけに、もともとの生産台数も少ないはずです」。
オーナーのソアラは、シリーズ3代目にあたる。1991年のフルモデルチェンジから2000年まで、約10年間生産された。ボディサイズは全長×全幅×全高:4900x1805x1350mm、排気量2997cc、3リッターVVT-iエンジンは低・中速域においてもトルクフルさを感じられる、ハイレスポンスなパワーユニットだ。また、インテリアはラグジュアリーな空間を演出。より質感が高められた。ちなみに、3代目ソアラといえば、D1グランプリのイメージも色濃いかもしれない。事実、2.5リッターツインターボエンジンのモデルは「ドリフト車」として今もなおファンが多い。
改めてソアラをじっくりと眺めてみる。その佇まいは実にエレガントだ。この型のソアラを久しぶりに目にした感動もあってか、思わず胸がいっぱいになってしまった。
「私は乗り換える頻度が多い方なので、今までさまざまなクルマを所有してきましたが、この後期型のソアラは10代の頃からずっと憧れ続けてきた存在なんです。高校生の頃に、カタログを見たとき、真横のアングルに惹かれて好きになりました。それ以来、常に理想の個体を探し続け、ようやくめぐり会ったのが今の個体です」。
と、熱っぽく話すオーナー。このソアラは週末や休日限定で乗っているそうだが、長距離ドライブを楽しむ機会が多いという。納車当初は7万6000キロだったオドメーターも、現在は10万2000キロを刻んでいた。モディファイといえばカーナビを新調したくらいで、ほぼフルノーマルかつ抜群のコンディションを保っている。
「当初は、純正部品を使ってマニアックなモディファイを考えていましたが、時間が経つとその気持ちはなくなりました。ただ、フルオリジナルを維持することに特別こだわりがあるわけではなく、イジってあるクルマも、イジることも好きなので、カスタム車のイベントにもよく行きますよ」。
オーナーの年齢は27歳。これまで集めてきたクルマのカタログの収蔵数は1500冊に及ぶという。さらに、人生初の愛車は、なんと免許取得前に手に入れているというから驚きだ。今まで国産・輸入車に関係なく乗り継いだ愛車遍歴はバラエティに富む。クルマ好きが高じて自費出版も行っているそうで、クルマへの愛は尋常ではない。取材は、オーナーが自作したという、プロ顔負けのクオリティを誇るソアラのカタログ(下の水辺に佇むソアラが写っている画像の冊子がそれだ)を眺めながらスタート。まずはオーナーの愛車遍歴を伺ってみることにした。
「高校1年生のとき、アウディ・200クワトロを手に入れました。さらに高校2年生のときにダイハツ・ミラ・モデルノ・パルコを手に入れました。いずれも自宅の庭に置いて、洗車と車内で昼寝をするというカーライフを楽しんでいました。免許取得後、初の愛車はトヨタ・プログレ。2.5リッターのモデルで、水色のボディカラーにベージュのヌバック調のインテリアという、珍しい組み合わせの個体でした。この時点で、既にソアラが欲しかったんですが、当時やりたかったことを優先して同じエンジンのプログレを選んだんです。それから、IMPULの日産・マーチ(K12型)でサーキット走行の楽しさを知り、社会人になってからシトロエン・C4クーペVTRに乗り替えたことで、学生時代からメーターのデザインに惹かれていたクルマをようやく手に入れることができました。このシトロエンで四国一周をしたのは良い思い出です。その後は、ホンダ・シビックSiRⅡへ。実はホンダ車も好きで、B16A型のVTECエンジンを味わってみたかったんです。あのサウンドは脳内麻薬ですよね(笑)。その後、マツダ・ミレーニアやメルセデス・ベンツEクラスなどを検討しましたが、そろそろソアラを買ってもいいだろうと自分にOKを出したわけです」。
愛車遍歴を通してオーナーの個性的なカーライフが垣間見える。続いて、クルマに魅せられたきっかけを伺った。
「私は『内装マニア』でして…。特に、ラウンディッシュな木目調のパネルを見るとたまりません(笑)。現行のメルセデス・ベンツCクラスや、ソアラの内装がまさに『木目ファンタジー』なんですよ…。親曰く、物心がつくまでに好きなクルマはたくさんあったようですが、初めて買ってもらった初代セルシオのミニカーが私の好みの礎を作ったような気がします。父親もクルマ好きで、私も少なからず影響を受けたと思いますが、今の自分を形成しているのは小学生の頃から描き続けているクルマのイラストですね。毎日1台描くのが日課だったんですが、オリジナリティを出すためにホイールやエアロを描き変えているうちに、内装を描く楽しさに目覚めてしまいました。内装って、クルマのトータルコーディネートでデザインが決まるんです。乗る人に寄り添ってくれるクルマになれるかどうかは、空間次第だと言っても過言ではないと思っていて、そこに魅力を感じています。私はものづくりに関わる仕事をしています。現在の仕事に結びついている面もありますね」。
そんなオーナーの「人生観を変えたクルマ」は、存在するのだろうか。
「ずばりシトロエン・DS21です。C6や初期型のXMにも大変惹かれますが、やはりDSですね。社会人になってからフランスに留学していた時期があったのですが、ある日、友人と飲んでいてうっかり最終バスを逃してしまいました。仕方なくほろ酔いのまま深夜のパリ郊外をブラブラ歩いていたときでした。緑色のDS21が、交差点に進入して行ったのです。いわゆる『シブいサウンド』です。ハイドロは上がった状態で、走り去った瞬間のテールランプの光が今でも記憶に焼き付いています。このときの姿がどうしても忘れられず、その年の暮れにシトロエンの工場跡地に建つ、半非公開の予約制ミュージアム『コンセルバトワール・シトロエン』に観覧を交渉して訪れたほどでした。間近で見るDSは、エクステリアだけでなくインテリアも優雅であり、すっかり虜になりましたね。シトロエンの合理・機能を突き詰めた結果、唯一無二の美しさを生み出してしまうという思想に痺れています」。
「クルマ観」を醸成させた背景は少し特殊かもしれないが、オーナーの豊かな感性は、話を伺うほどに感じ入る。最愛のソアラを手に入れるまで、こうしてさまざまなクルマとの思い出を重ねながら、機が熟すのをじっくりと待っていたようだ。
「魅力的なソアラが見つかると、県外でも実車を確認しに出かけていました。今まで静岡・仙台・大阪などに車中泊をしながら遠征してきました。今の愛車は、2016年の晩秋に中古車のサイトで検索してみたときに、福岡で売れられていた個体でした。電話でスタッフの方に確認すると『僕が選んだのだから間違いないです!』とプッシュするので、遠方ということもあり、結局実車を見ずに購入を決めてしまいました」。
それから納車の日を迎え、キャリアカーから降りてきたその姿に、オーナーは息を飲んだ。
「中古車のサイトで検索したときはそれほどでもなかったのに、実際に愛車として向き合ったとき、こんな美しい個体があったのか…と見とれてしまいました。車体はオプションカラーのホワイトパールマイカで、パールがいちばん強く出ている色です。内装は通常、ダーク系が定番なのですが、この個体は品のあるアイボリーでした。運転していて、このアイボリーが視界に入ってくるのが最高です。もともとロングドライブが好きでしたが、ソアラを手に入れてからはもっと好きになりました。ある日『自費出版の本を知ってもらう旅』に出たときは、自宅からコミケ会場である東京ビッグサイトに向かい、その後、約800キロ西にある広島の自動車博物館まで自費出版した本を置いてもらったこともありました。その足で車中泊をしながら四国へ渡り、京都でソアラの写真を撮りながら帰ってきたこともあります。とにかくどれだけ乗っても飽きません。体が疲れてしまうまで、どこまでも走ってしまうんです」。
今後、最愛のソアラとどう接していきたいかという「決意表明」を伺ってみた。
「10代から憧れていたクルマに乗れているので最高なのですが、実はソアラを『アガリの1台』にするつもりはなくて、まだまだ乗りたいクルマはあります。でも、ソアラを一度手放したとしても、必ずもう一度手に入れると思います」。
ソアラはオーナーが10代からの想いを経て、すでに人生に寄り添う存在へと深化しているのだろう。
余談だが、オーナーのライフワークとなっている出版活動についても触れておこうと思う。オーナーは現在「TUNA」というペンネームで「街中で見かけなくなったクルマを通じ、自動車の魅力を伝える」をテーマに自費出版で本を制作しているという。自らイラストを描き、取材を行い、編集までこなしている。これらの作業を1人で行うのは、かなりの手間と時間が掛かる作業のはずだが、自費出版に至ったきっかけを伺ってみた。
「絵を描いているので、作品をカタチにしたかったことと、捨てられてゆくクルマ特有の切ない感情を、メッセージとして多くの人に伝えたいと思ったからです。きっかけは、フランス留学をしているときのことでした。現地の人とクルマとの接し方に感銘を受けたんです。家族でもないのに大切にされているのがわかります。ある種の愛くるしさを感じましたね。クルマを楽しみ、長く大切にするオーナーが多いのは、国の文化に由来します。そこに着目して、何か自分に表現できることはないかと、海外旅行へ出かけるたびにずっと考え続けてきました」。
「ある日、ふとそんな思いがひとつのアイデアへとつながりました。以前からロシアに行きたかったのですが、その理由は、多くの日本車が流入している国だからです。特にサハリンあたりには、トヨタ・ビスタやラウムなど、日本では比較的マイナーな車種が多く棲息しています。安価という理由もあるのでしょうが、例えばInstagramのハッシュタグを辿っていくと、とても大切にされている数多くの日本車に出会えます。このとき、モノに対するリスペクトを確実に感じました。ロシアをはじめ、世界中で古い日本車たちが健気に走っている現実を知ると、たまらなく愛おしく思えてしまって…。新陳代謝という言葉は嫌いではありませんが、まだまだ使えるモノが『価値のない存在』のように見られていくのはあまりにも悲しい…。そうした気持ちを私の絵や写真で発信しようと決めました」。
オーナーのクルマに対する深い愛情は、「よいこのじどうしゃ1」という本に投影されていることが分かる。そして、ロシアで出会った日本車たちは、著書「極東ロシアじどうしゃ #異世界転生編」で紹介されている。こちらもぜひ、チェックしていただきたい。
いかなるクルマも、自然発生的に生まれたものではない。誰かが必ず苦労して創り上げたからこそデビューできたのだ。そして、おろしたての新品だった時代があり、大切に乗られていたはずだ。オーナーの本に目を通していると「モノに対するリスペクトすることの大切さ」を改めて感じずにはいられなくなるほど、真摯な思いが込められている。
【撮影地:日本橋・晴海周辺(東京都中央区)他】
(編集: vehiclenaviMAGAZINE編集部 / 撮影: 古宮こうき)
[ガズー編集部]
連載コラム
最新ニュース
-

-
トヨタが新型BEVの『bZ3C』と『bZ3X』を世界初公開
2024.04.25
-

-
メルセデスベンツ GLCクーペ、PHEVモデルを追加…EV走行距離118km
2024.04.25
-

-
中国IT大手のテンセントとトヨタ自動車が戦略提携
2024.04.25
-

-
ホンダが新型EVの『e:NP2』を発売
2024.04.25
-

-
ゲーム内で先行体験! AFEELAプロトタイプがグランツーリスモ7に登場
2024.04.25
-

-
マツダ、電動セダン『EZ-6』世界初公開、24年発売へ SUVコンセプトも…北京モーターショー2024
2024.04.25
-

-
ヒョンデの高性能EV『アイオニック5N』が日本上陸! 特別仕様車の予約開始
2024.04.25