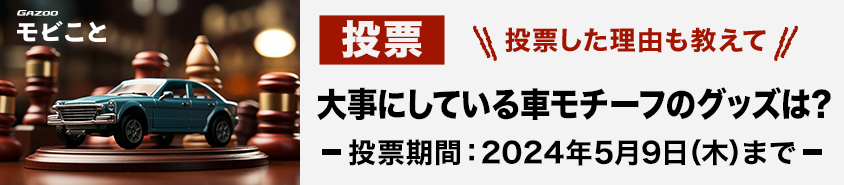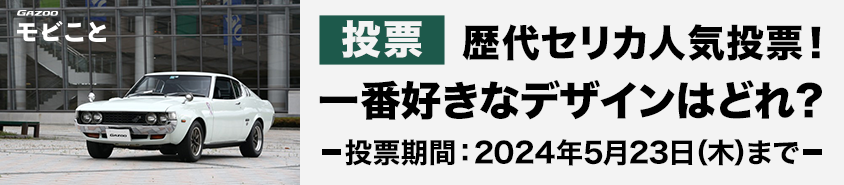水温も油温も高すぎはもちろん低過ぎも禁物! どちらも適温が大切なこれだけの理由!!
-

ラジエーター
暑い夏が迫るこの季節。これから気になるのがクルマの温度管理だ。エンジンを健康に保つためには水温と油温のふたつの温度が重要になる。
一般に温度が高くなるとトラブルの元となるというイメージもあるが、実は低すぎることによってトラブルや燃費が悪くなるといったこともあるのだ。
それでは一体適温はどのくらいなのか、適温はどのように保てばいいのか解説していこう。
目次
水温の適正温度は? 下がると燃費が悪化する可能性も
温度を安定させるサーモスタットの役割
ラジエーターで効率的に水温を下げるには?
エンジンオイルの温度は120℃以下なら問題なし
オイルクーラーのメリットとデメリット
水温の適正温度は? 下がると燃費が悪化する可能性も
水温とはエンジン冷却水の温度のこと。エンジンはクーラントと呼ばれる不凍成分を含んだ水で冷却されている。エンジンで熱せられた冷却水はラジエーターで空気中に熱を放出する。
このときに重要なのが加圧されていること。水は100℃になると沸騰してしまう。沸騰すると冷却水路に気泡が発生して冷却ができなくなってしまう。そのためにラジエーターキャップはスプリングが入っていて、冷却水の水路全体の圧力が上がるようになっている。
圧力鍋のように加圧することで水の沸点を上げることができるのだ。そうなると冷却水が沸騰してしまうことを防げるという仕組みだ。
冷却水の適正な温度は80~100℃くらい。だが、これはエンジンの設計によって異なる。とくにここ20年のエンジンは温度が高くなる傾向にある。
00年代までの常識では「水温は80℃が標準。100℃は危険温度」だった。ところがエンジン内部の温度を全体にあげて完全燃焼しやすい状況にしたほうが排気ガスが綺麗になりやすい。
そこで意図的に近年は温度が高めで「90℃が標準。110℃以上が危険温度」といったイメージに変わってきている。
近年のエンジンを80℃で安定させたからといってとくに良いことはない。むしろエンジン制御コンピュータ側でもっと水温を上げようという補正が働いて、適正よりも空燃比を濃くして燃費が悪くなることがある。
つまり、そのエンジンの設計温度に合わせて温度を管理することが大切なのだ。
温度を安定させるサーモスタットの役割
-

サーモスタット
そのためエンジンにはサーモスタットが装備されている。サーモスタットは水温が上がるとラジエーターに冷却水を流し、水温が下がるとサーモスタットを閉じてラジエーターに循環させずエンジン内部を冷却水が循環するようにする役割を持つ。
通常はラジエーターの放熱容量にはたっぷりと余裕がある。サーモスタットは常に開いて閉じてを繰り返している。最近のクルマだとサーモスタットが85~90℃で開くくらいの設定が多く、例えば「88℃で開く、87℃で閉まる」を繰り返すことで水温は88℃付近で安定するという仕組みだ。
チューニングカーでエンジンパワーが上がり、発生する熱量が大幅に増えているとか、サーキット走行でガンガン走って水温が上がってしまう、というわけでなければラジエーターを大容量にしても水温が下がるわけではないのだ。
ラジエーターで効率的に水温を下げるには?
車種ごとのサーモスタットの開く設定温度よりも水温がどんどん上がってしまうなら、ラジエーターをチューニングする意味が出てくる。大容量タイプなどがあるが、重要なのは厚みだけではないということ。
これまではラジエーター自体の厚みを増やして、2層とか3層などと言ってきた。蓄える水の量が増えて外気に触れるので温度が下がりやすい。もちろんそれもひとつの手。しかし、それだけではない。
ラジエーターは風が抜ける時に熱を奪っていくので、あえて薄めのラジエーターで風を通り抜けやすくして温度を下げるという手もある。
同じ狙いでボンネットやフェンダーのダクトからエンジンルームの熱を排出することも有効。エンジンルームから空気が抜けていけば、もっと空気が入りやすくなりラジエーターをたくさんの空気が通過するので温度は下がるのだ。
エンジンオイルの温度は120℃以下なら問題なし
もうひとつ重要な温度が油温。エンジンオイルの温度だ。こちらも昔に比べると適正温度が変わってきている。昔は100℃以下なんて言われたりもしたが、現在は120℃以下なら問題なし。むしろ低すぎると問題がある。
オイルには結露などによってどうしても水分が混入する。これが油温100℃以上になれば蒸発するので問題ないが、油温が低いまま乗っているとエンジンオイルと水分が混ざって乳化して、ドレッシングやコーヒー牛乳のようになってしまうのだ。
こうなるとエンジン保護性能は落ちるし、オイル自体のライフも極端に短くなってしまう。
昔は100℃以下と言われたが、現代のクルマなら110℃でも問題はない。120℃でも大丈夫。そしてそれ以上になると徐々にオイルにダメージが蓄積していく。120℃を超えるとオイルが徐々に傷んでいくので早めのオイル交換が必要になる。
そこでオイルクーラーの出番である。油温が高くなりすぎるとエンジンのダメージも心配だし、オイルが傷むのでそれによってエンジン内部がダメージを受けやすくなる。それを防ぐためにオイルの温度を下げるのがオイルクーラーの役割だ。
だが上記のように必要なシチュエーションは120℃を超えてくる場合のみ。それ以下ではほぼ意味がない。むしろオイルクーラーによって80℃や90℃で安定してしまっては温度が低すぎるのだ。
温度が低すぎると上記の乳化しやすくなるほかにそもそもオイルの設計温度になっていない問題がある。オイルは温度が低いほど高性能なわけではなく、ある程度の温度になったときに最適な性能を発揮するように成分が調整されている。良かれと思って温度を下げても良いことばかりではないのだ。
オイルクーラーのメリットとデメリット
-

オイルクーラー
なので、オイルクーラーを装着するならこちらもサーモスタット付きモデルが望ましい。そうすればオーバークールで温度が下がりすぎることもない。
だが、そもそもで言えばできればオイルクーラーは無い方が良い。なぜならそれは漏れるリスクが増えるから。大手メーカーのオイルクーラーキットであれば新品時にオイルが漏れることはほぼない。それだけの精度と信頼性はもちろん備えている。
しかし、5年、10年と使用していくうちにフィッティングのどこかから漏れてくるリスクや、フィッティングに力が掛かって折れてしまうリスクはある。
もし、漏れてしまうと車両火災にもつながるし、フィッティングから大量に漏れると瞬時に油圧はゼロになり、エンジン内部の潤滑がすぐにできなくなってしまう。そうなると一瞬でエンジンブローを招きかねない。そういったリスクもあるので、無闇につければいいわけではないのがオイルクーラーなのだ。
だが、コスト面でのメリットは見逃せない。
例えば日産のGT-R(R35)では、オイル交換について規定がある。油温が110℃を超えなかった時=1年/1万5000km交換。油温が110~130℃になった時=5000km交換。油温が130℃を超えた時=速やかにオイルとフィルターを交換。このように決められている。
これはすなわち高温になるとオイルがダメージを受けるので早めに交換が必要ということ。自動車メーカー側としてもオイルが高温になると劣化することを認識しているわけである。
ならば同じようにマイカーに当てはめるとすると、車種にもよるがオイルクーラーなしでサーキット走行をしたら早めに交換することになる。場合によっては毎回130℃を超えるようであれば、サーキット走行の度にオイル交換が必須となる。
それがオイルクーラー装着によって温度が抑えられればオイル交換時期を延ばすことができる。頻繁にサーキット走行を楽しむなら、オイルクーラーを付けたほうがランニングコストは抑えられるのだ。
このように温度に従ってオイル交換のタイミングも変わるので、オイルクーラーは適切な使い方をすれば大きな効果を持つパーツなのだ。
(文:加茂 新)
カスタマイズの連載コラム
-

-
チューニングの仕上げはアライメント調整。走りも燃費も左右する必須の項目
2023.10.16 コラム・エッセイ
-

-
曲がりにくくなるは昔の話!? LSDはスポーツ走行に必須!
2023.09.24 コラム・エッセイ
-

-
カスタムで正しいドライビングポジションを手に入れよう!
2023.09.17 コラム・エッセイ
-

-
ハンドリングをグレードアップ!! 補強パーツでもっと良いクルマに仕立てる
2023.08.28 コラム・エッセイ
-

-
レスポンスと速さをアップ! 車検も心配ない吸排気チューニング
2023.08.06 コラム・エッセイ
-

-
水温も油温も高すぎはもちろん低過ぎも禁物! どちらも適温が大切なこれだけの理由!!
2023.07.09 コラム・エッセイ
-

-
タイヤ選びで走りの楽しさが変わる!! 純正以外のタイヤを履く意味と理由とは
2023.07.02 コラム・エッセイ
-

-
パワーアップだけじゃない!? マフラー交換の絶大な効果!
2023.06.18 コラム・エッセイ
-

-
ホイールは走行性能に直結! 軽さだけじゃない機能的ホイール選び
2023.06.15 コラム・エッセイ
-

-
高けりゃいいわけじゃない! ブレーキパッド選びのキモは「適正温度」
2023.05.22 コラム・エッセイ
-

-
車高調やスプリングなど、サスペンションチューニングの基本を解説
2023.05.18 コラム・エッセイ
連載コラム
最新ニュース
-

-
トヨタがインドで新型SUV『アーバンクルーザー・タイザー』を発表…Aセグメント再参入
2024.05.01
-

-
メルセデスAMG『E53』新型、612馬力の電動セダンに…欧州受注開始
2024.04.30
-

-
この顔で中国EV市場に“爪痕”残すか? 日産『エピック・コンセプト』は26年までに市販へ…北京モーターショー2024
2024.04.30
-

-
トヨタ・クラウンのアウトドアカスタム「LANDSCAPE」がお披露目…移動時間すらも記憶に残るような車に
2024.04.30
-

-
トヨタのファミリー向けBEV『bZ3X』は、オーソドックスなSUVタイプ…北京モーターショー2024
2024.04.30
-

-
洗車機=傷が付くはもう古い! 最新洗車機の凄さとプラスアルファの洗車法
2024.04.30
-

-
イタリアの恋人:アルファロメオ『ジュリエッタ』が誕生70周年を迎える
2024.04.30
最新ニュース
-

-
トヨタがインドで新型SUV『アーバンクルーザー・タイザー』を発表…Aセグメント再参入
2024.05.01
-

-
メルセデスAMG『E53』新型、612馬力の電動セダンに…欧州受注開始
2024.04.30
-

-
この顔で中国EV市場に“爪痕”残すか? 日産『エピック・コンセプト』は26年までに市販へ…北京モーターショー2024
2024.04.30
-

-
トヨタ・クラウンのアウトドアカスタム「LANDSCAPE」がお披露目…移動時間すらも記憶に残るような車に
2024.04.30
-

-
トヨタのファミリー向けBEV『bZ3X』は、オーソドックスなSUVタイプ…北京モーターショー2024
2024.04.30
-

-
洗車機=傷が付くはもう古い! 最新洗車機の凄さとプラスアルファの洗車法
2024.04.30