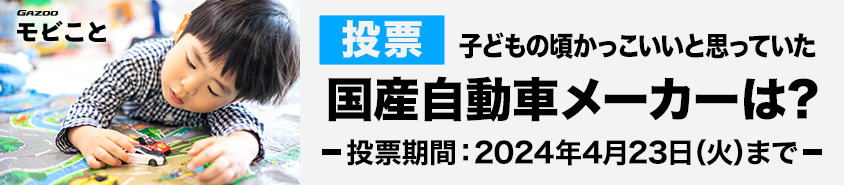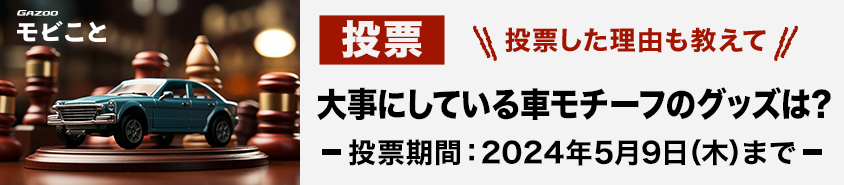陶芸家が、何の変哲もない先々代ホンダ フィットに見いだした「美」
鎌倉に工房と窯を持ち、茅ヶ崎にギャラリーを構える、既成の枠にとらわれない自由な作風で人気の陶芸家。同時に料理人としての顔も持ち、一時はなぜかリトアニアの日本大使館で「大使閣下の料理人」も務めていた。そして、マニアックなイタリア・フランス車専門店界隈ともディープな交友関係を持っている、重度のクルマ好き。
そんな人物の自家用車といえば、あなたはどんな車種を想像するだろうか?
筆者が最初、勝手になんとなく想像したのはフランスのルノー エクスプレスというフルゴネットのMPVで、「もしかしたら、意表をついてロシアのラーダ ニーヴァかな?」とも思った。いずれにせよ、マニアックな輸入車であることはほぼ間違いないような気がしたのだ。
だが、神奈川県茅ヶ崎市の「卓袱堂」――今回の主人公である陶芸家、今泉 卓さんのギャラリーで待ち受けていたのは、何の変哲もない国産ハッチバック。2世代前のホンダ フィットだった。
まぁ「何の変哲もない」と言っては失礼かもしれないし、今泉さんのフィットはRSというスポーティなグレードではある。
だが、トランスミッションは先々代フィットRS自慢の5MTではなくフツーのCVTで、ボディカラーも、失礼ながら芸術家の選択とは思えないほど普通なストームシルバーメタリック。このクルマだけを見て「うむ、オーナーは自由な作風の陶芸家に違いない」と見破れる人は、1000人に1人もいないはずだ。
しかしなぜフィットなのか?それも、やや地味なシルバーメタリックの。
「なんていうのかな、父の手前……ということになるでしょうか」
英国系の商社に勤務していた父の仕事の関係で、小学生時代の今泉 卓さんはオーストラリアに居住していた。そして残念ながら、当時の現地で何度も人種差別を受けた。
結果、卓少年は「将来は“日本人としての誇り”を感じられる職に就きたい」と考えるようになり、中学生の頃、陶芸家になることを決意。
高校卒業と同時に京都へ渡り、長年にわたって陶器と磁器制作の修行を重ね、繊細な茶陶の制作にも従事。そして1998年、32歳のときに自らの工房「卓袱堂」を立ち上げた。
「クルマ好きとしての今泉 卓」さんはその間、スバル レオーネやランチア βクーペ、あるいは1960年代のフォルクスワーゲン タイプ1やシトロエン AXなど、マニアックな車種に乗る生活を楽しんでおり、「次は、作品の運搬に使える英国製の古いバンでも買おうかな?」などと考えていた。
そして、すでに会社務めを引退していた父――卓さんの父だけあってなかなかのクルマ好きだった父は、今から12年前の2008年、自ら「これが最後のクルマ」と言ってシルバーメタリックのホンダ フィットRSを購入した。
「あの父にしては地味な選択だな」とも思った今泉さんだったが、それ以上のことは特に考えず、今泉さん自身はシトロエンに乗りながら6年の月日が流れた。
そして、父が倒れた。脳梗塞だった。
「幸いにして命に別状はなく、今も元気に暮らしています。でもクルマの運転は、とてもじゃないけどできる状態ではありませんでした」
入院した父のフィットRSを見てみると、クルマの四隅には小キズが大量に生じていた。クルマ好きで、もともとは運転の上手な今泉さんの父ではあったのだが、倒れる少し前から、そもそも普通に運転できる状態ではなくなっていたのだ。
「で、父は免許を返納してクルマの運転をやめることになったのですが、それはいいとして、僕に言うんですよ。『お前、このフィットに乗ってくれないか……?』って」
若い頃からクルマを愛していた人だけに、それがごく一般的な実用ハッチバックだったとしても、「最後の愛車」が目の前から消失してしまうことに耐えられなかったのだろう。
とはいえそう言われても、今泉さんも困る。
「父の気持ちはわかりますが、こっちにだって都合や趣味ってものがあります。正直『嫌だなぁ……』と思ったのですが、まぁ父の願いを無下にするのもアレですので、嫌々ですが『わかった』と言い、しばらくの間フィットに乗ることにしたんです。シトロエンのほうは売却してね。まぁしばらく乗ってやれば、父の気持ちも整理がつくだろう――なんて思いまして」
だが今泉さんと2008年式ホンダ フィットRSとの関係は「しばらくの間」では終わらず、結果としてその後6年間、乗り続けることになった。
そのため、ここで改めて冒頭付近で発した問いを繰り返したい。
なぜフィットなのか?
「今でもね、ちょっとどうかとは思うんですよ。懇意にしてるディープなイタリア・フランス車専門店までフィットに乗って行くと『来ないでくれ(笑)』と嫌がられますし」
もちろんその専門店店主氏が言う「来ないでくれ(笑)」というのはあくまで「(笑)」付きの、友人同士ゆえの冗談ではある。だがシルバーの国産小型ハッチバックが、その専門店の展示場にも、そして陶芸家にも、「バッチリ似合ってる」とは言い難いのはおおむね事実だろう。
「でもね、このフィットRSってクルマ……すっごくいいんですよ、実は」
2世代前のCVTのフィットRSは「いいクルマ」であり、「気持ちいいクルマ」でもあると、陶芸家は言う。
「小さいエンジンなんだけどトルクが豊かでね、その出方も自然で、運転していると妙に気持ちがいいんです。CVTというトランスミッションを嫌う人も多いみたいですが、僕は嫌いじゃないというか、このクルマには合ってるんじゃないかと思います。昔乗ってたシトロエンAXの5MTを低回転域でどんどんシフトアップさせたときのような、なんとなくそんな感じの気持ち良さが、このエンジンとトランスミッションにはある気がしますね。あと、これはまぁ有名な話ですがフィットは荷室が広いので、作品を運搬するためのクルマとしても非常に使い勝手がいい」
“父の手前”で乗り始めたシルバーメタリックの国産ハッチバックは、いつの間にか今泉 卓さんにとっての“けっこう気持ちのいい相棒”へと変わってしまったのだ。
思いもよらぬ展開にも見えるが、しかし考えてみれば、今泉さんの“変心”はごく当然のことなのかもしれない。
今泉さんは陶芸作品づくりにおいて、基本的には先人がすでに作った作品から学ぶのではなく、自然すなわち太陽や風、動物や植物の姿などを大きなヒントにしているのだという。
そして冒頭付近で紹介した「なぜか駐リトアニア大使の料理人もしていた」というキャリアについても、正式に料理を学んでいたからオファーがあったわけではない(むしろ正規の調理教育はいっさい受けていない)。ただただ料理が好きで、インスピレーションの赴くままに料理を作り、親しい知人にふるまっていたら評判が広がり、ひょんな縁でリトアニアの日本大使館に招聘され、そのオファーを受けてみたというだけのこと。
つまり今泉 卓さんとは、「その発想とアウトプットにおいて極度に自由」な人なのだ。
既存の枠組みにとらわれることなく発想し、そしてアウトプットできる精神的自由人。そんな彼にとって、2世代前の地味なハッチバックの隠れた美点を見いだすことなど、実は造作もないことだったのかもしれない。
(文=伊達軍曹/写真=阿部昌也)
[ガズー編集部]
「アーティスト」御用達の愛車たち
愛車ライフ 特集記事
愛車広場トップ
連載コラム
最新ニュース
-

-
ホンダの新型SUV『WR-V』、発売1か月で1万3000台を受注…月販計画の4倍超
2024.04.23
-

-
空力とエンジン性能を高める“穴”の真相~カスタムHOW TO~
2024.04.23
-

-
ポルシェ『カイエンGTS』改良新型、日本での予約を開始---価格は1868万から
2024.04.22
-

-
メルセデスAMG GT 新型に816馬力の電動「63」登場…0~100km/h加速2.8秒
2024.04.22
-

-
高速道路SA・PAでEV充電器大幅増設、2025年度末には充電口数1100へ
2024.04.22
-

-
ホンダ、新型SUV『WR-V』など展示へ
2024.04.22
-

-
乗員の数と愛犬の頭数によるクルマ選びの極意【青山尚暉のわんダフルカーライフ】
2024.04.22