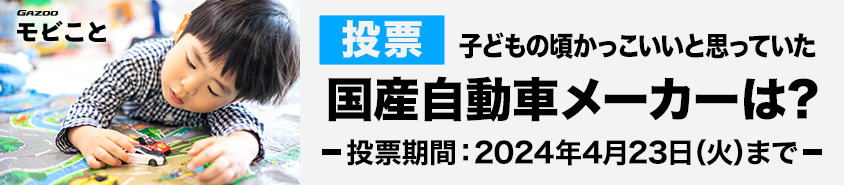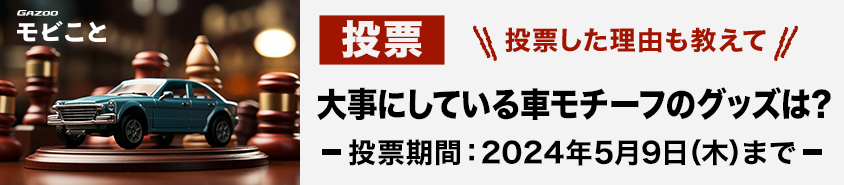デートカーからの脱却 4代目ホンダ・プレリュード・・・懐かしの名車をプレイバック
デートカーのイメージを払拭(ふっしょく)したかったのか、1992年に登場した4代目「プレリュード」はスポーツ濃度が一気に増した。丸みを帯びた砲弾型のフォルムや3ナンバーサイズとなったワイドなボディーは、従来モデルとは一線を画すものだった。
合わせて読む
目指したのは大人のパーソナルクーペ 初代 ホンダ・プレリュード
新風はバブルの訪れとともに 2代目 ホンダ・プレリュード
きらびやかで甘く切ない空気感 3代目ホンダ・プレリュード
デートカーブームの終焉 5代目ホンダ・プレリュード
“デートカー”として人気を博した「ホンダ・プレリュード」を解説
走りの質感が違う
当時、自動車専門誌の編集者をなりわいとしていたので、国内外の新車に触れる機会も多かった。プレリュードに出会う前の愛車も、報道関係者向けの新型車試乗会で一目ぼれした「インテグラ」だった。初めてVTECに乗った衝撃が強烈で、即注文した。
あの頃はスポーツカーの全盛期。いわゆるファミリーカー(4ドアセダン)には目もくれなかった。だが、“デートカー”と呼ばれるグレーゾーンがあった。スタイリッシュで、そこそこのスペック。正直、眼中にはなかったが、スタイリッシュで走りも悪くないというどこか気になる存在ではあった。
そんなあるとき、取材で鈴鹿サーキットへ向かった。そのとき移動の相棒だったのが取材車両として借り出した4代目プレリュードだった。
先代までのナンパな印象はなくなったとはいえ、オートマだし、2.2リッターエンジンなのに200PSだし。VTEC積んでるならリッターあたり100PSはないとね。期待せずに東名高速を西へとひた走る。「あれ? 4段ATのくせに踏めば高回転まできっちり回るじゃない」。しかも視線の低さはスポーツカーのそれ。悔しいが走りの質感は「インテグラ以上じゃないか」と思った。
ボディーを引き締め本格スポーツに舵を切る
決め手は純正オプションとして用意されていたテレビだった。小さいながらも助手席側のダッシュパネルにきれいに収まり、VTECサウンド以外の楽しみも与えてくれたのだ。それで陥落。人生初のAT車を所有することになる。最後の一押しがテレビだったとはいま思えば不思議だが、当時はそれがイイモノに思えたのだ。
デートカーのイメージが強かった先代に対して1765mmへと全幅は拡大。全長は4400mm、ホイールベースは2550mmへとこちらはいずれも短縮され、スポーツクーペらしいいでたちは十分に満足できた。赤いボディーカラーを選択したのは、気の迷いだったのかもしれない。
愛車はメーカーオプションを含めたほぼフル装備。その効果を実感することの少なかった4WSやトラクションコントロール+ビスカス式LSD、ちょっと制御の粗いABSも付いているだけで満足感に浸れた。愛煙家としてありがたかったのは初代から受け継がれてきたサンルーフで、これはチルトアップ機能付きのアウタースライド式に変更されていた。そして、例のテレビ。停車中や待ち合わせの時間つぶしにも退屈することはなかった。
クーペには我慢も必要
いざ走りだせばリッターあたり100PSに欠けるとはいえ、200PS/6800rpmの最高出力、219N・m/5500rpmの最大トルクは、1.6リッターのインテグラとは別の次元だった。ばかにしていたATにも、いつの間にか順応していた。デートカーと呼ばれた軟派なモデルというイメージからの脱却も図りたかったのだろう。スポーティーな足まわりやよく回るVTECエンジンが、存分に走りを楽しませてくれた。
走りもスタイリングも個性的なプレリュードに乗り換えたことは大正解だったが、ひとつだけ周囲に不評だった点がある。リアシートの居住性だ。
前期型となる愛車の後席中央には、左右の座席を隔てるかのような収納ボックスがあった。前席優先のキャビンレイアウトはスポーティーな雰囲気づくりにも欠かせないお気に入りのポイントだったのだが、運悪く後席に座る人にとっては、単に狭さを助長する邪魔なものでしかなかった。
N1耐久レースでも活躍
前期モデルの乗車定員が2+2の4人というのも減点ポイントで、さらに後席の足もとスペースが狭く、サイドシルエットからわかるとおりヘッドクリアランスも小さい。「そもそもスポーツカーなんだし、人をアッシー(死語)代わりに使っているんだから、それぐらい我慢しろよ」と思いつつも、後席に押し込まれた友人はもちろんのこと、世間も理解を示してはくれず、セールス面でもプラスに働くことはなかった。
その証拠に1993年に登場したマイナーチェンジモデルでは、後席の収納ボックスが廃止され、一般的なシート形状に改められていた。ヘッドクリアランスやニースペースは変わらないが、乗車定員は4人から5人に増えた。
余談になるがこの時代、当時人気のあったN1耐久レース(現在行われているスーパー耐久の前身)の取材に行くと、プレリュードで参戦していたチームから「もしもスペアパーツが足りなくなったら(クルマから部品外して)使わせて」と、声をかけられることもあった。
幸い部品を提供することはなかったが、「プレリュードがレースに参戦している。それはもうスポーツカーの証しじゃないか」と、当時はそう納得したものだった。
(文=名取則隆)
懐かしの名車をプレイバック
-

-
俊敏なFFライトウェイトスポーツカー 2代目「ホンダCR-X」を振り返る…懐かしの名車をプレイバック
2024.04.03 特集
-

-
ホンダが生んだ奇跡のオープンスポーツカー「S2000」を振り返る…懐かしの名車をプレイバック
2024.04.02 特集
-

-
その静かさが高級車の概念を変えた! 初代「トヨタ・セルシオ」を振り返る…懐かしの名車をプレイバック
2024.04.01 特集
-

-
人気ナンバーワンの5代目! S13型「日産シルビア」を振り返る…懐かしの名車をプレイバック
2024.03.31 特集
-

-
ただよう欧州車の香り 初代「日産プリメーラ」を振り返る…懐かしの名車をプレイバック
2024.03.30 特集
-

-
そのカッコよさにみんなシビれた! 憧れた! 初代「日産フェアレディZ」を振り返る・・・懐かしの名車をプレイバック
2024.03.29 特集
プレリュードが愛車のカーライフ
-

-
29歳のオーナーが受け継いだのは、父が引き取った“発注ミス車”の1990年式ホンダ プレリュード Si 4WS(BA5型)
2024.03.15 愛車広場
-

-
21年ぶりに初愛車と同じホンダ・プレリュードのオーナーに
2024.03.11 愛車広場
-

-
父の63歳誕生日にプレゼントしたプレリュード。ネオクラホンダの魅力
2023.12.03 愛車広場
-

-
本田宗一郎に想いを馳せて。62歳のオーナーが愛でる1981年式ホンダ プレリュード XXR(SN型)
2021.09.04 愛車広場
-

-
【GAZOO愛車広場 出張撮影会】偶然の出会いで見つけた超優良個体のプレリュードを即決購入
2019.01.14 愛車広場
連載コラム
最新ニュース
-

-
沖縄で初開催のラリーチャレンジは大盛り上がり!観客目線レポート&参加者インタビューをお届け
2024.04.18
-

-
GR Garageが沖縄の新たなカーカルチャーの牽引役へ。熱烈なクルマ好きスタッフが語る夢
2024.04.17
-

-
ホンダが新型EV「イエ・シリーズ」を中国で発表…2027年までに6車種を投入へ
2024.04.17
-

-
サスペンションの新常識! 1G締めがもたらす驚きの効果とは?~カスタムHOW TO~
2024.04.16
-

-
なぜ? アルファロメオ『ミラノ』の車名を禁じられる…なら『ジュニア』だ!
2024.04.16
-

-
日産が北京モーターショー2024で新エネルギー車のコンセプトカーを展示予定
2024.04.16
-

-
【ミサノE-Prix】ダ・コスタ失格、ローランドが繰り上げ優勝…フォーミュラE 第6戦
2024.04.15
最新ニュース
-

-
沖縄で初開催のラリーチャレンジは大盛り上がり!観客目線レポート&参加者インタビューをお届け
2024.04.18
-

-
GR Garageが沖縄の新たなカーカルチャーの牽引役へ。熱烈なクルマ好きスタッフが語る夢
2024.04.17
-

-
ホンダが新型EV「イエ・シリーズ」を中国で発表…2027年までに6車種を投入へ
2024.04.17
-

-
サスペンションの新常識! 1G締めがもたらす驚きの効果とは?~カスタムHOW TO~
2024.04.16
-

-
なぜ? アルファロメオ『ミラノ』の車名を禁じられる…なら『ジュニア』だ!
2024.04.16
-

-
日産が北京モーターショー2024で新エネルギー車のコンセプトカーを展示予定
2024.04.16