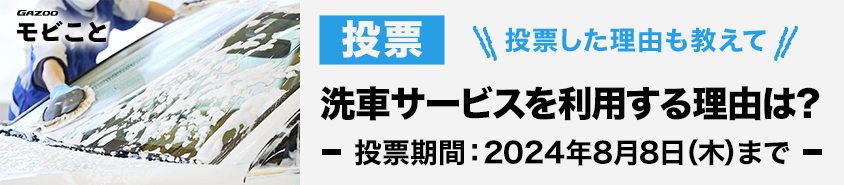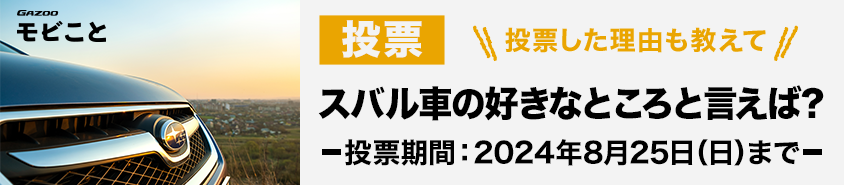日本の将来が見える!?シンガポールのシェアサイクル事情
シンガポールのシェアエコノミーの主役はクルマのライドシェアだが、都心部でラストワンマイル(直訳すると最後の1マイル=1.6kmという意味になるが、利用者にリーチする最後の距離という意味)をカバーする役目を果たしそうなのが、自転車やキックボードといった軽車両などを利用したシェアサービスだ。特にシェアサイクルは、エコな移動手段としても注目を集めており、シンガポールだけでなく全世界で注目されている。
シンガポールでは中国系のofo、Mobikeといった事業者や、シンガポールローカルなSG BIKEといった事業者などがシェアサイクル事業に参加しているほか、Neuronという事業者が電動キックボードシェアサービスを提供しており、それらを利用してちょっとした移動が効率よく可能になっている。
MaaSにおけるラストワンマイルの有望な選択肢、シェアサイクル
MaaS(Mobility-as-a-Service、ITを活用した統合された交通サービスのこと)への注目度は上がり続けるばかりで、特に自動運転の技術を利用したロボットタクシーやロボットバスには注目が集まっている。だが、実際のところMaaSを実現するにはそうした自動運転ばかりでなく、ラストワンマイルと呼ばれる公共交通機関から家庭までの最後の区間をカバーする交通サービスが必要と考えられている。
そうしたMaaS時代のラストワンマイルの候補と考えられているが、シェアサイクル、つまりは自転車のシェアリングサービスだ。例えば、電車で駅まで到着した場合、歩いて20分も30分もかかるような場所であればロボットバスに乗る、あるいはロボットタクシーに乗るということになるだろうが、例えば徒歩10分程度であれば歩くという選択肢が一般的だろうし、歩かないとしてももう少し速い移動手段があればいいということにならないだろうか? そこの隙間を埋めるのがシェアサイクルだと考えられているのだ。
特に中国では都市部における自動車の渋滞が常態化している。それを解消する手段の1つとしてシェアサイクルに注目が集まっていて、現在の中国ではシェアサイクルは一般的になりつつある。
シェアサイクルを実現する仕組みは、いわゆるIoT(Internet of Things)という概念が利用されている。IoTは機器に何らかの形でインターネットに接続する機能を持たせて、リモートで操作したりできるようにする仕組みだ。
シェアサイクルの自転車には低消費電力で動作する、セルラー(携帯電話)通信モジュールなどが内蔵されている。それにより事業者側のコンピュータが自転車の位置や、電動アシスト機能があるならバッテリーの状態を把握することができる。
-

- 利用するにはアプリを起動して、自転車に貼られているQRコードを読み込むだけ。すると事業者側のコンピュータが通信を使って自転車のロックを解錠する
-

- 返却時にはロックをかける、これだけで情報が事業者に反映され返却したことがユーザーのスマートフォンに通知される
利用者はスマートフォンを利用して利用可能な自転車がどこにあるのかを確認することが可能で、確認したらそこの場所へ行き、自転車についているQRコードなどをスマートフォンで読み込むことでレンタルを開始することができる。そして使い終われば、返却の手続きをとって終了と、実にシンプルに利用することが可能だ。
ofoやMobileなどの中国勢が中心のシェアサイクル、電動キックボードもサービスイン
-

- 日本でも事業を展開しているMobikeのシェアサイクル
シンガポールのシェアサイクルの事業者は複数あり、ofo、Mobikeといった中国の事業者と、SG BIKEというシンガポールローカルな事業者などが競争している状態だ。
-

- ofoのシェアサイクル
ofo、Mobikeは中国で急成長した事業者で、世界的にも有望なベンチャー企業として注目されてきた。ここ1年ぐらいは資金繰りが話題になるなど、成長に陰りが出始めているが、それでも他のアジアの国に進出するなど積極的な投資を行なっている。ちなみに、Mobikeは日本法人(モバイク・ジャパン株式会社)もすでに設立しており、福岡市、札幌市、神奈川県大磯町などでサービスを行なっている。もう1つの事業者であるSG BIKEはシンガポールの地場企業で、シンガポールのみで営業している。
-

- SG BIKEのシェアサイクル
-

- このようにポートではないところでも借りられるし、返却も可能
ofoやMobikeなどは中国ではどこでも、借り出し、返却が可能としているが、日本ではポートと呼ばれるシェアサイクル専用のパーキングスペースに返却すると説明している。これは、シェアサイクルが放置自転車となることを避ける措置だと考えられる。シンガポールではポートに返すことを奨励とはしているが、必ずしもポートである必要はないようで、そもそもポートではないところに自転車が置いてあり、それを借りることも可能だったし、ポートではないところに返すことも可能だった。
なお、シンガポールのシェアサイクルはバッテリーが搭載されているものの、それは通信用として利用されているらしく、電動アシスト自転車ではなかった。
-

- Neuron Mobilityの電動キックボード、最高時速25km/hとなかなか高性能
また、自転車ではないが電動キックボードシェアサービスを提供しているのがNeuron Mobility。充電ステーションを中心に電動キックボードが用意されており、それに乗って移動することができる。シンガポールの法律では15km/h(歩道)ないしは25km/h(サイクリングロード)以下で走る必要があり、2段階で速度が切り替えられるようになっている。サイクリングロードで走ると25km/hはかなり速く感じた。
都心部の公園に設置されていたポート
ただし、これらのシェアサイクルなどは、シンガポールのどこにもあるという形ではなく、主に都心部に集中していた。借り出し、返却ができるポートは、ほとんどが日本で言えば東京の大手町のような金融系の企業が集中しているCentral Business Districtのみにあり、その周辺でしか利用できないという現状だった。
-

- 金融街からかなり離れたところに放置されていたofoのシェアサイクル、こうならないようにポートへの返却が奨励されている。
これは無制限に行ける場所を増やすと、放置自転車や放置スクーターになってしまうことを避ける措置だと考えられる。このため現状ではラストワンマイルというよりは、都心でのより効率的な移動ということに主眼が置かれていると考えることができるだろう。現時点では市民の足になっているというよりは、実証実験の段階であると感じた。
-

- 世界三大がっかりの1つと言われる小さい方のマーライオンの前で1枚。このようにコンパクトなシンガポールだけに、シェアサイクルでの観光もお勧め
逆に言えば、そうした実証実験が成功すれば、例えばMRTの駅前に借り出し、返却ステーションを用意して住宅街にもそれを用意することでラストワンマイルに対応するという展開が可能になっていくだろう。
-

- こちらが大きいマーライオン
[ガズー編集部]
あわせて読みたい「シンガポールのMaaS事情」関連記事
-

MaaSで生活はどう変わる? MaaS先進国シンガポールに日本の未来を見る
-

食事もMaaSでOK!! 日本の先を行く、シンガポールのフードデリバリー事情
-

シンガポールへ行く方必見!Grabと同じアカウントで利用できるGrab Foodを使ってみた
-

シンガポールのフード・デリバリー・サービスの老舗~foodpandaを使ってみた
-

欧州発のフード・デリバリー・サービスDeliverooを使ってみた
-

シンガポールのライドシェア・カーシェア・配車サービス事情
-

シンガポール最大のライドシェア、呼んだらすぐ来るGrabを使ってみた
-

Grabを追いかける一番手RYDEを使ってみた
-
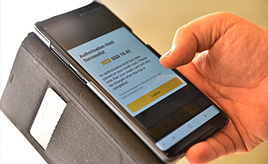
2018年7月に始まったばかりの新ライドシェア・サービスTADAを使ってみた
-

安全安心なタクシーを呼べるタクシー配車アプリ~ComfortDelGroを使ってみた
-

ライドシェアに先駆けて普及したカーシェアリング~Car Clubを使ってみた
-

日本の将来が見える!?シンガポールのシェアサイクル事情
-

QRコードにかざすだけで簡単にシェアサイクルが利用可能なofoを使ってみた
-

日本でもサービスを展開している中国のMobikeを使ってみた
-

シンガポール発のシェアサイクルサービス、SGBIKEの使い方
-

自転車専用道路では最高速25km/hにも達する電動キックボードシェア・サービス~Neuron Mobilityを使ってみた
あわせて読みたい「MaaS」関連記事
-

映画でしか見たことがなかった無人の自動運転車をスマホで呼び出して乗れるMaaSによる近未来とは
-

所有からシェアへと自動車所有の概念を大きく変える「カーシェアリング」
-

シェアパーキング、スマートパーキングという駐車場の新しい潮流
-

ラストワンマイルをカバーするサービスとして期待されているバイクシェア
-

今後数年で急成長が期待できるフードデリバリサービス、その正体は進化した「出前」
-

乗客とドライバーをマッチングさせるライドシェア、タクシーをさらに進化させる配車アプリ
-

人工知能によるスーパードライバーが運転する自動運転車
-

-

配車アプリがタクシーの乗り方の常識を変える!
-

豊田市で展開する超小型電気自動車のシェアリングサービス 「Ha:mo RIDE」
-

都内でちょい乗りに使える超小型電気自動車のシェアリングサービス「Times Car PLUS × Ha:mo」
最新ニュース
-

-
スバルがスーパー耐久に新車両で参戦、カーボンニュートラル燃料…第3戦オートポリス
2024.07.26
-

-
アウディの車載ディスプレイ、壁紙に米サッカー29チーム登場…照明も壁紙の色調に合わせて変化
2024.07.26
-

-
フィアット『グランデパンダ』、ステランティスのセルビア工場で生産開始
2024.07.26
-

-
プレミアムスポーツに進化した、レクサス『LBX MORIZO RR』の全貌[詳細記事]
2024.07.26
-

-
いすゞ『D-Max』を究極のオフローダーに…「Mudmaster」を英国発表
2024.07.26
-

-
ダイハツの小型3列SUV『テリオス』をカスタム、グレーに赤いアクセントが映える
2024.07.26
-

-
ダイハツ『ロッキー』大変身!? アウトドア仕様の「クロスフィールド」に厳つくカスタム
2024.07.26
最新ニュース
-

-
スバルがスーパー耐久に新車両で参戦、カーボンニュートラル燃料…第3戦オートポリス
2024.07.26
-

-
アウディの車載ディスプレイ、壁紙に米サッカー29チーム登場…照明も壁紙の色調に合わせて変化
2024.07.26
-

-
フィアット『グランデパンダ』、ステランティスのセルビア工場で生産開始
2024.07.26
-

-
プレミアムスポーツに進化した、レクサス『LBX MORIZO RR』の全貌[詳細記事]
2024.07.26
-

-
いすゞ『D-Max』を究極のオフローダーに…「Mudmaster」を英国発表
2024.07.26
-

-
ダイハツの小型3列SUV『テリオス』をカスタム、グレーに赤いアクセントが映える
2024.07.26